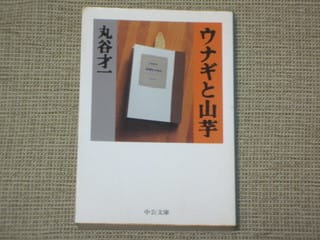小道迷子 平成元年 朝日ソノラマ
『ぴょんにゃらごろごろ』が見つからなくて困っている、どこいっちゃったんだろう。
というのは、本書のタイトルは、表紙にもちゃんと、“また”って付いてんだけど、マンガのタイトルは「ぴょんにゃらごろごろ」であって、これはその第二巻である。
第一巻も持ってたはずで、ここには並べて採りあげようと思ったんだけど、見つからない。
続編だけ残して、最初のを売っちゃったりするわけないんで、合点がいかない。
二十年以上も押し入れのなかに埋もれっぱなしぢゃあ、しょうがないのかもしれないけど、こういうの仕舞うときは揃いで片付けとくはずなのに、見つからないのはきもちがわるい。
さて、マンガのほうは、初出がどこか書いてないんだけど、話の進み方からみれば、たぶん月刊誌連載のもの。
雑誌掲載は知らないけど、『風します?』とか読んでたころに、単行本を本屋で見つけて、あ、こんなのもあるんだって思って買ったんぢゃないかと。
毎回だいたい7ページから9ページくらいの分量。
第二巻である本書は、NO.14からNO.33が収録されてる。ほかに巻頭にカラーの描き下ろし番外編一話。
主人公(たぶん?)の「ごろごろ」は、うさぎ。でも、ふつうのペットぢゃなくて、主婦役の仕事をしていて、家事一般をてきぱきとこなし、日々の家計の節約にもつとめている。
飼い主(たぶん?)の女の子は、あやちゃん。たぶん小学生くらい、わりと天真爛漫。
お父さんは、かつお丸大輔、職業はジャズピアニスト。おかあさんはいない。
あとはレギュラーとしては、店屋物のごはんばっかり食べてるおまわりさんとかいるが、そういうメンバーで毎回どたばたとする展開。
小道迷子らしい謎の登場物体としては、小さいダルマの集団とかが出てきて、画面のあちこちを埋めてたりする。
しかし、どこやっちゃったのかなあ、第一巻。

『ぴょんにゃらごろごろ』が見つからなくて困っている、どこいっちゃったんだろう。
というのは、本書のタイトルは、表紙にもちゃんと、“また”って付いてんだけど、マンガのタイトルは「ぴょんにゃらごろごろ」であって、これはその第二巻である。
第一巻も持ってたはずで、ここには並べて採りあげようと思ったんだけど、見つからない。
続編だけ残して、最初のを売っちゃったりするわけないんで、合点がいかない。
二十年以上も押し入れのなかに埋もれっぱなしぢゃあ、しょうがないのかもしれないけど、こういうの仕舞うときは揃いで片付けとくはずなのに、見つからないのはきもちがわるい。
さて、マンガのほうは、初出がどこか書いてないんだけど、話の進み方からみれば、たぶん月刊誌連載のもの。
雑誌掲載は知らないけど、『風します?』とか読んでたころに、単行本を本屋で見つけて、あ、こんなのもあるんだって思って買ったんぢゃないかと。
毎回だいたい7ページから9ページくらいの分量。
第二巻である本書は、NO.14からNO.33が収録されてる。ほかに巻頭にカラーの描き下ろし番外編一話。
主人公(たぶん?)の「ごろごろ」は、うさぎ。でも、ふつうのペットぢゃなくて、主婦役の仕事をしていて、家事一般をてきぱきとこなし、日々の家計の節約にもつとめている。
飼い主(たぶん?)の女の子は、あやちゃん。たぶん小学生くらい、わりと天真爛漫。
お父さんは、かつお丸大輔、職業はジャズピアニスト。おかあさんはいない。
あとはレギュラーとしては、店屋物のごはんばっかり食べてるおまわりさんとかいるが、そういうメンバーで毎回どたばたとする展開。
小道迷子らしい謎の登場物体としては、小さいダルマの集団とかが出てきて、画面のあちこちを埋めてたりする。
しかし、どこやっちゃったのかなあ、第一巻。