『日本の夜と霧 』(1960)
監督:大島渚
出演者:渡辺文雄
桑野みゆき
津川雅彦
【作品概要】
日米安全保障条約に反対する安保闘争をテーマにした作品だが、公開からわずか4日後、松竹が大島に無断で上映を打ち切ったため、大島は猛抗議し、松竹を退社した。
異例のスピードで制作された。撮影を短くすませるためにカット割りのない長回しの手法を多用し、俳優が少々セリフを間違えても中断せずに撮影を続けたが、そのことが独特の緊張感を生んだ。(Wikipediaより抜粋)

【感想レビュー】
『日本~』繋がりで、今度は大島渚監督の『日本の夜と霧』を観賞 。
。
とにかく、とにかく切迫感が凄まじい。
だんだん慣れてきましたけど、この時代の作品は早口な事が多くて 、役者さん達はややこしい台詞を早口でまくし立てます。
、役者さん達はややこしい台詞を早口でまくし立てます。
そして、噛みまくります 。
。
大急ぎで撮影されたとの事ですから、撮り直しもしなかったのでしょうね
長回しで台詞も噛みまくりという事で、何か舞台を観ているようでした。
津川雅彦さんの早口とか…昨今の作品ではお目にかかれなそう…。噛みまくりだし滑舌もよくないですけど、それだけ台詞を覚えたり練習する時間も無かったのかなぁと思いました。
チープに感じなかったのは、作品全体の緊張感だと思います。登場人物が多いので、青春群像劇の雰囲気です。
50年代の破防法反対闘争と60年代の安保闘争をそれぞれを経験した者達が語ったり討論したり。
その運動の熱が無かったかのように現在の立場に収まっている者。収まろうとしている者。未だその場所に佇む者。
色んな立場で白熱する討論は交わされていく。
そんな中、ずっと劇中音楽に使われているのは、ショスタコーヴィチの交響曲第5番。
さらに劇中でこのレコードを聴くシーンがあるのですが、そこでのショスタコーヴィチの認識は、“社会主義リアリズムの、音楽における最高の成果”という位置付け。
ショスタコーヴィチは、実は反体制の作曲家だったわけですが、これも皮肉な使われ方なのかな。
体制のプロパガンダ音楽と思って聴いていた曲が、実は違った…。
学生闘争を指導し、理屈ばかり言っていた党員がフォークダンスに興じる場面。ラストには声高に演説するも虚しく響くそれ…。
教師が学生寮の自治には口を出さない様子とかなんだか生々しい…。
この作品、1960年という年の空気がとても分かりやすいのですが、この世代で学生運動に参加していた方達はどう感じるのだろう。
いやはや、とっても独特な映画でした
監督:大島渚
出演者:渡辺文雄
桑野みゆき
津川雅彦
【作品概要】
日米安全保障条約に反対する安保闘争をテーマにした作品だが、公開からわずか4日後、松竹が大島に無断で上映を打ち切ったため、大島は猛抗議し、松竹を退社した。
異例のスピードで制作された。撮影を短くすませるためにカット割りのない長回しの手法を多用し、俳優が少々セリフを間違えても中断せずに撮影を続けたが、そのことが独特の緊張感を生んだ。(Wikipediaより抜粋)

【感想レビュー】
『日本~』繋がりで、今度は大島渚監督の『日本の夜と霧』を観賞
 。
。とにかく、とにかく切迫感が凄まじい。
だんだん慣れてきましたけど、この時代の作品は早口な事が多くて
 、役者さん達はややこしい台詞を早口でまくし立てます。
、役者さん達はややこしい台詞を早口でまくし立てます。そして、噛みまくります
 。
。大急ぎで撮影されたとの事ですから、撮り直しもしなかったのでしょうね

長回しで台詞も噛みまくりという事で、何か舞台を観ているようでした。
津川雅彦さんの早口とか…昨今の作品ではお目にかかれなそう…。噛みまくりだし滑舌もよくないですけど、それだけ台詞を覚えたり練習する時間も無かったのかなぁと思いました。
チープに感じなかったのは、作品全体の緊張感だと思います。登場人物が多いので、青春群像劇の雰囲気です。
50年代の破防法反対闘争と60年代の安保闘争をそれぞれを経験した者達が語ったり討論したり。
その運動の熱が無かったかのように現在の立場に収まっている者。収まろうとしている者。未だその場所に佇む者。
色んな立場で白熱する討論は交わされていく。
そんな中、ずっと劇中音楽に使われているのは、ショスタコーヴィチの交響曲第5番。
さらに劇中でこのレコードを聴くシーンがあるのですが、そこでのショスタコーヴィチの認識は、“社会主義リアリズムの、音楽における最高の成果”という位置付け。
ショスタコーヴィチは、実は反体制の作曲家だったわけですが、これも皮肉な使われ方なのかな。
体制のプロパガンダ音楽と思って聴いていた曲が、実は違った…。
学生闘争を指導し、理屈ばかり言っていた党員がフォークダンスに興じる場面。ラストには声高に演説するも虚しく響くそれ…。
教師が学生寮の自治には口を出さない様子とかなんだか生々しい…。
この作品、1960年という年の空気がとても分かりやすいのですが、この世代で学生運動に参加していた方達はどう感じるのだろう。
いやはや、とっても独特な映画でした



















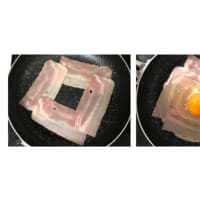

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます