年末に向かうなかでの訃報はいっそうつらい思いにさせられます。
知らせてくれた友人の「まだ若いものなー」が共通の思いです。 その友
人は70歳を越したところ、亡くなった彼はまだ現役の働き手でした、60に
なったばかりでしょう。
三か月ほど前に 「助からないようよ」 と知らせてくれたのは新宿での仕
事仲間で、在京の仲間の世話役をかってくれているご婦人。彼女の話で、
二人の娘さんが共に30歳を越しているが、二人とも独り者だとのことでし
た。 その時も今日もそのことが気にかかります。
彼だって娘さんのことが気になっていたに違いありません。彼と一緒に出
かけたのは昨年、同じ仕事場の仲間の墓参りでした。 そのことはこの 「つ
ぶやき」 でも触れたと思いますが、生涯独身であった彼女の墓参りでの話
でも、自分の娘さんのことが頭にあったことでしょう。 家族・家庭のあり方
も喜びもそれが成りったってからの話で、今日のように晩婚とか未婚とか、
周りに多く見られるとき、日常の生きる張合いと家庭をもつことが、一体に
ならない、家庭をもつことが不安であるという状況をひとりその人の責任と
か考え方とかに限らず、雇用の保障とか保育問題など社会的な生活の裏
付けを確立することが前提となるでしょう。
年賀状の話も出る時期ですが、同時に年賀欠礼状をもらう時期でもありま
す。 ひとり一人の生活の底に生死のことが深く関わっていることに目を届
けていきたいものです。











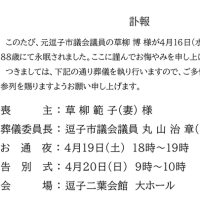



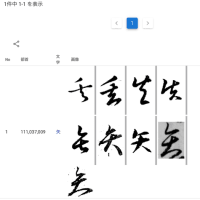




昨日の講座でも50代で結婚してない人が、数年前の3倍にも上り、その要因の一つに、社会保養の乏しさ、と合わせて食事などはコンビニで手に入り、洗濯も自分でしなくてもよい時代、ということも言われました。
でもやがて晩年を迎え、身内もない、パートナーも居ない時代をどう埋め合わせられるのか。
そんなことまで考えさせられる訃報ですね。
た。昨日知らせてくれた友人などが手分けして連絡を取
っているのでしょう。
50代の「孤独死」というようなこともある中で、よき友人
に恵まれていたというべきでしょうが、命を守るというよう
な事はやはり友人の手に余るように思われます。
チトセさんの昨日の講演の演題「ひとりの時代」の「ひとり」が「一人か独り」で意味が異なってくることもあるでしょう。