昨夜は月齢14.8、満月、満月を望月ともいいます。
望月といえばこの和歌
此の世をば我が世とぞ思ふ望月のかけたることもなしとおもへば
平安時代栄華を極めた藤原道長がこれを詠んだのは、娘たちを入内させ
三代天皇の外威となり全盛期を迎えた時・1018年でした。
その二年前、同じく月を詠んだ和歌でも
心にもあらでうきよにながらへば恋しかるべき夜半の月かな
は、その道長に天皇の位を追われた三条天皇の和歌で、『百人一首』に
もとられています。
道長・三条などの天皇貴族間、貴族対貴族などの権力闘争において、各々
のガードマン的役割をはたしていた「兵=つわもの」が時代を背負って立つの
は、平安時代の次の時代、鎌倉幕府よって幕が開かれた「武士の時代」です。
昨夜、この湘南の地では僅かの時間、雲間から満月がアリバイ証明的に見
られましたが、ところ変われば見えたり見えなかったりだったでしょう。それ以
上に参議院選を終えたあとのそれぞれで、見えるもの見えないものがあった
ことでしょう。
月の満ち欠けが「天体の理(ことわり)」であるならば、時代の推移は「社会
の理」、その遅速は「政治の理」であり「人心の理」です。
この間、詠み手はどんな心を詠んだのでしょう。「赤旗」紙の歌・句・詩に注目
したいと思います。











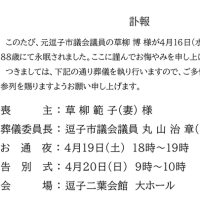



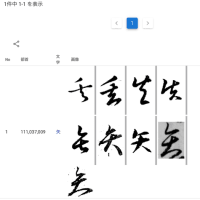




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます