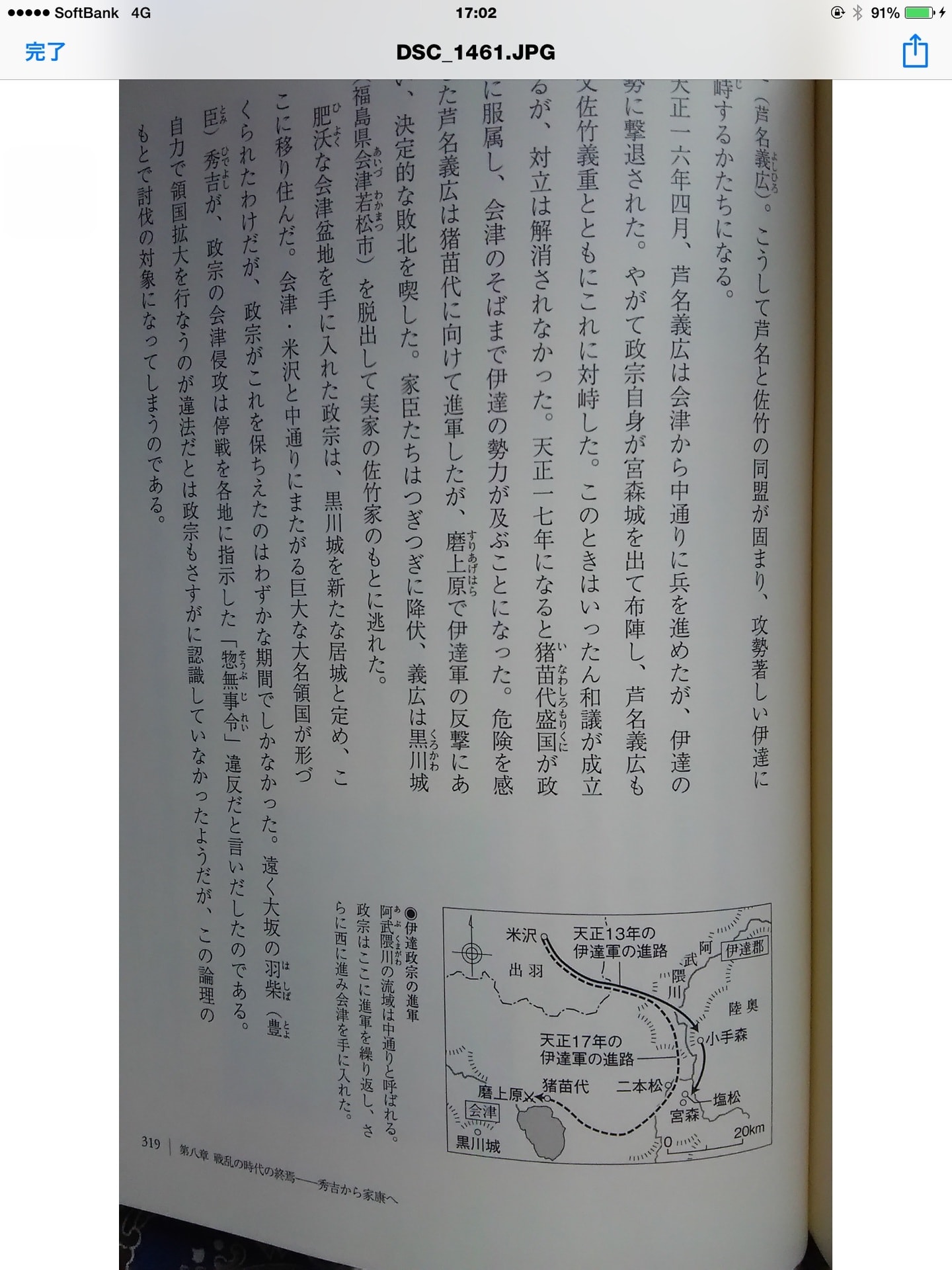このタイトルは平山優さんの『真田信繁』の第2章「関ヶ原合戦と上田城攻防」の第ニ節そのままです。
その第1節が「兄信幸との訣別」ですから「犬伏の別れ」です。
前回のタイトルを “「犬伏の別れ」はあったか” にしました。それは平山さんのこの本によって「史実としての犬伏の別れ」考だったわけです。さて今回も史実としての「第二次上田合戦」は? というところからはじまります。
例により該当部分を引用します。
【 徳川秀忠の任務
通説によると、秀忠は中山道を進んで真田昌幸を攻め潰し、しかるのちに家康本隊と合流して石田三成との決戦に参加する予定であったが、上田城に手こずり関ヶ原の決戦に間に合わず、父家康に叱責を受けたといわれている。だが果たして本当なのだろうか。これは通説的な関ヶ原合戦像の再検討にも帰着する課題といえる。この通説に疑問を提起し、秀忠の動向に再検討を加えたのが笠谷和比古氏である。以下、笠谷氏の業績に導かれながら、秀忠遅参説を再検討しておく。】(提示された説の史料について表示されていますがここでは略します。)
ここでもやはり史実としての「第二次上田合戦」像を求める姿を感じます。歴史学者としては当然ですが、史実にもとづく歴史への理解を拡めることも学者とてあるべきことだと思い、平山さんの本を引用する次第です。
このあと
【 実は史料を見ていくと、秀忠の任務は当初から明確で、八月二十三日付で在陣する宇都宮から岡田庄五郎に宛てた書状で、「信州(州は別字)真田表為仕置、明廿四日令出馬候」とあり、真田昌幸征討こそが彼の目的であった。同日付で秀忠は、野間久左衛門尉や平野九左衛門にもまったく同じ発言をしている。
また八月二十八日付の黒田長政宛書状でも「信州真田表仕置」が進軍の目的だと述べている。それは家康も当然承知していたことであった。真田をそのままに放置しておけば、信濃や甲斐が危険に曝されるし、上杉景勝の動き次第では、沼田も危険だとの認識が徳川方には確実にあった。実際に信幸は、家康より第二次上田合戦直前の九月一日、坂戸から三国峠を越えて敵が侵攻する危険性を指摘され、用心するよう求められている。
家康は、家臣青山忠成を使者として秀忠のもとへ派遣し、御諚(指示)を出している。これを受けて八月二十六日付で秀忠は、本多正純・村越直吉に宛てて「真田表之儀、少も油断申間敷候」と述べており、家康の「御諚」の趣旨が、真田昌幸討伐にあったことは明白だろう。
さらに、第二次上田合戦の真っ最中にあたる九月九日に、秀忠が家康とともにいた伊井直政・本多忠勝に宛てた返書で、京極高知が赤坂に到着したので、こちらの作戦に参加することは延引するとのことは了解した。こちらは真田表の仕置を行った後に、近日中に上方へ向かうこととすると述べている。つまり秀忠は、上方での戦局如何にかかわらず、真田討伐に専念すればよかったことがわかる。】
そして、
【 だが事態は急展開する。】と続くのですが長くなりました、また明日にしたいと思います。