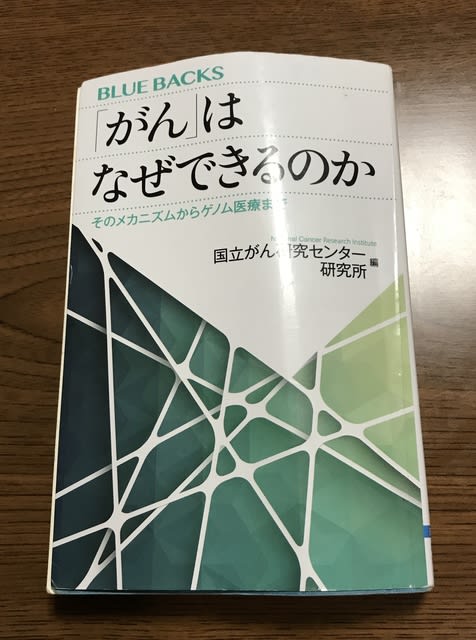書き手のシッダールタ・ムカジーがこう書いています。
「私が書いていたのは、ある病気の歴史というよりも、より人間的で、より感情的なもの、そう、伝記だった」
続いて、
〝 伝記ならば、私も伝記作家の例に洩れず、まずは主人公の誕生から書きはじめたいと思う。がんはどこで「生まれたのか?」 がんは何歳なのか? がんを最初に病気として記録したのは誰なのか?〟
これらの?への答えが、
一八六二年のこと、エドウィン・スミスという一風変わった人物ーー学者でもあり、小売り商人でもあり、骨董品の偽造者でもあり、たたき上げのエジプト学者でもあったーーが、エジプトのルクソールの骨董品売りから四 ・五メートルの長さのパピルス写本を買った(一説には、盗んだとも言われている)。写本は実にひどい状態で、今にも粉々に崩れそうな黄ばんだぺージには古代エジプトの筆写体文字がびっしりと書かれていた。今日ではそれは紀元前一七〇〇年に写本された、紀元前二五〇〇年の文書と考えられている。写本した人物一ー大慌ての盗用者ーーはいくつよものミスを犯しており、余白に赤いインクで修正が書き込まれている。
そのパピルス写本は一九三〇年に翻訳され、今日では、紀元前二六二五年前後に活躍した偉大なエジプト人医師、イムホテプの教えを集めた書と考えられている。現在知られている王室の血を引かない数人の古王国時代エジプト人の一人であるイムホテプは、急速に発展するエジプト文化の中心にいたルネサンス的教養人で、ジェセル王朝の宰相をつとめながら、脳神経の手術をおこなったり、建築に手を出したり、占星術や天文学の世界を覗いたりした。それから何世紀も経ったあとでエジプトに行軍したギリ シャ人ですら、彼の知性の熱風に遭遇したあとでイムホテプを魔法の神と崇めるようになり、ギリシャの医神アスクレーピオスと同一視したほどだった。
だが、スミスのパピルス写本の驚くべき特徴は、魔法や宗教ではなく、魔法も宗教も登場しないという点だ。魔法や呪文や魔力に浸りきっていた世界にあって、イムホテプは、折れた骨や椎骨脱白について、まるで現代の外科の教科書のように、客観的かつ淡々とした科学用語で書き記している。パピルス写本に登場する四八症例ーー手の骨折、ばっくりと開いた皮膚の膿瘍、粉々に砕けた頭蓋骨ーーはどれも神秘的な現象としてではなく、解剖学的な用語や診断名や経過や子後を持つ、医学的な状態として扱われているのだ。
古代の外科医療のそんな明断なヘッドライトの下で、がんは歴史上初めて、他と区別された一つの疾患として登場する。症例四五についての説明のなかで、イムホテプ は次のように助言している。「乳房に隆起する塊のある(症例を)診察し、その塊がすでに患者の乳房全体に広がっており(その)乳房に手を置いた(ときに)冷たくて、塊自体も熱を持っておらず、肉芽がなく、切開しても液体の貯留がなく、乳汁の分泌もないが、触診で明らかに盛り上がっている場合には、その症例についてこう言わねばならぬ。"これは隆起するしこりの病である..….乳房の隆起するしこりは、しだいに広がる大きな硬い腫癌が乳房に存在することを意味する。手で触れた感じは丸めた梱包用の布や、まだ熟していない硬く冷たい血液の果実のようだ"」
「乳房の隆起するしこり」 ーー冷たく硬く、血液でできた果実のように身が詰まっており、皮膚の下を秘かに広がっていくーーという表現は、乳がんの描写としてはこれ以上望めないほどに鮮明だ。パピルスに記載された症例には必ず、たとえそれがただ単に症状を緩和すそためのものであっても、治療に関する簡潔な考察が添えられていた。たとえば、脳神経外科の患者の耳にはミルクを注ぎ、傷にはハップ剤を貼り、火傷には香油を塗る、といったよらに。だが症例四五については、イムホテプは珍しく沈黙している。「治療」と題したセクシンで彼が書いたのはたった一文だった。「治療法はない」
さて「伝記」でこう書かれていることを短く言うと、こちらでは、
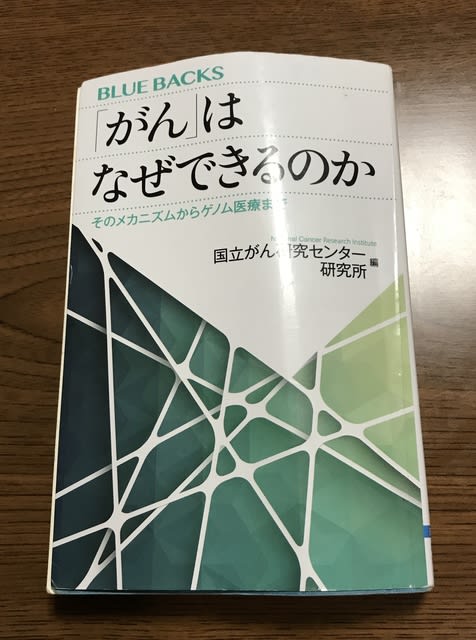
がんに関して現存する最古の記録は、紀元前2600年頃に活躍した古代エジプトの医師イムホテプが残したものだといわれています。48の症例を記載しているなかのひとつとして、「乳房の隆起するしこり」を取り上げ、「冷たく固く、血液でできた果実のように実が詰まっており皮膚の下をひそかに広がっていく」と表現しており、これが乳がんに関する記述であると考えらているのです。
と書かれています。
人間の記録にはじめて登場した「がん」は医師イムホテプに「治療法はない」と言わしめ、次に記録されるまでの2000年間「沈黙の覆いにつつまれます」。