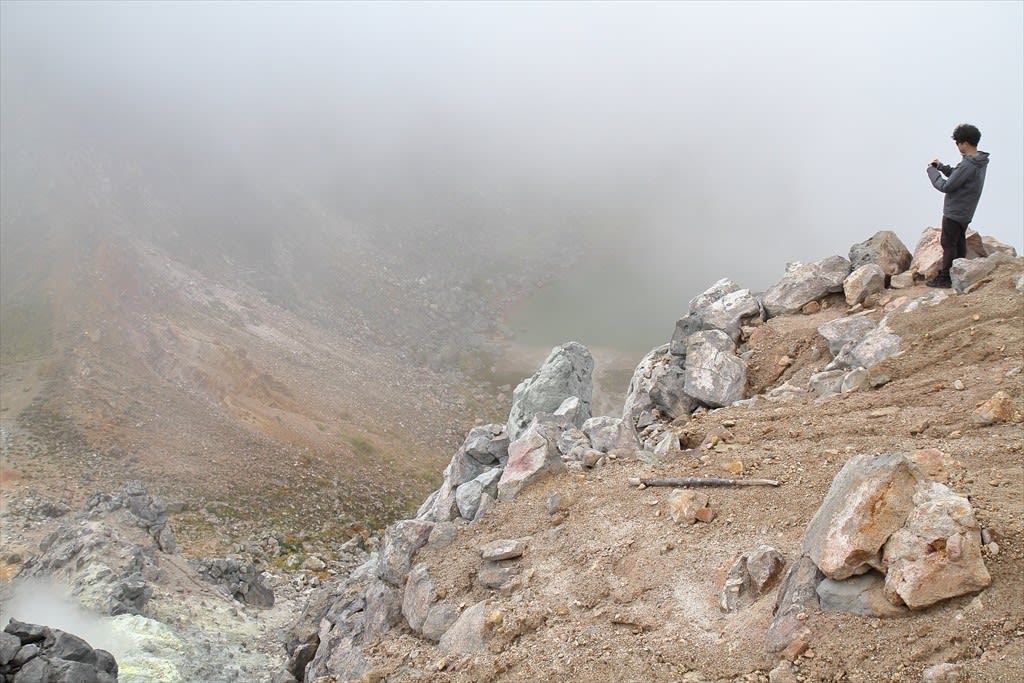2023年10月2日(月)
御嶽スキー場からの星景 (4:36)
前日の登山口調べ&観光は雨~曇りの空だったが、10/2は予報通り晴れることを信じ 4:00に宿を出る。 日の出は 5:45頃であったがどこかで星景を撮りたいと思っていたので早目に出発。 だが、実際どこで星を撮るかは決まっていなかった。 前日の登山口調べで御嶽山を入れての星景を撮るには登山口しかないことは分かったが、登山口では御嶽山に近すぎて空を多く入れることができない。 空を多く入れるにはスキー場からなら中央アルプス木曽駒ケ岳などを入れ撮れそうだが、車を停められそうな場所が見つけられなかった。 前日はスキー場のカーブの多い細い道に少し苦労したので、とにかく早く出て、星は撮れなくても朝景くらいはきちんと撮りたいと思っていた。
前日走っていたせいか、暗やみでもスキー場の道を案外スムーズに進むことができた。 更に良い場所に広めの路側帯を見つけ駐車できた。 そこで撮影したのが上写真。 下の方の光の筋は登山口に向かう車のヘッドライト。 平日なのにこの時間から数台上ってきた。

高い位置にオリオン座が見えたので縦構図で。
サッサと撮って登山口へ。
結局この日は 9/29の満月が少し欠け始めたとても明るい月が出ており、
しかも登山口に着くと御嶽山のすぐ左に見えたため、御嶽山と星 or 月、はボツ。

前日、田の原湿原散策で確認した展望台から中央アルプスの朝焼け。( 5:34)
背後に見えているのは南アルプス。 左端奥は奥秩父、北奥千丈岳あたり。

気温は低く、真っ赤に紅葉したクロマメノキ?の葉には霜が。
木道にも霜が降り、滑って転ばないようヒヤヒヤ。
それでも展望台とは反対側の散策路へ急いで移り。。。

御嶽山モルゲンロート (5:46)
寒かったがダウンを着るほどでもなく、天気予報の強風もなく、
やりたいことができて満足。

あとはしっかり登るのみ。(6:25)
本当に良い天気だ!

出だしは王滝頂上奥社遙拝所まではこのように歩きやすい平坦な道。
遙拝所の屋根が中央奥に見える。

斜面の黄葉も進んでいるようだ。
田の原口からの登山道は王滝頂上奥社までとにかくまっすぐなので、
この写真でも登山道が良くわかる。

30分ほど登ると大江権現。
明治10年以前、女性はここまでしか登ることができなかった。
遙拝所を過ぎると上る斜面が急になるが、この先更に急になってゆく。

「あかっぱげ」と呼ばれる所。
この辺りから見るカンバの黄葉が素晴らしかった。

登山道はよく整備されているが、そのうち岩々になってくる。

黄葉の美しい斜面。

南、奥に見える高い山は恵那山らしい。

八合目下の「金剛童子」と「中央不動」
岩々になり更に斜度もますが、どうも始めから息苦しくすぐにゼーゼーしてしまう。
登山口で既に標高 2,180m あり空気が薄いせいかと思っていたが、
どうも春や秋の始めは花粉や空気の温度差でこうなるのかもしれない、と思うこの頃。
ただ、周りの人たちも結構ゼーゼーしていた感じ。w

八合目石室到着。 (7:41)
とりあえず何かあるたびに目標になるし、その場で休んで息を整える。
体力や足腰の不調はないのが幸い。

次は九合目避難小屋に向けて歩くのだが、上の方に白く四角く見える所が避難小屋。
近く見えるので気持ち的には楽なのだが、これがなかなか到着しない。

立ち止まって息を整えながら少しずつ登ってゆく。
フ~、と振り返る。
出発地点も近くに見えるので「これしか上っていないのに。」と何だか微妙。

たくさんのシラタマノキの実。

ハイマツ斜面の向こう、南アルプスも良く見えるようになってきた。
高く見えるのは甲斐駒ヶ岳。 左奥には八ヶ岳。

九合目避難小屋到着。 (8:45)
朝早くから屋根の修理をされていた。
本当に遠くまで良く山が見える、と思っていると近くの人が「富士山だ。」と。

あら本当だ!
こんな感じ ↓


紅葉もナナカマドが7合目付近で色づいていたが、山の上はクロマメノキ?が真っ赤。
南アルプス、右奥には悪沢岳、赤石岳、光岳などが続く。

こちらも草紅葉の向こうに八ヶ岳連峰。

ようやく王滝頂上避難施設が見えてきた。

王滝頂上避難施設到着。(9:22)
避難小屋の前には素敵なベンチがいくつも置かれていたので八丁ダルミに備えここでおやつ休憩。
ここに座る際、ベストを着た指導員のような方がいたので座って休憩して良いのか尋ねた。
王滝頂上避難施設は、2014年の噴火の際王滝頂上山荘が被災し、その後取り壊しになった跡地に王滝村が作った防災施設だ。
噴火に備え外壁や屋根が強化され、施設全体で180名を収容できる施設になっている。
ヘルメットなども用意され(100個程度)、シーズン中にはパトロール員が常駐されている。
先ほどの方はパトロール員の方なのだな。

王滝頂上御嶽神社奥社
ここで参拝し、八丁ダルミを歩いて剣ヶ峰を目指す。