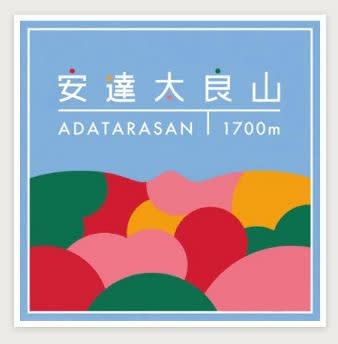2020年8月19日(水)
雨飾山山頂北峰から後立山連峰を望む

ようやく笹平に到着。( 9:20 )
ここまでの登りで帽子を通して頭に強い日差しを感じ、軽くクラッとするような感じもした。
こんな風に感じたことは初めてだと思い、水分補給をして、深呼吸をして、さらにゆっくり進むようにした。
もうゴールは目の前だからゆっくり、慎重に。

笹原も長く歩きそうだし、最後の登りも堪えそうだ。
と思っていると右手に日本海が見えた! あの辺が糸魚川か!

雨飾温泉からの登山道と合流。

お花が咲く笹原を歩き

進んでゆくと

とうとう山頂直下。

最後の登り、しんどそうだなぁ~、と思っていると、
なんとトレイル両側は素晴らしい花園!

あふれるほどにお花が咲いており、なかなか先に進まない。

というか、こんなにお花が見られたら、山頂に着かなくてもいいか、
と登りたくない言い訳にしたりして。

もうお花を撮りながらゆっくり、ゆっくり。

登りたくないと言っても山頂はもうあと少し。

もちろん登らないわけはないのだ。

はぁ~、と思いつつ登ってきたトレイルを振り返ると、
女神さまだ! 笹原に女神さまの横顔。
お会いできて良かった~!!

ほどなく山頂に到着。( 10:10 )
素晴らしい眺めだぁ~!!
直後に到着された方と記念撮影をし合い、
「お天気良くて眺めが最高ですね~!」と喜び合う。

「あれ? 双耳峰のもう一方はどこ?」と思ったら、後方にあった。

まずは到着した北峰から後立山連峰を眺める。
ちょうど中央一番高い頂が白馬岳。 右の方に高いのが雪倉岳、さらに右に丸く高いのが朝日岳。

白馬岳をアップで。
左に雲が掛かっているのが杓子岳、白馬鑓ヶ岳ケ岳。
白馬岳左手前辺りが乗鞍岳だそう。 右の高いピークが雪倉岳。

白馬岳左方は左から鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬鑓ヶ岳、杓子岳。
唐松岳右後方には立山がのぞいている。

鹿島槍ヶ岳より左方には爺ヶ岳。
少し離れた左方に槍ヶ岳。
さらに左方には穂高連峰、大天井岳、東天井岳、常念岳などが続いているようだ。

もう一度白馬岳から日本海へ続く山並み。

南方向には大きくそびえる乙妻山、高妻山、その右方奥に戸隠の山々。
さらに奥の方に見えるのは南アルプスの山々らしい。

充分休憩をして、お昼ご飯も食べ、南峰に行ってみる。
南峰左奥には手前に裏金山、金山、天狗原山かな。
そしてその左奥に焼山、火打山の頂。

南峰から後立山連峰。

南峰から北峰と日本海を望む。

糸魚川市方面。 田んぼの間には姫川が日本海まで流れている。
雨飾山の双耳峰は「猫の耳」と呼ばれている。 小谷村の各所からその姿が見られ、
古来から山頂に祭壇を祀り雨ごい祈願をした神の山だ。
糸魚川の漁師たちは漁に出るとこの二つの頂を目標にしたそう。
あの向こうの田んぼから、日本海から、雨飾山を見るのも良いだろうな。

雨飾山の女神様は高志国(こしのくに=越国)の女王、
翡翠で祭事を行った女神、奴奈川姫(ぬなかわひめ)様なのかな。
そろそろお別れをして下山する。

山頂では素晴らしい景色を眺め、おかげで色々な方と山の話をしたりして、
1時間半くらい滞在してしまったようだ。

せっかく早朝から登り、こんなに美しい場所にたどり着いたのだから、
そんな過ごし方も良いだろう。
既に写真もたくさん撮り、急な下りを慎重に下山するため、
もう写真はあまり撮らなかった。
荒菅沢ではザックを降ろし、帽子を取って顔を洗い、頭にも水を掛けた。
サケを採るクマのように水の中でバシャバシャしたかった程、だった。

それでも 14:30には下山できた。
帰路の荒菅沢からの登り返しは危惧したほどではなかったが、
往路山頂までの登りは大変だった~。 けれどその価値は十分にあったと思える山だった。

ヤマスタもGetでき、うれしい。 左下のお花はサンカヨウだそう。 そうだ。 今度はサンカヨウ、キヌガサソウが咲くころにまた登ってみたい。