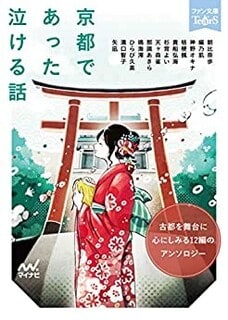思い立って短編を書きました(現実逃避←ギク)。
Berry's Cafeでも無料公開しています。
ファーストキスは予約済み
ある寒い冬の日。あたしはたった一言を切り出せなくて、ただじっと奏汰(かなた)兄(にい)の背中を見ていた。年上の幼馴染み、奏汰兄のベッドに腰掛けて、じっと固まって、もう三十分くらいずっとそうしている。あたしから見えるのは、洗いざらしのダンガリーシャツにざっくりしたセーター、ネイビーのジーンズの後ろ姿。暗めの茶髪の頭だけ。
奏汰兄はといえば、窓に向き合うデスクに座ってずっとあたしに背を向けている。大学三回生の奏汰兄は外交官を目指していて、来年度の公務員試験の勉強の真っ最中だ。
なにも言えずにもじもじしているあたしにしびれを切らしたのか、奏汰兄がチラとも後ろを見ずに言う。
「なんの用」
冷たいんだね。あたし、今、ものすごく必死で勇気をかき集めてるのに。
「奏汰兄、あたしね」
「うん」
奏汰兄の生返事。
「あたしね、フランスに行くことにした」
その一言を言うために、どれだけの勇気がいったか。でも、奏汰兄の返事はつれない。「ふーん」の一言。
あたしは奏汰兄の枕を取って、背中に投げつけた。
「ってーな」
ようやく振り返った奏汰兄。でも、ものすごく不機嫌な顔。
「あたし、フランスに行くんだよ!?」
あたしは立ち上がって両手をギュッと握り、叫ぶように言った。奏汰兄は長めの前髪をかき上げてあたしを見た。
「聞こえた」
「そうじゃなくてっ!」
イライラする私にお構いなしに、奏汰兄はふぅと息を吐いた。
「フランス留学は夢だったんだろ? 子どもの頃読んだ小説でフランスが大好きになって、フランス語をマスターしたいって言ってたじゃないか」
「そうだけどっ」
「よかったじゃないか。交換留学プログラムを利用して、高一のうちから海外に行けるなんて。そんなチャンス、めったにないぞ」
「奏汰兄はそれでいいのっ!?」
「いいも悪いもないだろ。フランス文学翻訳者になるって夢があるんだから、しっかり勉強してこいよ」
いつもどおり冷静な奏汰兄の言葉に、あたしのイライラがピークに達した。同時に涙もピークに達して、目からぶわっと涙があふれ出す。
「奏汰兄なんか、もう知らないっ! バカバカ、大バカっ!」
それだけ言って奏汰兄の部屋を飛び出した。階段を駆け下りて、玄関で靴を履く。
「あらー、愛海(まなみ)ちゃん、もう帰るの?」
キッチンの方からおばさんののんびりした声が聞こえてきた。奏汰兄のお母さんだ。
「お邪魔しましたっ」
あたしは言って、川西(かわにし)家の玄関ドアを閉めた。道を渡って、向かいにある東田(ひがしだ)家の玄関ドアを開けて、我が家に飛び込んだ。階段を駆け上がって自分の部屋のドアを開け、ベッドにダイブする。スプリングが勢いよく弾み、やがてそれが落ち着いていく。でも、あたしの気持ちはぜんぜん落ち着かない。
なによ、なによ。なにが『よかったじゃないか』よ。奏汰兄はあたしがフランスに行っても寂しくないんだ。バカバカバカ。奏汰兄なんか大嫌いっ!
お向かいに住んでて、あたしの五歳年上で、いつもお兄さんぶってて偉そうで。あたしがどんなわがままを言ってもすまし顔でさらりとかわして。
小一のとき、あたしがクラスの男子にランドセルにカエルを入れられそうになって泣いてたら、すっ飛んできて助けてくれた。
小五のとき、奏汰兄にあげようとがんばって手作りしたのに、失敗してしまったバレンタインのチョコレート。べそを掻きながら渡したら、『おいしいよ』って笑って食べてくれた。分離してぼろぼろになってたチョコレート、絶対おいしくなんかなかったはずなのに。
中三のとき、模試の成績が悪くて落ち込んで泣いてたら、『俺が勉強見てやるから元気出せ』って言ってくれた。奏汰兄のおかげで、今の高校に合格できた。
大嫌い。奏汰兄なんて大嫌い! あたしのこと、近所の年下の幼なじみとしか思ってないのなら、やさしくなんかしないでよ! 今まで……あんなふうにやさしくされなかったら、あたし……奏汰兄のこと、こんなに好きにならなかったのに……。
『もう勝手にひとりで行っちゃうからね。バカ!』
LINEでメッセージを送った。かまってちゃん丸出しだ。でも、奏汰兄にとってあたしは子どもだってわかってるから、かまってもらうしかないじゃない。それ以上の存在になれないってわかってるから……。
奏汰兄の返信メッセだってそれを物語ってる。
『バカはそっちだ。高校生にもなって、男の部屋でベッドに無防備に座るな。フランスに行ったら気をつけろ』
ほらね。保護者ぶっちゃって。もう知らないっ。
***
その一ヵ月後、いよいよ旅立ちの日がやってきた。あたしは関西国際空港の国際線のセキュリティチェックの列に並んだ。振り返って、お母さんとお父さんに手を振る。いつもどっしり構えているお父さんと違って、心配性のお母さんは今にも泣き出しそうな顔をしている。
「大丈夫、寮には日本人の女の子もいるし、しっかり勉強してくるから!」
「気をつけてね」
お母さんが心配顔で手を振った。あたしはうなずいて前を向く。
クラスの友達は前日にうちに来てお別れパーティを開いてくれた。でも、今はどこにいてもLINEでつながれるし、そんなに寂しい気はしない。そうだよ、いつでも連絡取れるから。
でも、公務員試験の勉強に集中したいから、という奏汰兄とはLINEもできないし、電話だってかけられない。留学期間の一年間、声さえ聞けないのだ。それなのに、奏汰兄はバイバイの一言も言いに来てくれなかった。
大嫌い、大嫌い……。別に奏汰兄に見送ってもらわなくたっていいもん。一人でがんばれるもん。一人で行けるもん……。
なのに、おかしいな。目の前がにじんできて、前がよく見えない。
あたしは立ち止まって、コートの袖で目をごしごしとこすった。
大嫌いなはずなのに、奏汰兄のことを考えたら涙が止まらない……。止まらないよ……!
そのとき、あたしの横に誰かが立った。セキュリティチェックを急ぐ人なのかと思って、あたしは一歩左によけた。それなのに、その人は進まない。どうして、と思ったとき、聞き慣れた声が聞こえてきた。
「手荷物検査、受けないのか?」
ハッとして顔を上げたら、柔らかく微笑む奏汰兄が横に立っていた。
「なんで……?」
奏汰兄がそっと右手を伸ばしてあたしの頬に触れた。びっくりして涙が止まる。
「夢を叶えに行くのに、なんで泣いてんだよ」
「だって」
「愛海は泣き虫だからな。きっと俺が見送りに行かないと泣いてるだろうなと思ったんだ」
「別に……泣いてなんか」
ないもん、と言ったとたん、ひっく、としゃくりあげてしまった。
「愛海、俺は公務員試験がんばるよ。ずっと働きたいと思ってた外務省に入るためにな。だから、愛海もがんばれ。おまえの訳したフランス文学を読めるのを、俺は楽しみにしてるんだからな」
あたしは手を伸ばして、奏汰兄のカーキ色のコートをキュッとつかんだ。
「でも……一年も……」
寂しいもん、と言いかけたとき、奏汰兄が顔を傾け、あたしの頬にチュッとキスをした。びっくりして目を見開いたまま、奏汰兄を見る。奏汰兄が照れたように小さく笑って、人差し指で頬を掻いた。
「唇は予約した」
「え?」
奏汰兄が人差し指を伸ばしてあたしの唇に触れた。長い指先が唇をなぞって離れる。
「一年後、帰国したらもらうから。それまで俺が予約したんだからな。ほかの男にやるなよ」
奏汰兄の瞳に、強い光が宿った。胸がドキンと大きく跳ねる。
「奏汰兄……っ」
胸が熱くなって、また泣いてしまいそうだ。
奏汰兄があたしの頬にもう一度触れた。
「泣くのは俺の前だけにしろ。一年後まで、顔を上げて行け。俺の大好きな笑顔で行け」
奏汰兄があたしの背中を大きく叩いた。その力強さに押されて、一歩足を踏み出す。
「来年、胸を張って会えるように、笑って行け。俺も採用通知と一緒に愛海を待ってるから」
「うん、うん」
あたしは何度もうなずいた。こぼれそうになる涙を、顔を上げて瞬きをして散らす。唇を引き結び、口角を引き上げて、奏汰兄を見た。奏汰兄が大きくうなずく。
「行ってこい」
「うん、行ってきます」
「帰ってきたら、俺を“兄”なしで呼べるように、練習しとけよな」
あたしはコクンとうなずく。奏汰兄が……大好きな奏汰が……大きく手を振ってくれた。
がんばろう。帰ってきたとき、奏汰にふさわしい彼女になれるように、胸を張れるように。
あたしは笑顔でセキュリティチェックに向かった。背中に大好きな人の温かな視線を感じながら……。



Berry's Cafeでも無料公開しています。
ファーストキスは予約済み
ある寒い冬の日。あたしはたった一言を切り出せなくて、ただじっと奏汰(かなた)兄(にい)の背中を見ていた。年上の幼馴染み、奏汰兄のベッドに腰掛けて、じっと固まって、もう三十分くらいずっとそうしている。あたしから見えるのは、洗いざらしのダンガリーシャツにざっくりしたセーター、ネイビーのジーンズの後ろ姿。暗めの茶髪の頭だけ。
奏汰兄はといえば、窓に向き合うデスクに座ってずっとあたしに背を向けている。大学三回生の奏汰兄は外交官を目指していて、来年度の公務員試験の勉強の真っ最中だ。
なにも言えずにもじもじしているあたしにしびれを切らしたのか、奏汰兄がチラとも後ろを見ずに言う。
「なんの用」
冷たいんだね。あたし、今、ものすごく必死で勇気をかき集めてるのに。
「奏汰兄、あたしね」
「うん」
奏汰兄の生返事。
「あたしね、フランスに行くことにした」
その一言を言うために、どれだけの勇気がいったか。でも、奏汰兄の返事はつれない。「ふーん」の一言。
あたしは奏汰兄の枕を取って、背中に投げつけた。
「ってーな」
ようやく振り返った奏汰兄。でも、ものすごく不機嫌な顔。
「あたし、フランスに行くんだよ!?」
あたしは立ち上がって両手をギュッと握り、叫ぶように言った。奏汰兄は長めの前髪をかき上げてあたしを見た。
「聞こえた」
「そうじゃなくてっ!」
イライラする私にお構いなしに、奏汰兄はふぅと息を吐いた。
「フランス留学は夢だったんだろ? 子どもの頃読んだ小説でフランスが大好きになって、フランス語をマスターしたいって言ってたじゃないか」
「そうだけどっ」
「よかったじゃないか。交換留学プログラムを利用して、高一のうちから海外に行けるなんて。そんなチャンス、めったにないぞ」
「奏汰兄はそれでいいのっ!?」
「いいも悪いもないだろ。フランス文学翻訳者になるって夢があるんだから、しっかり勉強してこいよ」
いつもどおり冷静な奏汰兄の言葉に、あたしのイライラがピークに達した。同時に涙もピークに達して、目からぶわっと涙があふれ出す。
「奏汰兄なんか、もう知らないっ! バカバカ、大バカっ!」
それだけ言って奏汰兄の部屋を飛び出した。階段を駆け下りて、玄関で靴を履く。
「あらー、愛海(まなみ)ちゃん、もう帰るの?」
キッチンの方からおばさんののんびりした声が聞こえてきた。奏汰兄のお母さんだ。
「お邪魔しましたっ」
あたしは言って、川西(かわにし)家の玄関ドアを閉めた。道を渡って、向かいにある東田(ひがしだ)家の玄関ドアを開けて、我が家に飛び込んだ。階段を駆け上がって自分の部屋のドアを開け、ベッドにダイブする。スプリングが勢いよく弾み、やがてそれが落ち着いていく。でも、あたしの気持ちはぜんぜん落ち着かない。
なによ、なによ。なにが『よかったじゃないか』よ。奏汰兄はあたしがフランスに行っても寂しくないんだ。バカバカバカ。奏汰兄なんか大嫌いっ!
お向かいに住んでて、あたしの五歳年上で、いつもお兄さんぶってて偉そうで。あたしがどんなわがままを言ってもすまし顔でさらりとかわして。
小一のとき、あたしがクラスの男子にランドセルにカエルを入れられそうになって泣いてたら、すっ飛んできて助けてくれた。
小五のとき、奏汰兄にあげようとがんばって手作りしたのに、失敗してしまったバレンタインのチョコレート。べそを掻きながら渡したら、『おいしいよ』って笑って食べてくれた。分離してぼろぼろになってたチョコレート、絶対おいしくなんかなかったはずなのに。
中三のとき、模試の成績が悪くて落ち込んで泣いてたら、『俺が勉強見てやるから元気出せ』って言ってくれた。奏汰兄のおかげで、今の高校に合格できた。
大嫌い。奏汰兄なんて大嫌い! あたしのこと、近所の年下の幼なじみとしか思ってないのなら、やさしくなんかしないでよ! 今まで……あんなふうにやさしくされなかったら、あたし……奏汰兄のこと、こんなに好きにならなかったのに……。
『もう勝手にひとりで行っちゃうからね。バカ!』
LINEでメッセージを送った。かまってちゃん丸出しだ。でも、奏汰兄にとってあたしは子どもだってわかってるから、かまってもらうしかないじゃない。それ以上の存在になれないってわかってるから……。
奏汰兄の返信メッセだってそれを物語ってる。
『バカはそっちだ。高校生にもなって、男の部屋でベッドに無防備に座るな。フランスに行ったら気をつけろ』
ほらね。保護者ぶっちゃって。もう知らないっ。
***
その一ヵ月後、いよいよ旅立ちの日がやってきた。あたしは関西国際空港の国際線のセキュリティチェックの列に並んだ。振り返って、お母さんとお父さんに手を振る。いつもどっしり構えているお父さんと違って、心配性のお母さんは今にも泣き出しそうな顔をしている。
「大丈夫、寮には日本人の女の子もいるし、しっかり勉強してくるから!」
「気をつけてね」
お母さんが心配顔で手を振った。あたしはうなずいて前を向く。
クラスの友達は前日にうちに来てお別れパーティを開いてくれた。でも、今はどこにいてもLINEでつながれるし、そんなに寂しい気はしない。そうだよ、いつでも連絡取れるから。
でも、公務員試験の勉強に集中したいから、という奏汰兄とはLINEもできないし、電話だってかけられない。留学期間の一年間、声さえ聞けないのだ。それなのに、奏汰兄はバイバイの一言も言いに来てくれなかった。
大嫌い、大嫌い……。別に奏汰兄に見送ってもらわなくたっていいもん。一人でがんばれるもん。一人で行けるもん……。
なのに、おかしいな。目の前がにじんできて、前がよく見えない。
あたしは立ち止まって、コートの袖で目をごしごしとこすった。
大嫌いなはずなのに、奏汰兄のことを考えたら涙が止まらない……。止まらないよ……!
そのとき、あたしの横に誰かが立った。セキュリティチェックを急ぐ人なのかと思って、あたしは一歩左によけた。それなのに、その人は進まない。どうして、と思ったとき、聞き慣れた声が聞こえてきた。
「手荷物検査、受けないのか?」
ハッとして顔を上げたら、柔らかく微笑む奏汰兄が横に立っていた。
「なんで……?」
奏汰兄がそっと右手を伸ばしてあたしの頬に触れた。びっくりして涙が止まる。
「夢を叶えに行くのに、なんで泣いてんだよ」
「だって」
「愛海は泣き虫だからな。きっと俺が見送りに行かないと泣いてるだろうなと思ったんだ」
「別に……泣いてなんか」
ないもん、と言ったとたん、ひっく、としゃくりあげてしまった。
「愛海、俺は公務員試験がんばるよ。ずっと働きたいと思ってた外務省に入るためにな。だから、愛海もがんばれ。おまえの訳したフランス文学を読めるのを、俺は楽しみにしてるんだからな」
あたしは手を伸ばして、奏汰兄のカーキ色のコートをキュッとつかんだ。
「でも……一年も……」
寂しいもん、と言いかけたとき、奏汰兄が顔を傾け、あたしの頬にチュッとキスをした。びっくりして目を見開いたまま、奏汰兄を見る。奏汰兄が照れたように小さく笑って、人差し指で頬を掻いた。
「唇は予約した」
「え?」
奏汰兄が人差し指を伸ばしてあたしの唇に触れた。長い指先が唇をなぞって離れる。
「一年後、帰国したらもらうから。それまで俺が予約したんだからな。ほかの男にやるなよ」
奏汰兄の瞳に、強い光が宿った。胸がドキンと大きく跳ねる。
「奏汰兄……っ」
胸が熱くなって、また泣いてしまいそうだ。
奏汰兄があたしの頬にもう一度触れた。
「泣くのは俺の前だけにしろ。一年後まで、顔を上げて行け。俺の大好きな笑顔で行け」
奏汰兄があたしの背中を大きく叩いた。その力強さに押されて、一歩足を踏み出す。
「来年、胸を張って会えるように、笑って行け。俺も採用通知と一緒に愛海を待ってるから」
「うん、うん」
あたしは何度もうなずいた。こぼれそうになる涙を、顔を上げて瞬きをして散らす。唇を引き結び、口角を引き上げて、奏汰兄を見た。奏汰兄が大きくうなずく。
「行ってこい」
「うん、行ってきます」
「帰ってきたら、俺を“兄”なしで呼べるように、練習しとけよな」
あたしはコクンとうなずく。奏汰兄が……大好きな奏汰が……大きく手を振ってくれた。
がんばろう。帰ってきたとき、奏汰にふさわしい彼女になれるように、胸を張れるように。
あたしは笑顔でセキュリティチェックに向かった。背中に大好きな人の温かな視線を感じながら……。