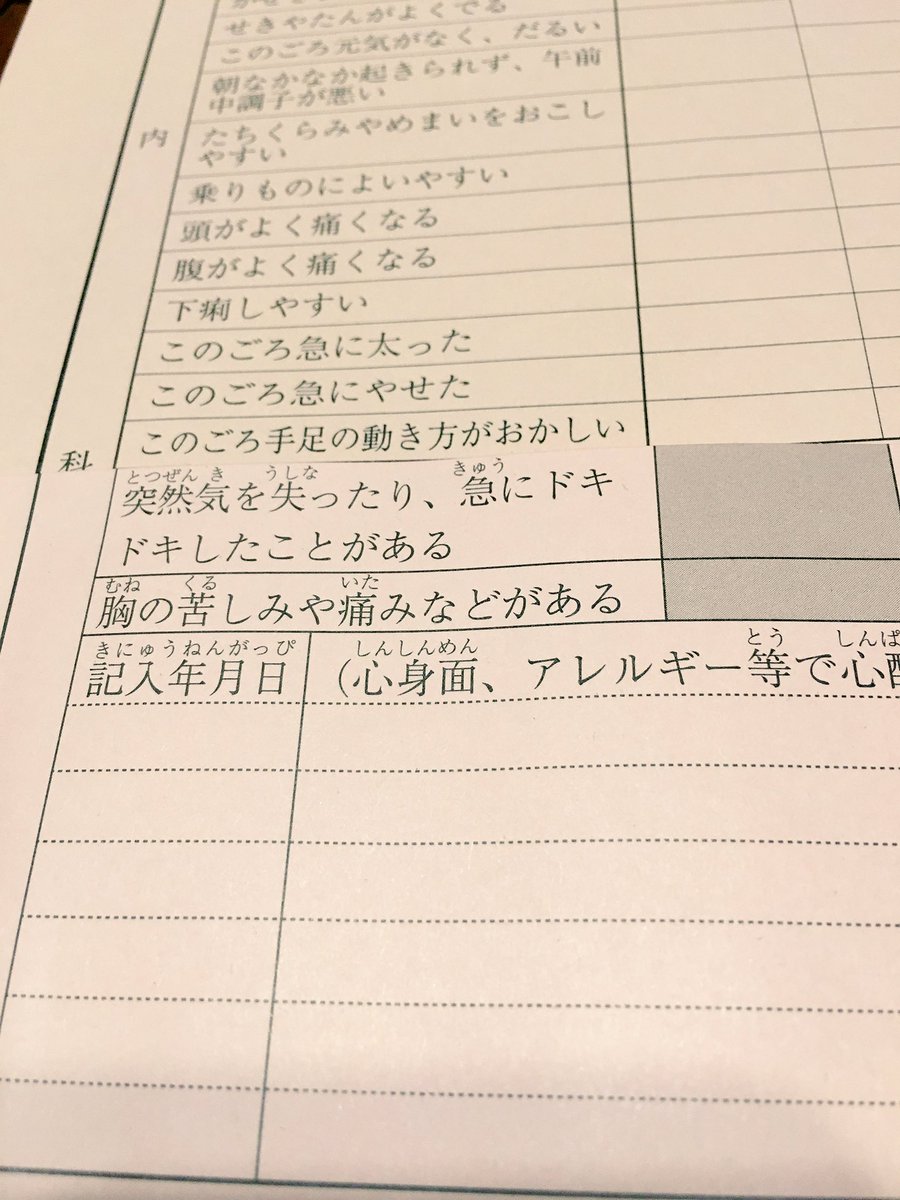*『死の淵を見た男』著者 門田隆将 を複数回に分け紹介します。47回目の紹介
『死の淵を見た男』著者 門田隆将
「その時、もう完全にダメだと思ったんですよ。椅子に座っていられなくてね。椅子をどけて、机の下で、座禅じゃないけど、胡坐をかいて机に背を向けて座ったんです。終わりだっていうか、あとはもう、それこそ神様、仏さまに任せるしかねぇっていうのがあってね」
それは、吉田にとって極限の場面だった。こいつならいっしょに死んでくれる、こいつも死んでくれるだろう、とそれぞれの顔を吉田は思い浮かべていた。「死」という言葉が何度も吉田の口から出た。それは、「日本」を守るために戦う男のぎりぎりの姿だった。(本文より)
吉田昌郎、菅直人、斑目春樹・・・当事者たちが赤裸々に語った「原子力事故」驚愕の真実。
----------------
**『死の淵を見た男』著書の紹介
第15章 一緒に「死ぬ」人間とは
思い浮かべた仲間の顔 P248~
原子炉建屋からおよそ900メートル離れた正門付近で、「毎時500マイクロシーベルト」の放射線量が計測されるのは、午後9時35分ごろのことだった。
一度は、下がり始めたはずの2号機の格納容器圧力が、ふたたび上昇に転じていた。それは、気まぐれな原子炉が、あたかも人間を弄んでいるかのようだった。
午後10時50分、東京本店では、記者たちに2号機格の納容器の圧力が、異常上昇したことで、現災法15条に基づく通報がなされたことが発表された。現場の必死の作業にもかかわらず、圧力は低下せず、厳しい状況が続いていた。
すでに円卓に座る幹部たちの体力は、限界を超えている。午後11時46分、ついに2号機の格納容器圧力は、設計圧力の2倍近い「750キロパスカル」まで上昇し、いつ「何が」起こってもおかしくない状態になっていった。
実は、2号機のベント操作は前日の13日朝からおこなわれ、この段階では、まだ一号機のような高線量の状況ではなかったためにMO弁は手動で開けられ、AO弁も外部からのエア注入によって、いったんは開いていた。しかし、3号機の爆発の影響と思われる電気回路の不調で弁が閉じ、必死の復旧操作にもかかわらず、ふたたび開くことはなかったのである。
一進一退がつづいていた。だが、それは、いよいよ”最期”に向かう一進一退ではないだろうか。口には出さずとも、幹部たちはそのことを悟っていた。
吉田は、格納容器爆発という最悪の事態に備えて、協力企業の人たちに、帰ってもらおうと思った。
「みなさん今やっている作業に直接、かかわりのない方は、いったんお帰りいただいて結構です。本当に今までありがとうございました」
緊対室の廊下に出た吉田は大声でそう叫んだ。
廊下には、多くの人間が身体を横たえている。ほとんどが、タイベックを着たまま泥のように眠っているのである。膝を抱えて座っている物、壁にもたれたままの人間、小さなスペースを見つけて深い眠りに落ちている者・・・それは、”野戦病院”そのものだった。
彼らが、突然の吉田の言葉に驚き、そして、耳を傾けた。
最期が近づいていることを誰もが肝に命じた。免震重要棟から一歩外へ出るということは、放射能汚染の中に「出ていく」ということである。しかし、その危険をお冒してでも、今は、ここから「離れる」ことのほうが重要だったのである。
「本当にありがとうございました」
協力会社の人たちに頭を下げる吉田の姿を見て、復旧に全力を尽くす社員たちもいよいよ最期が近づいていることを知った。
朝方の何時だっただろうか。午後4時、いや5時を過ぎていたかもしれない。
席に戻り、しばらく経った時、吉田のようすがおかしいことに何人もが気づいた。顔から精気が失われ、どこか虚ろな表情をしている。明らかにこれまでと雰囲気が違う。
ふいに吉田が、座っている椅子を後ろに引いて、立ち上がった。それは、”ゆらりと”立ったように見えた。
身長184センチ、体重83キロという吉田が、幽霊のように立ち上がったかと思うと、今度はテーブルを背にして、椅子と机の間にできたスペースにそのまま、あぐらをかいて座り込んだ。
そして、ゆっくりと頭を垂れたのだ。吉田は、目をつむったままあ微動だにしなかった。手は、長い脚が交差している部分を包み込むように置かれている。見ようによっては、それは座禅を組んでいるようにも思えた。
(もう、終わりだ・・・)
(「思い浮かべた仲間の顔」は、次回に続く)
※続き『死の淵を見た男』~吉田昌郎と福島第一原発の500日~は、
2016/4/21(木)22:00に投稿予定です。
 |
![]()










 ANTIFA大阪 @antifa_osk
ANTIFA大阪 @antifa_osk
 ふーみんみん @doka2mom
ふーみんみん @doka2mom 原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx エリック ・C @x__ok
エリック ・C @x__ok
 ふらん @framboise731
ふらん @framboise731 neko-aii @neko_aii
neko-aii @neko_aii

 ア ダ チ @A_september4
ア ダ チ @A_september4
 麒麟地震研究所 @kirinjisinken
麒麟地震研究所 @kirinjisinken
 cmk2wl @cmk2wl
cmk2wl @cmk2wl
 とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel
 サトコ @satokokuni
サトコ @satokokuni
 Massy @tokugawa300
Massy @tokugawa300 忍者=Ninjya @_Ninjya_
忍者=Ninjya @_Ninjya_


 あおてん農園 @aoten49003
あおてん農園 @aoten49003
 ブリーフみそ2 @brief_miso2
ブリーフみそ2 @brief_miso2 名もなき投資家 ? @value_investors
名もなき投資家 ? @value_investors
 so sora @sosorasora3
so sora @sosorasora3
 タニ センゾー @Tanisennzo
タニ センゾー @Tanisennzo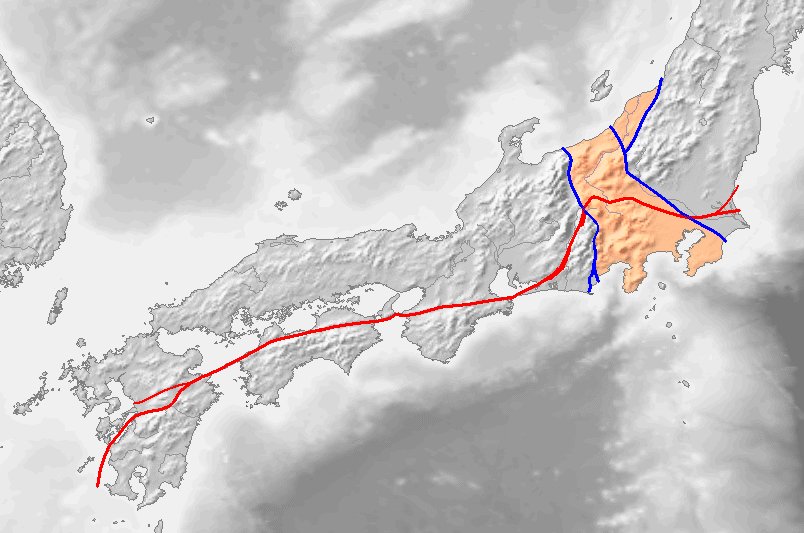
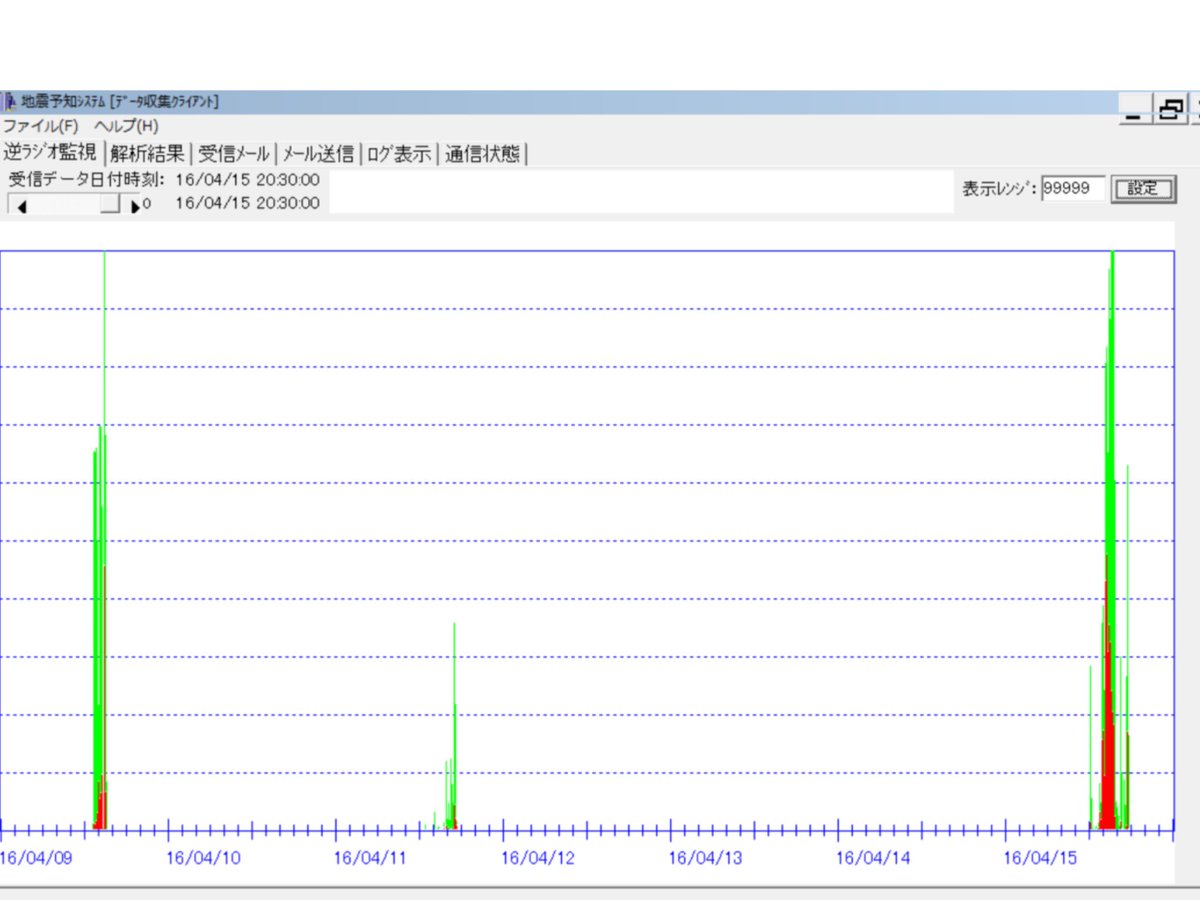
 今一生 @conisshow
今一生 @conisshow ゴン太 @kizusi
ゴン太 @kizusi ヌッキー @kokunan2015
ヌッキー @kokunan2015
 日本未来学生連合@安保法案反対 @kokunan2016
日本未来学生連合@安保法案反対 @kokunan2016

 古川哲嗣 @tetsushi_jp
古川哲嗣 @tetsushi_jp
 Misao Redwolf @MisaoRedwolf
Misao Redwolf @MisaoRedwolf LINE NEWS @news_line_me
LINE NEWS @news_line_me
 まったけ @mattake_iphone
まったけ @mattake_iphone
 世鳥アスカ @setori_aska
世鳥アスカ @setori_aska
 菊池ことは @rose_Gumi
菊池ことは @rose_Gumi


 aya @itoshimasimple
aya @itoshimasimple