
元暦二年(1185)三月二十四日、先陣のことで源義経と梶原景時とが口論となる。
<本文の一部>
同じく十九日、判官(義経)、伊勢の三郎義盛を召して、「阿波の
民部成能が嫡子田内左衛門教能(でんないざえもんのりよし)、河野
を攻めに伊予の国へ越えたんなるが、これにいくさありと聞きて、
今日はさだめて馳せ向かふらん。大勢に入れたててはかなふまじ。
なんぢ行き向かひ、よき様にこしらへて召して参れ」とのたまへ
ば、伊勢の三郎、「さ候はば、御旗を賜はつて向かひ候はん」と申
す。「もっともさるべし」とて、白旗をこそ賜はりけれ。
その勢十六騎にて向かふが、みな白装束なり。兵どもこれを見て、
「三千余騎が大将を、白装束十六騎にて向かひ、生捕にせんことあ
りがたし」とぞ笑ひける。・・・・・・・略・・・
三月二十四日の卯の刻に、長門の国(山口)壇ノ浦、赤間が関にて
源平矢合せとぞ定めける。その日すでに判官と梶原といくさせんと
することあり。
梶原、判官に申しけるは、「今日の先陣をば侍のうちに賜はり候
へ」と申せば、判官、「義経がなからんにこそ」。「まさなや。君
は大将軍にてまします」と申せば、「鎌倉殿こそ大将軍よ。義経は
奉行を承ったれば、ただおのおのと同じことぞ」とのたまへば、梶
原先陣を所望しかねて、「天性この殿は侍の主にはなりがたし」と
ぞつぶやきける。判官、「総じてなんぢは烏滸の者ぞ」とのたまへ
ば、「こはいかに、鎌倉殿のはかは主を持ちたてまつらぬものを」
と申す。判官、「にくいやつかな」とて、太刀に手をかけ、立ちあ
がらんとし給へば、梶原も太刀に手をかけ、身づくろひするところ
に、三浦の介、土肥の次郎むずと中にへだたりたてまつる。
三浦の介、判官に申しけるは、「大事を御目の前にあてさせ給ふ
人の、か様に候はば、敵に力をそへさせ給ひなんず。なかんずく、
鎌倉殿の聞かせ給はんところも、穏便ならず」と申せば、判官しず
まり給ふうへは、梶原すすむにおよばず。
これより梶原、判官をにくみはじめて、つひに讒言してうしなひ
けるとぞ聞こえける。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<あらすじ>
(1)元暦二年(1185)二月十九日、義経は、伊勢三郎義盛に命じて、
阿波の民部成能(しげよし)の嫡男で、田内左衛門教能(のりよし)
を調略させる。
義盛は白装束姿の僅か十六騎で向かい、三千余騎を率いる
田内左衛門教能の一行と行き会い、「貴方の叔父・桜間の介殿
は、鎌倉(頼朝)殿の御弟・九郎判官義経殿に討たれ、昨日は屋島
の平家内裏や御所の全てを焼き払い、中でも新中納言・知盛殿や
能登守・教盛殿は立派に戦って自害なされた旨、そして大臣殿父
子(宗盛、清宗)も生け捕ったこと。貴方の父・民部成能殿も降参し
て、この義盛が身柄を預かっている・・・等など、あること無いことを
出まかせに言い、遂には田内左衛門もかねての噂どおりかと思い
込み、降伏してしまうのであった。
(2) 長らく平家側に従っていた熊野権現の別当・堪増は、平家の運
が尽きるとみて心変わりし、伊予(愛媛)の河野水軍などと合流して
源氏の側に付くことを決心した。
平家は田内左衛門教能が生け捕られたと聞き、讃岐(香川)を出て
船に乗り合わせて、いづこともなく去って行ったと言う。
(3) 二月二十二日、梶原景時ら二百余艘の船がやっと屋島の磯に着
き、義経の配下の兵に冷やかされる。
(4) 三月二十四日早朝に、”壇ノ浦・赤間が関”が源平の矢合わせと定
まるが・・・・・・・
その日の内に義経と梶原の口論から、今にも同士討ちするのでは
ないかという事件が起こる。
梶原が義経に、「今日の先陣を侍の私達に賜りたい」と云うと、義経
は、「戦の奉行を仰せつかっただけ」で同じ立場だと譲らず、口論とな
り太刀に手をかけ身構え、”あわや”というところまでいき、三浦義澄や
土肥実平が中に割って入り止めたと云う。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



















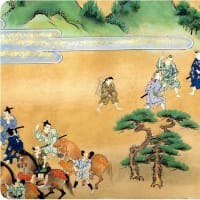
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます