
天台座主・明雲大僧正が流罪に処せられる
<本文の一部>
治承元年(1177)五月五日、天台座主明雲大僧正、公請(くじょう)を停止せられけるうへ、蔵人をつかはして、如意輪の御本尊を召しかへし、護持僧を改易せらる。そのうへ庁使をつけて、今度神輿(しんよ)を内裏へ振りたてまつる衆徒の張本を召されける。「加賀の国に座主の御坊領あり。師高(西光法師の子)これを停廃のあひだ、門徒の大衆寄りて訴訟をいたす。すでに朝家の御大事におよぶ」よし、西光法師(藤原師光)が無実の讒訴によって「ことに重科に処せらるべき」よし聞こえけり。
明雲は法皇の御気色あしかりければ、印鎰(いんやく)をかへしたてまつりて、座主を辞し申さる。おなじき十一日、鳥羽の院の七の宮、覚快法親王を天台座主になしたてまつらせ給ふ。これは青蓮院の大僧正行玄の御弟子なり・・・・・
僧を罪するならひとて、度縁(どえん)を召しかへして還俗(げんぞく)せさせたてまつり、「大納言の大夫藤井の松枝」といふ俗名をこそつけられけれ。
この明雲と申すは、村上の天皇第七の皇子、具平親王より六代の御末、久我の大納言顕通の卿の御子なり・・・・・・
おなじき二十二日、「配所伊豆の国」と定めらる。人々様々(ようよう)に申されけれども、西光法師父子が讒奏(ざんそう)によて、か様におこなはれけるなり・・・・・・
祇園の別当澄憲法印(保元の乱で斬首された入道信西の子)、そのときはいまだ権大僧都にておはしけるが、あまりに名残を惜しみたてまつりて、泣く泣く粟津まで送りまゐらせて、そこよりいとま申してかへられけり。
(注)カッコ内は本文ではなく、私の注釈記入です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(藤原六条流) 顕季-○-家成---隆季-隆房
-成親-成経
-師光(西光)-師高
-師経
「治承元年五月五日」=安元は八月の改元であり、五月はまだ"安元三年"である。
「公 請」=宮中の恒例、臨時の法会に召されること。
「俗 名」=俗名をつけるのは、僧籍剥奪の一環である。
「護持僧」=国家、天皇を守護するために祈祷する。
治承元年(1177)、加賀守・藤原師高、師経の兄弟が、延暦寺末寺の寺領をめぐって争いとなり、堂宇を焼いてしまう。
延暦寺はこの処罰を要求するため内裏に強訴するが、後白河上皇は、平重盛に命じて撃退させる、その騒乱の中で神輿に矢を放ったことで、京中は騒然となる。
やむを得ず、師高を流罪、重盛家来の数人を投獄することになる。
このことで怒った師高、師経兄弟の父で上皇の側近であった西光法師は、「衆徒をそゝのかしたのは座主の明雲である」と訴え、結局、明雲は座主解任、所領没収、伊豆流罪となり、天台座主流罪という前代未聞のできごとに発展してしまったのである。
<本文の一部>
治承元年(1177)五月五日、天台座主明雲大僧正、公請(くじょう)を停止せられけるうへ、蔵人をつかはして、如意輪の御本尊を召しかへし、護持僧を改易せらる。そのうへ庁使をつけて、今度神輿(しんよ)を内裏へ振りたてまつる衆徒の張本を召されける。「加賀の国に座主の御坊領あり。師高(西光法師の子)これを停廃のあひだ、門徒の大衆寄りて訴訟をいたす。すでに朝家の御大事におよぶ」よし、西光法師(藤原師光)が無実の讒訴によって「ことに重科に処せらるべき」よし聞こえけり。
明雲は法皇の御気色あしかりければ、印鎰(いんやく)をかへしたてまつりて、座主を辞し申さる。おなじき十一日、鳥羽の院の七の宮、覚快法親王を天台座主になしたてまつらせ給ふ。これは青蓮院の大僧正行玄の御弟子なり・・・・・
僧を罪するならひとて、度縁(どえん)を召しかへして還俗(げんぞく)せさせたてまつり、「大納言の大夫藤井の松枝」といふ俗名をこそつけられけれ。
この明雲と申すは、村上の天皇第七の皇子、具平親王より六代の御末、久我の大納言顕通の卿の御子なり・・・・・・
おなじき二十二日、「配所伊豆の国」と定めらる。人々様々(ようよう)に申されけれども、西光法師父子が讒奏(ざんそう)によて、か様におこなはれけるなり・・・・・・
祇園の別当澄憲法印(保元の乱で斬首された入道信西の子)、そのときはいまだ権大僧都にておはしけるが、あまりに名残を惜しみたてまつりて、泣く泣く粟津まで送りまゐらせて、そこよりいとま申してかへられけり。
(注)カッコ内は本文ではなく、私の注釈記入です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(藤原六条流) 顕季-○-家成---隆季-隆房
-成親-成経
-師光(西光)-師高
-師経
「治承元年五月五日」=安元は八月の改元であり、五月はまだ"安元三年"である。
「公 請」=宮中の恒例、臨時の法会に召されること。
「俗 名」=俗名をつけるのは、僧籍剥奪の一環である。
「護持僧」=国家、天皇を守護するために祈祷する。
治承元年(1177)、加賀守・藤原師高、師経の兄弟が、延暦寺末寺の寺領をめぐって争いとなり、堂宇を焼いてしまう。
延暦寺はこの処罰を要求するため内裏に強訴するが、後白河上皇は、平重盛に命じて撃退させる、その騒乱の中で神輿に矢を放ったことで、京中は騒然となる。
やむを得ず、師高を流罪、重盛家来の数人を投獄することになる。
このことで怒った師高、師経兄弟の父で上皇の側近であった西光法師は、「衆徒をそゝのかしたのは座主の明雲である」と訴え、結局、明雲は座主解任、所領没収、伊豆流罪となり、天台座主流罪という前代未聞のできごとに発展してしまったのである。



















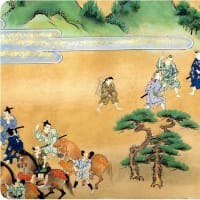
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます