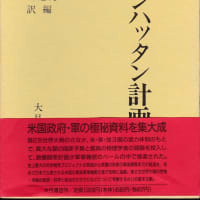▲ 藤田日出男 『あの航空機事故はこうして起きた』 上図は17頁掲載のフライトレコーダーによる日航123便の高度変化、およびボイスレコーダーの記録
藤田日出男 『あの航空機事故はこうして起きた』2005年 新潮社 その3
その3では
減圧が人間に与える影響
事故調査委員会報告のように、日航123便の機内に急激な減圧があった場合、人体にどのような影響があるのか、また機内はどういう状態におかれるのだろうか。
藤田によれば、
「人間の肺にある空気もふくらみ口から吐き出される。」
「耳の中の空気も膨張し、耳に詰まった感じを与える。鼓膜にダメージを与え、耳が聞こえなくなることも珍しくない。
「気体は熱を加えエネルギーを与えると、膨張する。逆に熱を与えないで、機械的に膨張させると、温度が低下する。「これを「断熱膨張」と呼んでいる。」
「飛行機の胴体に穴開いて発生する減圧は、「熱の加えられない」断熱膨張である。そのため必ず気温は低下する。事故調査委員会の計算では65度気温が低下したはずだと試算されている。」
「お盆のさなか、誰もが夏服を着ている時季に、数秒間で65度も気温が下がり、氷点下40度まで室温は低下したと報告書には書かれている。このような温度低下は急減圧では必ず起こる現象であるが、生存者は誰も寒いと感じていなかったのである。」
「事故調査委員会が想定したような急減圧が発生すれば、、それに伴って「大きな騒音」「突風」「気温の低下」は物理的に必ず発生する。くり返すが、4人の生存者たちは、誰一人、そのような証言はしていない。」
「生存者の一人、落合さんは、当時現役の客室乗務員であり、緊急時の訓練も受けていた。」
「彼女はジャーナリズムの取材に対し、客室内に「空気の流れ」がなかったこと、「空気の流れる騒音」もなかったことを明らかにしている。また事故調査委員会は、気温の低下という肝心な点については質問さえ行っていない。」
「私(藤田)が直接、落合さんに訊いたところでは、「バーンの直後には別に気にならなかった、墜落してから空気がつめたく感じた」と答えてくれた。」
「重要なことは、事故調査委員会の筋書きでは、毎分30万フィートと「いう急減圧がなければ、垂直尾翼は壊れないと言う点にある。穏やかな減圧では、この筋書きは崩壊する。
「なんとしても毎分30万フィート程度の急減圧と、5秒間で外気と等しい圧力になっていなければこの筋書きは成り立たない。」 藤田日出男 『あの航空機事故はこうして起きた』2005年 新潮社 (31~34頁)
高度7300メートルでも苦痛なし?
「事故調査委員会は「防衛庁での実験の結果から、毎分約30万フィートとそれに続く18分間の2万フィート以上の、気圧の状態は、人間に直ちに嫌悪感や苦痛を与えない」と報告書に記載している。」
しかし、藤田によれば
「これは、世界中の航空関係者の常識をくつがえす全く新しい見解といえるものだ。」 (要するに事故原因を急減圧にするため、世界の航空常識に異を唱えた詭弁 ブログ主 注)
「たとえば、我が国の防衛庁の教科書では、2万フィート以上の気圧の状態は危険域として扱っており、事実「意識喪失、ショックなど生命に危険が生じる」との注意書きが見られる。」
「ところがこの実験を行った防衛庁の医官は、テレビ局の取材に対して、「報告書のとおりです」と答え、防衛庁の教科書が間違っているかのような回答をしている。だが、その教科書は、その後もちろん改訂などされていない。」
藤田日出男 『あの航空機事故はこうして起きた』2005年 新潮社 (35頁)
以上でおわかりのように、圧力隔壁の破壊 ・ 急減圧 →垂直尾翼の破壊というシナリオは不可能であることがわかる。
すくなくても、事故調査委員会の「報告書」は、紙屑同然のものとわかる。
もちろん、事故調査委員会の報告書が、紙屑同然のものあっても、垂直尾翼の大きな部分が航行中に破壊されたことは間違いがない。
ではこの垂直尾翼の破壊はなぜ起きたのか。
ミサイルが衝突?
「垂直尾翼を破壊したエネルギーは何だったのか。ものを壊すには、外部からの力によるものと、構造的な欠陥や材料の欠如、あるいはそのものの自体の振動による破壊などが考えられる。」
藤田は、事故調査研究にも詳しい元パイロットであるから、いきなり、ミサイルが衝突?という説はとらない。
藤田は
「フラッター現象」の可能性
を指摘する。
「フラッター現象」とは方向舵が、風の強い日に旗や、のぼりなどがパタパタとはためく状態とおなじようになる現象で、過去にはこのために墜落した飛行機が少なくない。翼が破壊される原因としては、かなりの件数を占めていたものである」
「最近では設計段階でのテストなどにより発生は少なくなった。」
「相模湾からの破片回収要求の声を無視しておきながら、事故調は「回収された破片が少ないので尾翼の破壊過程は明らかにできなかった」などといってとぼけている。」 藤田日出男 『あの航空機事故はこうして起きた』2005年 新潮社 (39~44頁)
藤田日出男 『あの航空機事故はこうして起きた』2005年 新潮社
は今から10年前の本なのであるが、今メディアの誰が、藤田の指摘を踏まえて、日航機123便の事故を語っているであろうか。真相の真相を語る熱さを、すでに20年前の研究者の指摘から出発して、論を進めているだろうか?
未だに、日航機123便の垂直尾翼の大きな破片は相模湾の海深200メートルの浅海に回収されずに眠っているのである。回収されても、秘匿されてしまったのではないか。あるいは、御巣鷹山で、発見・回収された破片にも秘匿されたものがあったのではないか。という疑いが残る。
防衛庁が発表した、日航123便の墜落現場の発表が、何と4回も誤った位置を発表し、遭難者救出作業を異常に遅延させたのはなぜなのだろうか。
米田憲司の『御巣鷹の謎を追う』や、藤田日出男のこの本を読むと、事故調査委員会の構成メンバーに、自衛隊の医療関係者、ボイス・レコーダー解析にも、自衛隊所属の人物が参加していることがわかる。
これは、「鶏小屋の門番や入り口の鍵を狸や狐に任せる」のとどう違うのか?
国策会社でもあった日航、運輸省(現国土交通省)、ボーイング社、航空産業安全管理体制、自衛隊、国防費問題、日米安全保障などが絡んだ、政治・経済の根幹にかかわる・軍・産・官複合体を露わに見せた出来事であった。この事件は、たまたま、航空機墜落事故という形をとってはいるが、出来事の氷山の一角なのだなということを、まざまざと国民に知らせたのだ。
つづく