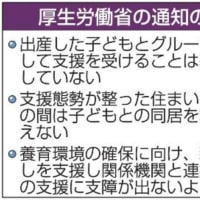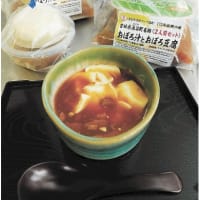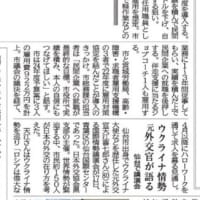重症児向け施設
変化見逃さず命を守る
放課後等デイサービス事業所には、重症心身障害児対象の施設もある。仙台市に7カ所あるうち、NPO法人「あいの実」は泉区で「ラズベリー」と「クランベリー」の2カ所を運営、計28人が利用登録する。
注意深くケア
子どもたちは学校から事業所に来ると、一人ずつ入浴サービスを受ける。両事業所の特色の一つだ。「気持ちいいね」。スタッフ2人に体を抱えられ全身を洗ってもらう。
昨年12月上旬の平日の午後4時すぎ、ラズベリーでは入浴を終えた3人が、姿勢を保つ椅子に座り、スタッフとゴム風船に小麦粉を詰めて感触を楽しむスクイーズ作りを始めた。
「大ちゃんは何色がいいかな」。スタッフは仙台市鶴谷特別支援学校小学部4年の畑中大渉君に声を掛け、表情を見ながらオレンジ色の風船を選んだ。小麦粉を中に入れて「キューキューしてみようね」と大ちゃんの手に触れさせた。
常にスタッフが注意深く寄り添う。スクイーズ作りの最中、1人がたんがからんで苦しくなると、スタッフが急いで吸引した。
児童発達支援管理責任者 (看護師)の岩元優子さんは「命を守るため、目の動きなどちょっとした変化も見逃さずにチェックする必要がある」と話す。
NPO法人「環」の事業所 「ココア(心愛)」は、重症心身障害児向けの施設がなかった仙台市南部の太白区中田に昨年7月に開所した。利用登録者は11人。
子どもたちの過ごし方はそれぞれだ。体調の悪い子は和室の布団で横になり、スタッフの医師と看護師から付きっきりでケアを受ける。車いすに乗り酸素ボンベを着けた子は、おなかに開けた穴からチューブでおやつの栄養を取り、スタッフと遊ぶ。
児童発達支援管理責任者(保育士)の小石川真紀子さんは「障害はさまざまで、必要なケアも気持ちの表し方も違う。特徴を理解して対応しないと信頼関係は築けない」と話す。
事業所少なく
重症心身障害児は抵抗力が弱く、特に冬場は体調を崩して休む子が多い。長期入院もよくある。「国の配置基準に従い、利用者がいなくても最低4人の職員を確保する必要がある。人件費がかかる」と小石川さん。「例えば市が看護師ら福祉関係の人材をプールして派遣するなど、行政のバックアップがもっとほしい」と訴える。
「働きたい」「兄弟の行事に参加したい」という保護者の要望に応え、土曜や祝日も預かるが、運営は厳しい。環は昨年末に訪問介護、未就学児対象の発達支援事業を新たに始め、運営継続へ努力を重ねる。
重い障害を抱えて生きていく子どもの支援体制の整備はなかなか進まない。放課後等デイサービスでも重症心身障害児向けの事業所は少なく、宮城県には仙台市を除くと4ヵ所しかない。県内の重症心身障害児・者は約2000人と推計されており、受け入れ枠が極端に少ないのが現状だ。
宮城県障害福祉課の担当者は「ケア自体の難しさと、人材確保がネックとなり事業所がなかなか増えない。開設への働き掛けや環境整備を推進したい」と課題を挙げる。
<メモ>
重症心鏝堡見対象の施設は、国の報酬単価により定員5人とする高業所が多い。仙台市によると、学齢期の重症心身障害児は2017年5月時点で、たんの吸引など医療的ケアが必要な子が69人、必要ない子が96人いる。国は、各自治体が18年度策定する障害児福祉計画に、20年度までに1ヵ所以上重症心身障害児対象の施設を整備することを盛り込むよう求めている。
変化見逃さず命を守る
放課後等デイサービス事業所には、重症心身障害児対象の施設もある。仙台市に7カ所あるうち、NPO法人「あいの実」は泉区で「ラズベリー」と「クランベリー」の2カ所を運営、計28人が利用登録する。
注意深くケア
子どもたちは学校から事業所に来ると、一人ずつ入浴サービスを受ける。両事業所の特色の一つだ。「気持ちいいね」。スタッフ2人に体を抱えられ全身を洗ってもらう。
昨年12月上旬の平日の午後4時すぎ、ラズベリーでは入浴を終えた3人が、姿勢を保つ椅子に座り、スタッフとゴム風船に小麦粉を詰めて感触を楽しむスクイーズ作りを始めた。
「大ちゃんは何色がいいかな」。スタッフは仙台市鶴谷特別支援学校小学部4年の畑中大渉君に声を掛け、表情を見ながらオレンジ色の風船を選んだ。小麦粉を中に入れて「キューキューしてみようね」と大ちゃんの手に触れさせた。
常にスタッフが注意深く寄り添う。スクイーズ作りの最中、1人がたんがからんで苦しくなると、スタッフが急いで吸引した。
児童発達支援管理責任者 (看護師)の岩元優子さんは「命を守るため、目の動きなどちょっとした変化も見逃さずにチェックする必要がある」と話す。
NPO法人「環」の事業所 「ココア(心愛)」は、重症心身障害児向けの施設がなかった仙台市南部の太白区中田に昨年7月に開所した。利用登録者は11人。
子どもたちの過ごし方はそれぞれだ。体調の悪い子は和室の布団で横になり、スタッフの医師と看護師から付きっきりでケアを受ける。車いすに乗り酸素ボンベを着けた子は、おなかに開けた穴からチューブでおやつの栄養を取り、スタッフと遊ぶ。
児童発達支援管理責任者(保育士)の小石川真紀子さんは「障害はさまざまで、必要なケアも気持ちの表し方も違う。特徴を理解して対応しないと信頼関係は築けない」と話す。
事業所少なく
重症心身障害児は抵抗力が弱く、特に冬場は体調を崩して休む子が多い。長期入院もよくある。「国の配置基準に従い、利用者がいなくても最低4人の職員を確保する必要がある。人件費がかかる」と小石川さん。「例えば市が看護師ら福祉関係の人材をプールして派遣するなど、行政のバックアップがもっとほしい」と訴える。
「働きたい」「兄弟の行事に参加したい」という保護者の要望に応え、土曜や祝日も預かるが、運営は厳しい。環は昨年末に訪問介護、未就学児対象の発達支援事業を新たに始め、運営継続へ努力を重ねる。
重い障害を抱えて生きていく子どもの支援体制の整備はなかなか進まない。放課後等デイサービスでも重症心身障害児向けの事業所は少なく、宮城県には仙台市を除くと4ヵ所しかない。県内の重症心身障害児・者は約2000人と推計されており、受け入れ枠が極端に少ないのが現状だ。
宮城県障害福祉課の担当者は「ケア自体の難しさと、人材確保がネックとなり事業所がなかなか増えない。開設への働き掛けや環境整備を推進したい」と課題を挙げる。
<メモ>
重症心鏝堡見対象の施設は、国の報酬単価により定員5人とする高業所が多い。仙台市によると、学齢期の重症心身障害児は2017年5月時点で、たんの吸引など医療的ケアが必要な子が69人、必要ない子が96人いる。国は、各自治体が18年度策定する障害児福祉計画に、20年度までに1ヵ所以上重症心身障害児対象の施設を整備することを盛り込むよう求めている。