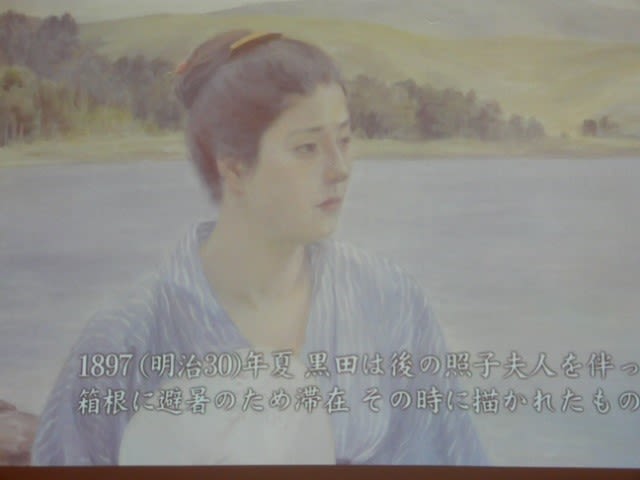天然記念物に指定されている来宮神社の「大楠」
熱海市の来宮神社に国の天然記念物に指定されている「大楠の大樹」があります。
祝嶺の型研究会奉納演ときに、来宮神社の本殿裏手にある大楠の大樹を見てきました。樹齢2000年と銘打ってあるだけにその巨大さにはびっくりした。
(来宮神社HPから)
二千年の樹齢にあやかり、古くからこの大楠を一廻りすると一年寿命が延びると伝えられています。また、願い事のある人は思うことを誰にも云わず一廻りすると願い事がまとまるとも伝えられています。
キノミヤ信仰
古代の日本民族は、大きな木、岩、滝など巨大な自然創造物に神々が宿っていると信じ、其の自然創造物の前で祭祀を行い、感謝し祈りを捧げる神籬磐境信仰を持っておりました。
時が流れ建物の文化が進み、それらを中心に社殿、鳥居が建立され神社が形成されたといえます。
熱海鎮座の来宮神社は江戸末期まで『木宮明神』と称し、現在の『来宮』ではなく、『木宮』の字で古文書等記されております。
また伊豆地方に『キノミヤ神社』という社は十数カ所あり、各社とも必ず千年以上の御神木があることから、『木』に宿る神々をお祀りする神社として崇敬を集め、古来生活文化に欠くことのできない木に感謝する信仰を有しておりました。
今から百三十年前の嘉永年間に熱海村に大網事件という全村挙げての漁業権をめぐる事件が勃発し、その訴訟費等捻出のため、境内に聳え立っておりました七本の楠のうち五本は伐られてしまいました。
古記によると、残されているこの大楠をも伐ろうとして樵夫が大鋸を幹に当てようとしたところ怱然として白髪の老人が現れ、両手を広てこれを遮る様な姿になると大鋸は手元から真っ二つに折れ、同時に白髪の老人の姿は消えてしまったそうです。
これは神のお告げであるとして村人等は大楠を伐ることを中止致しました。この木が即ち現在ある御神木であります。