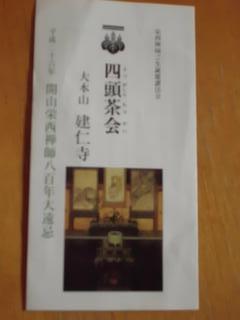正午の茶事に従い、

お客様8名、お水谷4名で皐月の茶事を行いました。

花菖蒲、色紙:鮎を釣る 狭に夕立の 名残雲 【北嶺(ソウガワ, ホクレイ)】

待合い:床 ”柳にツバメ ”三浦竹泉

腰掛待合い

本席;朝鮮風炉(麻生吉造)、釜:あられ(菊地政光)、皆具:荒磯(萬古焼、加賀瑞山)



初座 床:渓雲(東大寺 清水公照)、香合:堆黒(渡辺明泉)


後座 未央柳 (びょうやなぎ)とヤマアジサイ

濃茶点前;茶杓:好日(藤本寛道)、主茶碗:黒楽 曳き舟(吉村楽入)
 >
>
薄茶点前;茶杓:貝舟(時代)、茶碗:あやめ(白井半七)


水谷にて(*水屋と通常書くと思いますが、先日書の稽古にて、屋を谷にして先生は用いているとのこと。調べてもでてきませんが、使わせていただきました。)
お客様には喜んでいただくことができました。
お水谷の方々および料理方、すべて皆様のおかげです。
これからもお稽古の一環として、気軽に行いたいと思います。

お客様8名、お水谷4名で皐月の茶事を行いました。

花菖蒲、色紙:鮎を釣る 狭に夕立の 名残雲 【北嶺(ソウガワ, ホクレイ)】

待合い:床 ”柳にツバメ ”三浦竹泉

腰掛待合い

本席;朝鮮風炉(麻生吉造)、釜:あられ(菊地政光)、皆具:荒磯(萬古焼、加賀瑞山)



初座 床:渓雲(東大寺 清水公照)、香合:堆黒(渡辺明泉)


後座 未央柳 (びょうやなぎ)とヤマアジサイ

濃茶点前;茶杓:好日(藤本寛道)、主茶碗:黒楽 曳き舟(吉村楽入)
 >
>薄茶点前;茶杓:貝舟(時代)、茶碗:あやめ(白井半七)


水谷にて(*水屋と通常書くと思いますが、先日書の稽古にて、屋を谷にして先生は用いているとのこと。調べてもでてきませんが、使わせていただきました。)
お客様には喜んでいただくことができました。
お水谷の方々および料理方、すべて皆様のおかげです。
これからもお稽古の一環として、気軽に行いたいと思います。