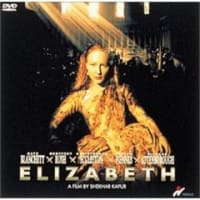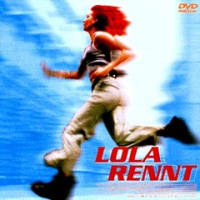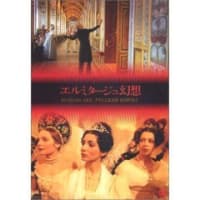いままでのところ、今年一番気に入った小説がこれだ。
久しぶりにbk1にも書評投稿した。
-----------bk1書評--------------
映画「白いカラス」は映画としては失敗作だと思いながらも、その豊かなテーマに心惹かれ、原作はさぞや素晴らしいに違いないと本書を読み始めたのだが、案の定、この豊穣な原作から映画はほんのひと絞りの果汁を汲み出しただけであることがわかった。それでもあれだけ心に残る作品ができたのだから、いかに原作が優れているかの証左と言えよう。
小説の中心人物コールマン・シルク教授のイメージは映画とずいぶん違う。アンソニー・ホプキンスはミスキャストだ。ショーン・コネリーに演じさせるべきだったのだ。シルク教授はホプキンスよりずっと見た目が若くて精悍でスマートな老人なのだ。だからこそ34歳のファーニア(ニコール・キッドマン)が恋するのも納得なのに。
さて、物語の舞台は大学、しかもその知的世界の裏側を描いており、たいそう興味深い。この小説にはいくつもの挿話が複雑に編みこまれている。
白人として生きてきた黒人が人種差別者のレッテルを貼られるという皮肉と欺瞞。
継父からの性的暴力と夫の暴力、わが子の死、を経て今は老人とのセックスに命を吹き込まれる女性の苦難の人生と官能。
ベトナム帰還兵が戦後数十年を経てなおジャングルの悪夢に憑りつかれている悲劇と壮絶な暴力。
文字を覚えられない生徒に四苦八苦する女性教師の絶望。
名門家系の圧迫から逃げるためにフランスからアメリカへやってきた若き女性文学者の野心と失望。
以上すべての物語を、作家は神の目をもって一人称で語る。「私」ネイサン・ザッカーマンという作家は小説の語り部であるが、主役は作家の友人コールマン・シルク(元)教授だ。ネイサンは一人称で物語を紡ぎつつ、コールマン周辺の人物の内面に大胆に迫り、彼ら・彼女らの心理を詳らかに開陳する。まるで人体を腑分けするように、ネイサンの魔術によって皮をめくられた人々の苦笑と嘆息と狡知と驚愕と恐怖がありありと読者の脳裏に浮かぶ。
文体は淡々として平明かつ知的。しかもいくつもの物語を重層的な時制の下に配置し、時間を縦横に往還することによって小説世界にふくらみを持たせた。コールマンの「秘密」も早々と明らかにされるが、この作品には、ネタバレしようが動じないだけの巧みな構成力とテーマの深さ、文体の品位で読者を最後まで惹きつけて放さないだけの魅力がある。
重要な登場人物たちすべての生き様と苦悩の背景は一つずつが説得力ある筆致で描かれているため、わたしはどの人物にも並々ならぬ関心や同情を感じてしまう。
ベトナム帰還兵レスター・ファーリーのおぞましい暴力に戦慄しながらも彼をこのような人間にした悲劇に同情を禁じえないし、コールマンを陥れるフランス人教授デルフィーヌ・ルーにさえ、憐れさを感じる。名家である母の一族の圧力に抗しながらの血の呪縛から解き放たれない頭脳優秀で美しいデルフィーヌ。映画ではこのデルフィーヌのエピソードを大胆にカットしてしまったのが惜しまれる。
さらに、映画ではコールマンに子どもがいないことになっていたが、これも原作と異なる。原作ではコールマンには4人の子どもたちがいて、その存在がコールマンの精神生活に大きな影響を及ぼすのだから、これはぜひカットせずにおいてほしかった。
差別とアイデンティティの病理や差別撤廃運動の弊害、大学と学問の荒廃(むしろ、大学教員の高慢と怠惰というべきか)といった現代アメリカ社会の問題(日本社会の問題でもある)を凝縮させたお手並みに拍手。
※映画「白いカラス」レビューはHP「吟遊旅人」のシネマ日記に書いてます。観てから読むか読んでから観るか悩んでおられるかた、原作は観てから読んでください。先に読んでしまうと物足りなさばかり目立つでしょう。
---------------------------------------
以下は、bk1に書かなかったこと。
コールマンが学生たちに読ませたギリシャ古典戯曲の内容が女性差別的だと、ある女子学生が不満を女性教授にもちかける場面で、わたしは自分の学生時代のことを思い出した。英書講読のときにある教官が使ったテキストが女性差別的な内容だったので、わたしはその英語の授業時間中ずっと不愉快だったのだ。よっぽど教官に抗議してやろうかと思ったが面倒なのでやめた。
本書ではこの場面、コールマンはその女子学生のことを、「ろくに勉強もせず古典劇など何も理解していないのに文句だけは一人前だ」と取り合わない。
今思えば、もしあのときに教師に抗議していたら、わたしもそのようにしか見られなかったんだろうなと思ってちょっと苦笑。
タイトルの”The human stain "を映画字幕では「傷」と訳していたが、原作では「穢れ」と訳している。前後の文脈からすると、「穢れ」と訳するほうが適切だが、映画の場合は確かに「人間の傷」と訳したほうがぴったりくる場面だった。
映画「白いカラス」レビューはここ
<書誌情報>
ヒューマン・ステイン
フィリップ・ロス著 ; 上岡伸雄訳. 集英社, 2004
久しぶりにbk1にも書評投稿した。
-----------bk1書評--------------
映画「白いカラス」は映画としては失敗作だと思いながらも、その豊かなテーマに心惹かれ、原作はさぞや素晴らしいに違いないと本書を読み始めたのだが、案の定、この豊穣な原作から映画はほんのひと絞りの果汁を汲み出しただけであることがわかった。それでもあれだけ心に残る作品ができたのだから、いかに原作が優れているかの証左と言えよう。
小説の中心人物コールマン・シルク教授のイメージは映画とずいぶん違う。アンソニー・ホプキンスはミスキャストだ。ショーン・コネリーに演じさせるべきだったのだ。シルク教授はホプキンスよりずっと見た目が若くて精悍でスマートな老人なのだ。だからこそ34歳のファーニア(ニコール・キッドマン)が恋するのも納得なのに。
さて、物語の舞台は大学、しかもその知的世界の裏側を描いており、たいそう興味深い。この小説にはいくつもの挿話が複雑に編みこまれている。
白人として生きてきた黒人が人種差別者のレッテルを貼られるという皮肉と欺瞞。
継父からの性的暴力と夫の暴力、わが子の死、を経て今は老人とのセックスに命を吹き込まれる女性の苦難の人生と官能。
ベトナム帰還兵が戦後数十年を経てなおジャングルの悪夢に憑りつかれている悲劇と壮絶な暴力。
文字を覚えられない生徒に四苦八苦する女性教師の絶望。
名門家系の圧迫から逃げるためにフランスからアメリカへやってきた若き女性文学者の野心と失望。
以上すべての物語を、作家は神の目をもって一人称で語る。「私」ネイサン・ザッカーマンという作家は小説の語り部であるが、主役は作家の友人コールマン・シルク(元)教授だ。ネイサンは一人称で物語を紡ぎつつ、コールマン周辺の人物の内面に大胆に迫り、彼ら・彼女らの心理を詳らかに開陳する。まるで人体を腑分けするように、ネイサンの魔術によって皮をめくられた人々の苦笑と嘆息と狡知と驚愕と恐怖がありありと読者の脳裏に浮かぶ。
文体は淡々として平明かつ知的。しかもいくつもの物語を重層的な時制の下に配置し、時間を縦横に往還することによって小説世界にふくらみを持たせた。コールマンの「秘密」も早々と明らかにされるが、この作品には、ネタバレしようが動じないだけの巧みな構成力とテーマの深さ、文体の品位で読者を最後まで惹きつけて放さないだけの魅力がある。
重要な登場人物たちすべての生き様と苦悩の背景は一つずつが説得力ある筆致で描かれているため、わたしはどの人物にも並々ならぬ関心や同情を感じてしまう。
ベトナム帰還兵レスター・ファーリーのおぞましい暴力に戦慄しながらも彼をこのような人間にした悲劇に同情を禁じえないし、コールマンを陥れるフランス人教授デルフィーヌ・ルーにさえ、憐れさを感じる。名家である母の一族の圧力に抗しながらの血の呪縛から解き放たれない頭脳優秀で美しいデルフィーヌ。映画ではこのデルフィーヌのエピソードを大胆にカットしてしまったのが惜しまれる。
さらに、映画ではコールマンに子どもがいないことになっていたが、これも原作と異なる。原作ではコールマンには4人の子どもたちがいて、その存在がコールマンの精神生活に大きな影響を及ぼすのだから、これはぜひカットせずにおいてほしかった。
差別とアイデンティティの病理や差別撤廃運動の弊害、大学と学問の荒廃(むしろ、大学教員の高慢と怠惰というべきか)といった現代アメリカ社会の問題(日本社会の問題でもある)を凝縮させたお手並みに拍手。
※映画「白いカラス」レビューはHP「吟遊旅人」のシネマ日記に書いてます。観てから読むか読んでから観るか悩んでおられるかた、原作は観てから読んでください。先に読んでしまうと物足りなさばかり目立つでしょう。
---------------------------------------
以下は、bk1に書かなかったこと。
コールマンが学生たちに読ませたギリシャ古典戯曲の内容が女性差別的だと、ある女子学生が不満を女性教授にもちかける場面で、わたしは自分の学生時代のことを思い出した。英書講読のときにある教官が使ったテキストが女性差別的な内容だったので、わたしはその英語の授業時間中ずっと不愉快だったのだ。よっぽど教官に抗議してやろうかと思ったが面倒なのでやめた。
本書ではこの場面、コールマンはその女子学生のことを、「ろくに勉強もせず古典劇など何も理解していないのに文句だけは一人前だ」と取り合わない。
今思えば、もしあのときに教師に抗議していたら、わたしもそのようにしか見られなかったんだろうなと思ってちょっと苦笑。
タイトルの”The human stain "を映画字幕では「傷」と訳していたが、原作では「穢れ」と訳している。前後の文脈からすると、「穢れ」と訳するほうが適切だが、映画の場合は確かに「人間の傷」と訳したほうがぴったりくる場面だった。
映画「白いカラス」レビューはここ
<書誌情報>
ヒューマン・ステイン
フィリップ・ロス著 ; 上岡伸雄訳. 集英社, 2004