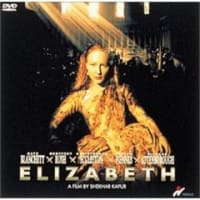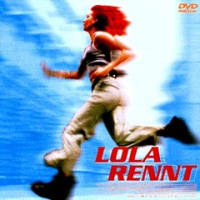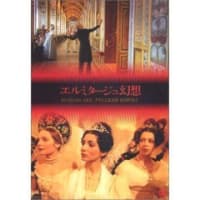Posted by pipihime at 22:07 │Comments(2) │TrackBack(1)
2005年01月20日
「ねじまき鳥」は長い小説だった。ある友人は、「いったいいつになったらおもしろくなるんやろうとずっと我慢して読んでたけど、とうとう我慢できずに途中で放り投げた」と言っていた。さもありなん。確かに、引っ張り引っ張りずぅ~っと読者を引っ張りつづけて、結局最後にオチをつけないのだから、これはまあ、詐欺といえば言える。
編集者・書評者の故ヤスケンさんも『本など読むなバカになる』の中でそういう意味のことを書いている。だけどね、ヤスケンさんの酷評、あたっているところもずいぶんあるんだけど、わたしはちょっと違うなあと思っている。
たとえば、物語の初めのほうで、主人公たちが夫婦喧嘩する場面。主人公「僕」は岡田亨という30歳の失業者。法律事務所の使い走りのような仕事をしていたが、つい最近辞めた。妻の久美子は雑誌の編集者。二人の間に子どもはいない。結婚して6年の彼らは、ささいなことで喧嘩をする。それはおかずの組み合わせが気に入らなかったという妻の不平が発端なのだ。あるいはまたトイレットペーパーの色や柄が気に入らないという。そんなささいな妻の好みを、6年も一緒に暮らした夫が知らないなんておかしい、とヤスケンは批判する。妻の生理周期は熟知しているのに、なんで料理の好みを知らないわけがあろうか、不自然だ、と。
このことを通して作者は、夫婦のディスコミュニケーションなり、冷え切った夫婦生活を暗示しているのでもない。(p19)
そして、オカダ・トオルという主人公のことをヤスケンさんは
「僕」のキャラクターとは世の中に五万といる三十代前後の一種のモラトリアム人間、何かクリエイティヴ(オエッ!)なことが出来るのではと錯覚してはいるが実は何もできず、しかもやりたいことなど皆無、むろん、いわゆる社畜にはなりたくなく、軽蔑すらしている、しかし、どこかに常に欲求不満と将来に対する漠然たる不安はあるといったウルトラ薄馬鹿人間の典型とも言える(p21-22)
と、ボロクソである。
確かにそうなのだ。オカダ・トオルはふわふわととらえどころがなく実在感がなく、生身で生きているという感じのしない人間だ。確かに魅力的な人物とも思えない。けれど、わたしはこの冒頭の部分が一番気に入ったのだ。この二人の「薄馬鹿人間」たちの夫婦喧嘩にこそリアリティがあると感じた。
何十年一緒に暮らしたって、ほんとうのところ、妻や夫のことを理解しているといえるだろうか? むしろますます相手の事を真剣に斟酌しなくなるのではなかろうか。ささいなことで「あなたはわたしを見ていない」と夫をなじるクミコの気持ちがわたしにはよくわかる。
だからこそ、冒頭に置かれたこのささいな夫婦喧嘩の意味は大きいと思う。ところが、問題はこの夫婦のディスコミュニケーションに分け入っていく内容が展開されると期待してもいっこうに話がそちらの方向に進まないことにあるのだ。
なんだかよくわからない登場人物が大勢登場するのだけれど、誰も彼もいったい何のために登場してきたのかさっぱり理解不能だ。謎をたくさんちりばめていくけれど、結局のところ「彼女はいったいなんだったの?」と思うころにはもう彼らは退場している。
ただし、ヤスケンさんの怒りもイライラも確かによくわかるけれど、本作がそれほど一顧だにする必要もないほどの愚作だとは思えない。というのも、「間宮中尉」のサイドストーリーがものすごくおもしろかったからなのだ。間宮中尉というのは、ノモンハン事件以来、ずっと中国東北部で戦争し続けた軍人なのだが、彼の数奇な運命がわたしを惹きつける。
そして、「レーニンはマルクスの言ったことのなかで自分にわかるところだけを都合よく引用し、スターリンはさらにレーニンの言葉のなかから自分にわかるところだけを利用した」という意味のことが描かれているくだりにきて、「名言やんか」と思わず手を打ってしまった。
『ねじまき鳥』は主人公達の現実生活よりも、間宮中尉の回想録のほうがおもしろいから、これだけを戦記ものとして村上春樹は書けばよかったのに。
して、ヤスケンさんのこの本は、前半が『ねじまき鳥クロニクル』をこき下ろす精読批判だが、後半は読書案内になっていて、これがまたけっこうおもしろくて役に立つ。その中で、「一作ごとに腕を上げる」と誉められているのが小川洋子だ。小川洋子については斎藤環も『文学の徴候』で誉めていたし、「とみきち読書日記」でも『ブラフマンの埋葬』が取り上げられているし、去年のベストに『博士の愛した数式』を挙げておられたので、わたしも次に読んでみようと図書館にリクエスト中である。
ほかにも、読まず嫌いだった村上龍を読んでみようと思わせる絶賛ぶりなので、やっぱりヤスケンさんは本好きをそそるのがうまい。
ヤスケンさんは本を見る目があると思うし、すぐれた書評家・編集者なんだと思う。でも、読者は、「愚作」と自分でも思うような小説に惹かれてしまうことだってあるんだということを忘れてはいけない。
<書誌情報>
ねじまき鳥クロニクル / 村上春樹著 ; 第1部 : 泥棒かささぎ編 - 第3部 :
鳥刺し男編. -- 新潮社, 1997. -- (新潮文庫 ; む-5-11~む-5-13)
本など読むな、バカになる / 安原顯著. -- 図書新聞, 1994
2005年01月20日
「ねじまき鳥」は長い小説だった。ある友人は、「いったいいつになったらおもしろくなるんやろうとずっと我慢して読んでたけど、とうとう我慢できずに途中で放り投げた」と言っていた。さもありなん。確かに、引っ張り引っ張りずぅ~っと読者を引っ張りつづけて、結局最後にオチをつけないのだから、これはまあ、詐欺といえば言える。
編集者・書評者の故ヤスケンさんも『本など読むなバカになる』の中でそういう意味のことを書いている。だけどね、ヤスケンさんの酷評、あたっているところもずいぶんあるんだけど、わたしはちょっと違うなあと思っている。
たとえば、物語の初めのほうで、主人公たちが夫婦喧嘩する場面。主人公「僕」は岡田亨という30歳の失業者。法律事務所の使い走りのような仕事をしていたが、つい最近辞めた。妻の久美子は雑誌の編集者。二人の間に子どもはいない。結婚して6年の彼らは、ささいなことで喧嘩をする。それはおかずの組み合わせが気に入らなかったという妻の不平が発端なのだ。あるいはまたトイレットペーパーの色や柄が気に入らないという。そんなささいな妻の好みを、6年も一緒に暮らした夫が知らないなんておかしい、とヤスケンは批判する。妻の生理周期は熟知しているのに、なんで料理の好みを知らないわけがあろうか、不自然だ、と。
このことを通して作者は、夫婦のディスコミュニケーションなり、冷え切った夫婦生活を暗示しているのでもない。(p19)
そして、オカダ・トオルという主人公のことをヤスケンさんは
「僕」のキャラクターとは世の中に五万といる三十代前後の一種のモラトリアム人間、何かクリエイティヴ(オエッ!)なことが出来るのではと錯覚してはいるが実は何もできず、しかもやりたいことなど皆無、むろん、いわゆる社畜にはなりたくなく、軽蔑すらしている、しかし、どこかに常に欲求不満と将来に対する漠然たる不安はあるといったウルトラ薄馬鹿人間の典型とも言える(p21-22)
と、ボロクソである。
確かにそうなのだ。オカダ・トオルはふわふわととらえどころがなく実在感がなく、生身で生きているという感じのしない人間だ。確かに魅力的な人物とも思えない。けれど、わたしはこの冒頭の部分が一番気に入ったのだ。この二人の「薄馬鹿人間」たちの夫婦喧嘩にこそリアリティがあると感じた。
何十年一緒に暮らしたって、ほんとうのところ、妻や夫のことを理解しているといえるだろうか? むしろますます相手の事を真剣に斟酌しなくなるのではなかろうか。ささいなことで「あなたはわたしを見ていない」と夫をなじるクミコの気持ちがわたしにはよくわかる。
だからこそ、冒頭に置かれたこのささいな夫婦喧嘩の意味は大きいと思う。ところが、問題はこの夫婦のディスコミュニケーションに分け入っていく内容が展開されると期待してもいっこうに話がそちらの方向に進まないことにあるのだ。
なんだかよくわからない登場人物が大勢登場するのだけれど、誰も彼もいったい何のために登場してきたのかさっぱり理解不能だ。謎をたくさんちりばめていくけれど、結局のところ「彼女はいったいなんだったの?」と思うころにはもう彼らは退場している。
ただし、ヤスケンさんの怒りもイライラも確かによくわかるけれど、本作がそれほど一顧だにする必要もないほどの愚作だとは思えない。というのも、「間宮中尉」のサイドストーリーがものすごくおもしろかったからなのだ。間宮中尉というのは、ノモンハン事件以来、ずっと中国東北部で戦争し続けた軍人なのだが、彼の数奇な運命がわたしを惹きつける。
そして、「レーニンはマルクスの言ったことのなかで自分にわかるところだけを都合よく引用し、スターリンはさらにレーニンの言葉のなかから自分にわかるところだけを利用した」という意味のことが描かれているくだりにきて、「名言やんか」と思わず手を打ってしまった。
『ねじまき鳥』は主人公達の現実生活よりも、間宮中尉の回想録のほうがおもしろいから、これだけを戦記ものとして村上春樹は書けばよかったのに。
して、ヤスケンさんのこの本は、前半が『ねじまき鳥クロニクル』をこき下ろす精読批判だが、後半は読書案内になっていて、これがまたけっこうおもしろくて役に立つ。その中で、「一作ごとに腕を上げる」と誉められているのが小川洋子だ。小川洋子については斎藤環も『文学の徴候』で誉めていたし、「とみきち読書日記」でも『ブラフマンの埋葬』が取り上げられているし、去年のベストに『博士の愛した数式』を挙げておられたので、わたしも次に読んでみようと図書館にリクエスト中である。
ほかにも、読まず嫌いだった村上龍を読んでみようと思わせる絶賛ぶりなので、やっぱりヤスケンさんは本好きをそそるのがうまい。
ヤスケンさんは本を見る目があると思うし、すぐれた書評家・編集者なんだと思う。でも、読者は、「愚作」と自分でも思うような小説に惹かれてしまうことだってあるんだということを忘れてはいけない。
<書誌情報>
ねじまき鳥クロニクル / 村上春樹著 ; 第1部 : 泥棒かささぎ編 - 第3部 :
鳥刺し男編. -- 新潮社, 1997. -- (新潮文庫 ; む-5-11~む-5-13)
本など読むな、バカになる / 安原顯著. -- 図書新聞, 1994