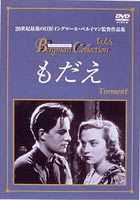わたしって動物もののドキュメンタリー映画が好きなんだとつくづく思う。「WATARIDORI」なんてDVDを買ってしまったしね。「ディープブルー」ももちろん劇場で見たし、これも劇場で見たかったのだけれど、残念ながらDVDで鑑賞。で、やっぱり劇場で見ればよかったと後悔。北極の空撮は迫力満点だし、音楽はフォークロア風だったり幻想的だったりしてなかなかよかったし、けれど淡々としすぎているものだからつい寝てしまう。劇場だと寝ないですんだのじゃなかろうか。地球温暖化の影響で北極の氷も減り、白熊の狩場が狭くなって生存の危機にあるといった話には軽い恐怖心も感じた。これは「アース」にあったシーンと重なる部分ですね、「アース」のほうが後から公開されているけど。「アース」が地球全体を描写の対象としたのに対して、本作はひたすら北極圏の動物たちを追う。
海中の撮影などは寒いし暗くて怖そうなのに、どうやって撮ったのだろう、ひたすら被写体を追いかけていくカメラマンは偉い。とにかくカメラマンに敬意を表して。(レンタルDVD)
----------------
LA PLANETE BLANCHE
フランス/カナダ、2006年、上映時間 83分
監督: ティエリー・ラコベール、ティエリー・ピアンタニーダ、製作: ジャン・ラバディほか、脚本: ティエリー・ピアンタニーダ、ステファン・ミリエール、音楽: ブリュノ・クーレ
ナレーション: ジャン=ルイ・エティエンヌ
海中の撮影などは寒いし暗くて怖そうなのに、どうやって撮ったのだろう、ひたすら被写体を追いかけていくカメラマンは偉い。とにかくカメラマンに敬意を表して。(レンタルDVD)
----------------
LA PLANETE BLANCHE
フランス/カナダ、2006年、上映時間 83分
監督: ティエリー・ラコベール、ティエリー・ピアンタニーダ、製作: ジャン・ラバディほか、脚本: ティエリー・ピアンタニーダ、ステファン・ミリエール、音楽: ブリュノ・クーレ
ナレーション: ジャン=ルイ・エティエンヌ