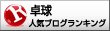3日午前、台湾東部の花蓮県で震度6強の大地震が発生し、今までに9人が死亡し、1000人以上がけがをしたと発表されているが、テレビで現地の映像を見ている限り、大きな建物が傾いたり、倒壊したりするシーンが多く映し出されており、今後、もっと犠牲者が出ることが予想される。日本でも、沖縄の離島で津波が押し寄せる等のニュースも流れていた。マグニチュードは7.7で震源地に近い台湾東部の花蓮の街の様子が紹介されていたが、花蓮は、風光明媚な観光地で、多くの観光客が訪れるので、観光客の犠牲者も心配される。
花蓮には、太魯閣という有名な渓谷があり、国立公園にも指定されており、個人的にも1973年11月に訪れたことがあるが、国立公園の被害状況も心配される。当時、台北から花蓮までバスが走っていたが、過去には時々、バスが崖から転落するという事故も時々発生していたので、バスは避けた記憶がある。自分の場合は、遠東航空(現在運航停止中)を利用して、台北から花蓮に入ったが、遠東航空といえば、1981年に大きな航空事故を起こし、当時作家で有名だった向田邦子さんが犠牲になったことでも有名である。1月1日の能登半島大地震からまだ3ヵ月しか経っていないが、地震はいつ、どこで発生するか分からないし、大地震は必ず起こるものとして備えが必要である。その意味で、地震大国の日本の原子力政策には大きな疑問がある。個人的に台湾は最初に行った外国であり、その後も何回か訪問している。大好きなテレサ・テンの母国でもあり、人一倍親しみを感じている。台湾自体、大変親日な国なので、日本政府も出来る限りの支援を行ってほしいものである。
NHKニュース(4/4): https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014412001000.html
お正月元旦に能登地方で震度7の大地震が発生し、お正月気分が吹っ飛んだ。能登半島を震源とするが、広範囲にわたり、東京でもかなりの揺れを感じた。東日本大震災でも最大震度7であったので、その規模の大きさは尋常ではない。それにすぐに日本海側の広範囲で津波が発生し、大津波警報まで発令され、東日本大震災の悪夢がよぎった。時間が経つと様々な被害も報告され、輪島で大規模な火災が発生している様子がライブで報道され、地震の被害を実感した。大きな余震も頻発しており、現地の人々の不安は想像を絶するものがある。震源地周辺には、志賀原発という原子炉があるとのことで怖くなった。日本は地震大国だから、原発なんか推進するととんでもないことが起こる恐れがある。地震が起こるたびに、びくびくするので、原発推進の政府方針も是非見直してもらいたいところである。地震のニュースに胸を痛めていた最中、2日に飛行機事故が羽田空港で発生するという惨事が起きた。着陸した飛行機とタクシング中の海上保安庁の飛行機が衝突したようである。乗客は、緊急脱出して全員無事であったようであるが、保安庁の乗員5人は、脱出し重症を負った機長を除き全員犠牲になったとのことである。北陸へ救援物資を運ぶ予定であったというから、何とも言えない思いである。
「天災は忘れた頃にやってくる」とよく言われるが、まさに青天のへきれきでそれも新年のスタートからとは。。。お正月の浮かれ気分も一気に吹っ飛んだ感じである。親鸞聖人が出家する得度式の際に詠んだ「明日ありと思う心の仇桜、夜半に嵐の吹かぬものかは」という無常を謳った句も思い出される。まさに明日何が起こるかわからない世の中である。早く復旧することを祈るばかりであるが、2024年の嫌な前途を暗示するものである。嘘と闇と泥まみれの大阪万博が税金を食い潰すだけで、2024年も破滅に向ってまっしぐらであることも不吉な予感で、下記のデモクラシータイムスを見るだけでもよくわかる。汚染土壌の上にパビリオンを建てて、世界中から人を呼ぶなんて、安全上あり得ないあたりを中国から正当に指摘される前に、岸田政権も大阪維新もメンツを捨てて早く中止を決定すべきである。安倍派の裏金疑惑の全容も解明されつつあり、自民党・岸田政権の裏金国家は2024年に破綻することは間違いなさそうである。
デモクラシータイムス(1/2): https://www.youtube.com/watch?v=gpUPhhXPYkk
12月25日は、クリスマスの日でイエス・キリストの誕生を祝う日であるが、実際は誕生した日ではないようである。Christmasとは「Christ-mas」、「キリスト」の「ミサ」── キリストを礼拝するという意味だという。今年は月曜日だったので、多くの人はクリスマス・イブの24日(日曜)にお祝いイベントを行ったのではないかと思う。我が家でも、クリスマスケーキもチキンも24日にいただいた。
日本では、政界は嵐が吹いているものの、一般的には平和で平穏なクリスマスを迎えているのではないかと思うが、ニュースによるとキリストの生誕地、ベツレヘムでは、多くの教会でクリスマスミサが催されたが、ガザ地区でのイスラエル軍とイスラム組織ハマスとの戦闘を受け、クリスマスツリーの展示などの多くのイベントが中止されたという。パレスチナ人は9割以上がイスラム教徒だが、約1割のキリスト教徒がいて、例年、クリスマスイブは各地のキリスト教徒がベツレヘム集まり、イエスの誕生を祝ってきたというが、今年は、ガザ地区で多くの人が殺害されていることから、宗教行事以外のイベントはすべて中止されたという。
ベツレヘムという名前は、キリストの生誕地としてキリスト教徒でもない自分でもよく耳にしていたので、一度は訪れてみたいと思っていたが、それが実現したのは、2014年4月1日で、エルサレムからバスでベツツレヘムに日帰り旅行した。バスの車中で、簡単なパスポートチェックがあっただけで、特に大きな問題はなかったが、路線バスなので、思った以上にバスの乗降に苦労した。ベツレヘムでは、キリストが生まれたた場所に建てられた聖誕教会が目玉で、生まれた場所は、教会の地下洞窟にあり、銀で星の形がはめ込まれた祭壇となっていた。教会内部には、数多くのランプがつり下げられていたのが印象的であった。エルサレムからはそんなに離れていないのに、今は、パレスチナ自治区に属しており、街の風景もイスラム教徒の街という印象であった。
テレビでも、聖誕教会で「平和への祈り」を捧げるミサの模様が放映されたが、懐かしいとともに今の厳しい状況に心が痛む思いであった。エルサレムはキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の聖地として、死ぬ前に一度は訪れたい魅力ある街なのに、今や訪れることもままならないのは残念である。特に、エルサレムに行ったことがなければ、イエス・キリストやキリスト教や教会について語る資格はないともいえる。早く、イスラエルとハマスの戦争は終結してほしいものである。
写真は、イエス・キリストが聖誕した場所
毎日新聞ニュース(12/25): https://mainichi.jp/articles/20231225/k00/00m/030/010000c
ANNニュース(12/24): https://www.youtube.com/watch?v=gN5J4fSr5lM