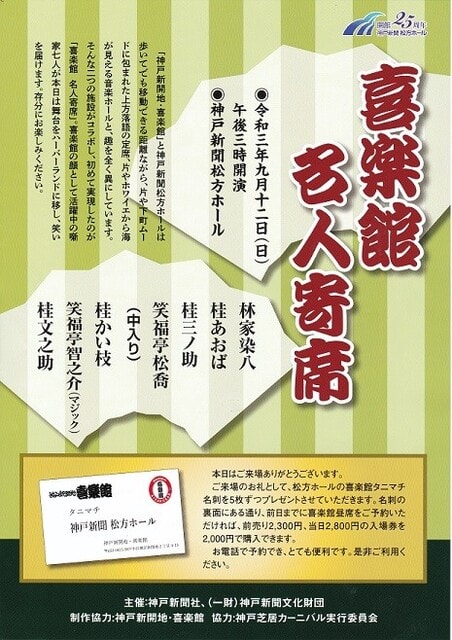喜楽館へ行って来ました。今週は笑福亭生寿さんの上方落語若手噺家グランプリ優勝お祝いウィークです。だから生寿さんが連日トリをつとめます。
開演前の一席は桂雪鹿さん。インドで創作落語を執筆している桂文鹿師匠のお弟子さんです。こんな出番とは思えぬ落ち着いた噺家さんです。「煮売り屋」をやらはった。「東の旅」のプロローグ部分で、「七度狐」の前半部です。落ち着いた噺ぶりでした。
開口一番は、「石段」の出囃子で高座にあがった桂弥っこさん。「真田小僧」です。親をゆすって小遣いをせびるガキの噺です。とんでもない悪ガキで、子供らしくないこまっしゃくれたガキですが、そこがかわいいのです。かわいい悪ガキをいかに表現するかがこの噺のポイントですが、弥っこさん。さすが吉朝一門吉弥師匠のお弟子さんです。なかなかの「真田小僧」でした。
2番手は笑福亭たまさん。たまさんは私がいちおしの上方の噺家さんの一人です。こんなところの出番とはなんとも贅沢な番組構成です。ショート落語を何本かのあと「動物園」をやらはった。大学の落研がやるような前座噺ですが、たまさんがやると大爆笑です。それにしてもたまさんそろそろそれらしい名跡を襲名してもいいころだと思いますが、笑福亭の空名跡はなんでしょう。最大の名跡は八代目松鶴ですが、私はそれでもいいと思うんですが。現実的ではないでしょう。ネットで調べると笑福亭圓篤とか笑福亭梅香という名跡があるようです。そのたまさん、こんど笑福亭のあがりの噺ともいうべき「らくだ」をやらはるそうです。
たまさんで想い出した噺家がおります。浪速の爆笑王と呼ばれた桂枝雀師匠です。枝雀師匠もSRとして落語のショートショートをやってはったし、たまさんの高座っぷりは、なんか枝雀師匠をほうふつとします。一門がまったく違うので不可能でしょうが、笑福亭たまさんが3代目桂枝雀になっても私は違和感はありません。
色もんは音曲漫才のれ・みおぜらぶるずさんの二人です。アコーデオンとギターを持ってるが、ギターを持ってる方のリピート山中さんは「桂雀三郎と満腹ブラザース」のメンバーで大ヒットした「ヨーデル食べ放題」の作者です。この曲、JR環状線鶴橋駅にいけばいつでも聞けます。
仲入り前の仲トリは桂文三師匠。丸顔でいつもニコニコの文三師匠です。「てんしき」をやらはった。寺かたのご住職がお腹を壊しはった。医者から「てんしき」はありましたかとたずねられる。「ちはやふる」や「つる」なんかと同じ知ったかぶりの噺です。お寺のご住職はインテリで物知り。みなから尊敬されるご仁。本人も知らんとはいえない。そんな噺ですが、たいへんおかしい噺です。
仲入り後、幕が上がると赤もうせんを敷いた高座に3人がおりました。左から笑福亭たまさん、笑福亭生寿さん、桂文三さんの3人です。ここは撮影OKです。生寿さん優勝のお祝いの口上がたまさん、文三さんからありました。こういう場では本人はしゃべらないのが通例だそうですが、生寿さんもしゃべりはった。最後は文三さんの音頭で大阪しめで手じめ。
トリ前は笑福亭松五さん。笑福亭松枝師匠のお弟子さんですが、まくらは入門当時のお話し。松五という芸名は「しょうし」のでしだから「しょうご」ですって。おめでたい噺ということで「松竹梅」です。おめでたい名前の3人、婚礼に呼ばれておめでたい芸をする噺です。
さて今日のトリ。もちろん笑福亭生寿さんです。グランプリ本番の時は、不利だといわれている芝居噺で優勝したそうです。芝居噺がお得意なんです。で、この時演じたのも芝居噺です。でも「蛸芝居」「本能寺」「七段目」などのよく聞く噺ではなく「狐芝居」をやらはった。生寿さん、うまいです。つい聞きほれてしまいました。笑福亭生寿さん、これからますます大きな噺家に成長していくでしょう。ライバルの桂二葉さんと切磋琢磨して上方落語の未来を明るくすることを上方落語ファンとして期待します。
「てんしき」「松竹梅」「狐芝居」とあまり聞くことのない噺を聞けて大満足です。
開演前の一席は桂雪鹿さん。インドで創作落語を執筆している桂文鹿師匠のお弟子さんです。こんな出番とは思えぬ落ち着いた噺家さんです。「煮売り屋」をやらはった。「東の旅」のプロローグ部分で、「七度狐」の前半部です。落ち着いた噺ぶりでした。
開口一番は、「石段」の出囃子で高座にあがった桂弥っこさん。「真田小僧」です。親をゆすって小遣いをせびるガキの噺です。とんでもない悪ガキで、子供らしくないこまっしゃくれたガキですが、そこがかわいいのです。かわいい悪ガキをいかに表現するかがこの噺のポイントですが、弥っこさん。さすが吉朝一門吉弥師匠のお弟子さんです。なかなかの「真田小僧」でした。
2番手は笑福亭たまさん。たまさんは私がいちおしの上方の噺家さんの一人です。こんなところの出番とはなんとも贅沢な番組構成です。ショート落語を何本かのあと「動物園」をやらはった。大学の落研がやるような前座噺ですが、たまさんがやると大爆笑です。それにしてもたまさんそろそろそれらしい名跡を襲名してもいいころだと思いますが、笑福亭の空名跡はなんでしょう。最大の名跡は八代目松鶴ですが、私はそれでもいいと思うんですが。現実的ではないでしょう。ネットで調べると笑福亭圓篤とか笑福亭梅香という名跡があるようです。そのたまさん、こんど笑福亭のあがりの噺ともいうべき「らくだ」をやらはるそうです。
たまさんで想い出した噺家がおります。浪速の爆笑王と呼ばれた桂枝雀師匠です。枝雀師匠もSRとして落語のショートショートをやってはったし、たまさんの高座っぷりは、なんか枝雀師匠をほうふつとします。一門がまったく違うので不可能でしょうが、笑福亭たまさんが3代目桂枝雀になっても私は違和感はありません。
色もんは音曲漫才のれ・みおぜらぶるずさんの二人です。アコーデオンとギターを持ってるが、ギターを持ってる方のリピート山中さんは「桂雀三郎と満腹ブラザース」のメンバーで大ヒットした「ヨーデル食べ放題」の作者です。この曲、JR環状線鶴橋駅にいけばいつでも聞けます。
仲入り前の仲トリは桂文三師匠。丸顔でいつもニコニコの文三師匠です。「てんしき」をやらはった。寺かたのご住職がお腹を壊しはった。医者から「てんしき」はありましたかとたずねられる。「ちはやふる」や「つる」なんかと同じ知ったかぶりの噺です。お寺のご住職はインテリで物知り。みなから尊敬されるご仁。本人も知らんとはいえない。そんな噺ですが、たいへんおかしい噺です。
仲入り後、幕が上がると赤もうせんを敷いた高座に3人がおりました。左から笑福亭たまさん、笑福亭生寿さん、桂文三さんの3人です。ここは撮影OKです。生寿さん優勝のお祝いの口上がたまさん、文三さんからありました。こういう場では本人はしゃべらないのが通例だそうですが、生寿さんもしゃべりはった。最後は文三さんの音頭で大阪しめで手じめ。
トリ前は笑福亭松五さん。笑福亭松枝師匠のお弟子さんですが、まくらは入門当時のお話し。松五という芸名は「しょうし」のでしだから「しょうご」ですって。おめでたい噺ということで「松竹梅」です。おめでたい名前の3人、婚礼に呼ばれておめでたい芸をする噺です。
さて今日のトリ。もちろん笑福亭生寿さんです。グランプリ本番の時は、不利だといわれている芝居噺で優勝したそうです。芝居噺がお得意なんです。で、この時演じたのも芝居噺です。でも「蛸芝居」「本能寺」「七段目」などのよく聞く噺ではなく「狐芝居」をやらはった。生寿さん、うまいです。つい聞きほれてしまいました。笑福亭生寿さん、これからますます大きな噺家に成長していくでしょう。ライバルの桂二葉さんと切磋琢磨して上方落語の未来を明るくすることを上方落語ファンとして期待します。
「てんしき」「松竹梅」「狐芝居」とあまり聞くことのない噺を聞けて大満足です。