昨日は例年ならだんじり祭りの日でした。
前日に12町パレードをやって、
昨日は8町のパレードの日でした。
まあもう年齢的には
交差点の警備の役割なんですが、
今は違いますねえ。
町会長としてだんじりの前の
ひな壇に立っていなくてはなりません。
これがねえ、結構腰に響くのです。
なにせ、木でできているタイヤで
動いてますし、当然
ショックアブソーバーもありません。
路面のデコボコがもろに
腰に響いてくるのです。
まあもともとブレーキ係なので
慣れていないことはないのですが、
年齢的にも厳しい所があったりします。
ところがねえ、今年はだんじりの曳行は
1cmもなかったです。
だんじり小屋さえ開けずに、
飾りもつけられず
だんじりはじっと眠ったままでした。
まあこんなコロナの時代ですから
仕方ないですね。
昨日の午後は「宮入」といって
各町のだんじりが我が村の
神社に集まることになっていました。
氏子の関係で6台のだんじりの集合です。
しかし、この神事も結局は
1台のだんじりも来ないで
終わることになりました。
ただし、宮入は大事な神事ということで、
町によっては綱先のまといだけで
お参りに来るという町が2町ありました。
ではこれを氏子総代としては
どうするかということになります。
そもそも祭りがあろうがなかろうが、
神社のスケジュールとしては
秋の奉納というのは
きちんと仕組まれていますので、
だんじり来なくても総代は
神社へと参ります。
こんな風にスーツを着て家を出てゆきます。
ああ、スーツを着るなんて
年に3~4度ですよ。
祭りの総代奉納と正月の初もうで、
それと何か祝い事や
葬儀なんかがあった時ですね。
仕事の経験からネクタイの結び方を
わすれることはないのですが、
なんかこんな姿にはもう
違和感があるような感じです。
そうしてスーツを着て神社に行くと、
もう神主とかは待っています。
ここでスーツの上に
かみしもを付けて待機します。
神殿でお参りをする前に、
まといを持ってやってくる町を待つのです。
静かな境内で、鳥が鳴いている中
ボーっと立っていると、
やってきましたよ。
まといを持って、
若者と祭りの役の人々がやってきます。
そんな集団をお迎えし、
最後の鳥居のところで
神主によるお祓いが行われます。
そのあと集団が本殿前に行き、
代表に会わせて柏手を打ちます。
そしてまた集団のまま
神社を出ていって解散します。
これが1町の動きですね。
これをあらかじめ依頼のあった
2町分を済ませたら、
そこから総代のお祈りが
本殿の中で行われます。
お祓い、のりと、榊の奉納と続き、
最後にお神酒をいただいて終了です。
終了時に本殿から出てきたところで、
見に来ていたミセスに写真を
撮ってもらって、すべて終了です。
二日間、もしだんじり曳行が
あったとしたら、
とっても晴天のいいお天気でしたね。
すこし暑いくらいだったかもしれません。
来年こそは、だんじりを
神社内に並べてにぎやかな中で
厳かにお参りすることが
できるでしょうかねえ。
今日はそんな静かな中で
しっくりと行われた
宮入の奉納だったのであります。
ここにある狼の像はネットで見るとこんな感じ。
階段を上りながら探していきましょう。
父親が犯罪を犯したというのは嘘で、
願掛けをしていた娘の前に狼が現れて、
それ以降父親が無実になった
という昔話があるそうです。
そこから設置された像です。
でもねえ、見当たりませんよ。
本堂の所とかお墓の所なんかを
見ましたが見つけられません。
う~ん、ここまで来て
からぶりかと思いながら、
寺の周辺も合わせて探しましたが見つかりません。
犯罪の話と清廉潔白なdoironとじゃ
相性が悪いんですかね。
結局見つからないまま、
そこを後にすることにしました。
でもねえこのままだったらつまらないので、
最後に野間の大けやきを見に行くことにしましたよ。
ではまたナビを入れましょう。
え~っと「のまのおおけやき」と
入れるのですが、出てきません。
ネットで住所を調べて入れても
なんかはっきりとしません。
結局「けやきしりょうかん」といれたら
出てきましたので、
その案内に沿って進んでいきましょう。
もうここには4回くらい
来ているはずなんですが、
やはりこういう大きな命に
会いに行くというのは
こころはずみますねえ。
あんな大きなけやきですから、
近づいていったらわかるはずだ
と思うのですが、周りがもう
山の緑がいっぱいなんで、
何となく見落としてしまいがちです。
とそうしているうちに、
ようやくその姿が見えてきました。
近づいてゆくと大きな木です。
けやきとしては大阪府で最大です。
樹齢は約1000年で
昭和23年に国の天然記念物になりました。
生育地はかつてこの場所にあった
蟻無宮(ありなしのみや)の
境内跡地であり、このケヤキは
同社のご神木であったそうです。
蟻無宮なので、この木の生えている
下の土を持って帰って巻くと、
蟻がいなくなるそうです。
クスノキだったら防虫剤の役目を
持っているから、1000年も経た
木の下の土なら蟻もいやがるかも
しれんけどねえ。
まあそんな言い伝えがあるそうです。
ちなみに日本最大のけやきは
山形県の東根小学校の
校庭の西北隅にある、
東根の大ケヤキで、樹齢は1500年を
超えるといわれています。
ちょっと見に行くには遠いかなあ。
ではその野間の大けやきには
駐車場もあるのでそこに
車をとめてじっくりと見に行きましょう。
まずはけやき資料館に入って
勉強してゆきましょう。
そこには、このけやきに住む
フクロウ科のアオバズクのことが
たくさん展示されていました。
まあこれだけ大きいと
鳥にはいい木ですよねえ。
そうそうここは大阪みどりの百選
の一つでもあります。
では外に出て、クスノキの周りを
歩きましょう。
まわりにはぐるっと一周回れるように
なっており、蟻無宮のほこらあたりは
かなり近づけるようになっています。
木をじっくり眺めながら、
時折みられるアオバズクの姿も
探したのですが、見つけられませんでした。
では横にならんで写真撮影です。
木の周りも整備されていて、
たくさんの花々が植えられ、
あの槇尾川にあった
センニンソウによく似たボタンずるも
生えています。
けやきは樹形が幅広く大きいので、
木の下は広大な野原になっていますねえ。
しばらくそこでのんびり過ごし、
けやきの命のかけらを
いただいてきたような感じでした。
さあこれで能勢の旅も終わりです。
大阪で最北端の町で、
秋をいっぱい感じて帰った
そんな一日でした。
香川に行った時に立ち寄ったのが、
津田の石清水神社。
海辺にある神社でしたねえ。
建物も古くてよかったのですが、
ここの特徴はやはり狛犬。
日本狼が狛犬になっているのです。
そんなことから、日本の狛犬の話を
ネットで少し勉強しました。
大阪じゃ犬鳴山が
山犬みたいな狛犬だといいます。
そして少し離れたところでは、
能勢の放光山慈眼寺が狼の狛犬だといいます。
まあお寺なので狛犬とは言い難いのですが、
父と娘の話の中から想像される
狼の立像があるといいます。
ではいつかこれを見に行かなくちゃ
と思っていたのですが、
ころあい的にも今がクリの季節で
あることから、クリ購入も合わせて
そちらへ行くのもいいなあと考え、
出かけて行ったのです。
秋のクリを求めて、ドライブです。
ここへ行くには阪神高速ですね。
堺線から乗って、豊中を抜け、
大阪空港の横を通り、どんどん北へ
向かって行きます。
高速を降りたら、国道173号
丹州街道を走ってゆきます。
一蔵ダムを過ぎて、
少し人里のようなところに来たら、
道の駅「能勢クリの里」に到着です。
いつもはここにクリを買いに
来るのですが、たいていは収穫の
ピークを外しています。
店の中に入ってゆくと、
クリの棚だけが空っぽになっています。
ピーク時にはそんな感じで、
あっという間に売り切れてしまうんですね。
で、今年はきたのは、
クリにはまだ少し早い時期かなあって感じです。
道の駅の車も少ないから
ああまだクリの販売はまだかなあ
って感じでしたが、
店に入ってみますとクリの棚に
固まりが二つだけ乗っていました。
ああ、久しぶりにこのあたりの
クリが帰るんやあって感じでしたね。
クリを買うぞと気合を入れて
来たのではないのに、
案外そんな時に買えてしまうなんて、
人生なかなか思うようにはいきません。
さてではクリも買ったし、
本日一番の目的地である
慈眼寺に向かいましょう。
事前に調べてあったので、
ほぼ位置はわかっていますが、
ナビで案内してもらいましょう。
なにせ小さな橋を渡ったら、
肝心な道路に入っていくみたいな
ちょっと感覚的にややこしいしいのです。
このあたりの道は能勢街道と合わさって、
丹波の米などの山の産物と
瀬戸内の海産物が、昔は行きかった
道だといわれています。
まっすぐに一本道が続いている
わけではなくて、自然の景色と
ひとつになってくねくねと
続いていく道が多いですね。
マイカーは対向車が来ませんように
なんて祈りながら、山の谷間沿いの
狭い道を走り、自然の中を進んでいきますと、
ああお店で売ってたように
もうあちこちでクリが実をつけていますね。
道にもイガイガが散らばっています。
もうあんな元気そうなクリやったら
パンクせーへんやろな
なんて気づかいながら走ります。
山の斜面は棚田になっており、
いい感じの景色も続きます。
そういえば昔、ここの棚田を訪ねて
ぶらぶらしに来たことがあったなあ。
田んぼ道を歩いている人を見て、
こんなところ歩くって
大変やなあって思っていたなあ。
今だったら少しうらやましい感じがするから
不思議なもんだ。
狭い山道を抜けてこんな山の中に
寺があるのかなあと思ったら、
突然そのお寺に到着しました。
駐車場に車をとめ、
山道を歩いて行きましょう。
お寺なので、狛犬としてあるんでは
ないだろうと思いながら進んでいくと、
本堂へ上がっていく階段の下に出ました。
続く
来週の月曜日ですが、
スポーツの日ということで
カレンダーでは休日になっていますが、
間違えちゃいけませんよ。
doironのカレンダーを見てください。
10月11日は平日になっていますからね。
とまあこう書いても、
もう年齢的に仕事とかの分野から
遠ざかっている友達も多いので、
さほど大きな影響はないのですが、
まだまだ仕事だと頑張っている
皆さんは休みだと思って油断しないで、
しっかり気を付けてください。
そんなdoironのカレンダーですが、
早いものでもう製作時期にはいっています。
なんと今年はこのカレンダーが出来て、
もう10作目のカレンダーです。
ということはまあ、絵的にはすでに
120枚以上描いているって感じですね。
昔は絵を何枚も載せていたこともありますので、
実際はもう少し多いですね。
趣味で始めたお絵かきですが、
カレンダーにすることによって
少しでも皆さんの目に
触れることができるのが
うれしいですね。
ある意味迷惑な部分もあるかもしれませんが、
トイレにでも飾ってスケジュール管理にでも
使ってもらえたらなあって思います。
まあこんな素人の遊びなんですが、
それなりにいろいろ工夫もしています。
今回は祝日設定に関して機敏に
対応できたのでそういう意味で
少しは役に立てれたかなあ
とか思っ足りなんかしちゃってね。
で、来年のカレンダーですが、
いろんな対応があります。
まずは日にち部分の製作です。
これはねえ、非常に権威のある
100均のカレンダーをもとに
製作しています、へへ。
多分祝日配置は元に戻りますね。
首相が変わってもその考えは
変わらないでしょう。
あとは月のカレンダー配置の
空きの部分に何を入れるか
なあんてことも
常に意識しつつ考えています。
日常生活の中で、
こんなことが分かったらいいなあ
なんてことはないか
なんてことを意識しつつ、
世の中を眺めているわけです。
はてさて来年はどうなるでしょうかね。
まだ決まってはいません。
そして時間がかかるのはやはり絵です。
まだ、すべてのページを埋めれる量の
絵はできていません。
今年はなんかお絵かきに熱中する期間が
短かったようです。
最近お絵描きのテーマも減ってきて、
あ、これを描こうなんて言うテーマに
すぐには行きあたらなかった
ということもあります。
世の中を眺めるときに、
テーマはないかなあなんてことも
意識しながら、きょろきょろ
暮らしているわけです。
スーパーなんかいったらあきませんね。
あ、これなんか書いてみたら
どうかなあなんて考えると、
携帯で写真を撮ったり
することもたまにあります。
定員さんなんかは、
よそのスーパーの闇調査員かもしれんなあ
なんて考えたりしていないでしょうか。
世の中を眺めるときに
スパイ大作戦のように、
こそこそ生きています。
お絵かきの中で1枚だけ、
最近はテーマを決めている絵があります。
それは1月分です。
その年の干支を絵に描いています。


来年は虎ですね。
ではそれを描いてみましょう。
虎も以前描いたことがあるので、
今回は張り子のトラを描きます。
まずは下書きをしましょう。
おもちゃなんで、
けわしい目つきとかはあきませんね。
のんびりとした顔にしましょう。
鼻も豚鼻みたいにしています。
そして出来上がったのが、こんな下絵。
親子の虎にしました。
正月なんで、少しのんびりした
親子姿にしています。
これに色をぬっていくわけですが、
果たしてどんな絵になりますか。
年末配布のカレンダーを見てください。
ブログではこんなカレンダー製作時の
報告もこれから少ししていくことにしましょう。
大阪ミナミの高島屋で開催されていた、
安野光雅の絵画展がもう終わるというので、
慌てて見に行ってきました。
(もう終わっています)
コロナの時代に繁華街まで行って、
人混みの中で絵画鑑賞もどうかなあ
って感じだが、今回の絵画展の
主なテーマが前から興味深かった
「洛中洛外」であったので
やはり出かけていくことにしたのだ。
この絵画群は産経新聞の夕刊に
時折掲載されてた。
レベルは全く違うのだが、
いやもう全くレベルの問題では
ないのだが、水彩画のこの絵を
見るたびに、自分でこんな絵が
描けたらなあと本当にうらやましく
思ってしまうんだよね。
「もっているものが違うんだよ」
と優しい友達は言ってくれたりするのだが、
いやあ描いててもう全くの違いを実感している。
こういうあきらめが
人生の中には多いものだ。
それは仕方ない。
でもまあそんなキラメキの多い絵を
しっかり見ておけば、
少しくらいはおこぼれに
預かったりすることもあるかもなあ
なんて思いながら
都合よく出かけて行くわけだよね。
早速南海電車に乗っていってみた。
会場に入ってみると、
おお~なんていう人の多さだ。
できるだけ集団にならないように
歩いていると、なかなか絵には近づけない。
かといってずっと息を止めておく
わけにはいかないので、
マスクを隙間がないように
きちんとつけ鑑賞することにした。
展示は、作品そのものと
その横に絵のタイトルと
安野さんの言葉が少し描かれてある。
多分新聞掲載時の言葉が
書かれてあるのだろう。
中には新聞にも載らなかった
作品群もあるのだが、
そんなところにも言葉が
書かれてあったりした。
そんな解説板の下にはこう書かれてある。
「産経新聞掲載」
おお~この言葉でよくわかりますねえ。
でもねえその時ふと思ったんです。
doironの絵も、これと同じことが
書けるじゃないかってね。
絵の解説の下にそう書けばいいわけで、
今のところは5枚ありますからね。
じゃあ、タイトルは何にしましょう。
消毒薬とマスクの絵は
「守ってね!」がいいかなあ。
ミズナスの絵は
「心に漬け込んでください」
巻きずしの絵は
「巻いて巻いて、幸せ巻いて」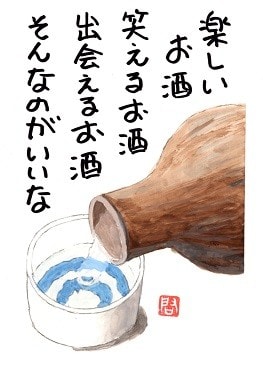
お酒の絵は、こんなお酒なら
「飲みつぶれたいなあ」
岡山ちらし寿司の絵は
「幸せのおすそわけ」
う~んなんかとっても庶民向け。
でもねえ、これらの絵の下には
「産経新聞掲載」って
書けるんですよねえ。
ほんの1mm、安野さんに近づけたかなあ。
他にも掲載はされなかったけど
梅の絵とかもありますよ。
そしてこの秋に送った
エノコログサも乗らなかったから、
ここで掲載しておきましょうかね。
こんな絵でした。
新聞に載せるには絵が小さかったかなあ。
まあそれはさておき、
安野さんの展示を見ていると、
絵の中でここという部分には
鮮やかな色を使っています。
これは「ムラサキサギゴケとタンポポ」の絵。
タンポポの黄色が生えていますねえ。
またほかの絵ではバックの
塗りつぶしなんかも
かなり考えて塗られているようですね。
これは「カラスウリ」の絵です。
バックの茶色が鮮やかに
実の赤い色を輝かせています。
ああ、こんな風に描くことも
重要なんですねえ。
いま絵の対象を見ながら、
何を輝かせるか、
これがとても大事なんですねえ。
安野さんの絵をじっくり眺めながら、
また一つ何かを学びましたね。
早速次の絵からは
できるところから
取組んでいきましょうか。
毎年作っているカレンダーも
ぼちぼち本気入れて
作ったいかなくちゃなあ
と思ったりもした
ガハガハ画伯のdoiron
だったのでした。













