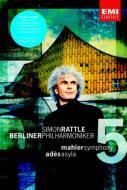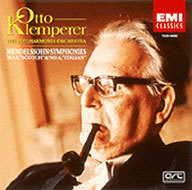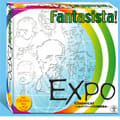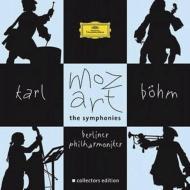今日も先日に引き続きクラシック音楽の話題です。
モーツァルトのピアノ協奏曲第20番には数々の名盤がありますが、私が選ぶとっておきの1枚と
いえば、《Clara Haskil=クララ・ハスキル》(ルーマニア 1895-1960)が弾いた盤です。
これはハスキルが亡くなる1ケ月前に録音したもので、まさに《白鳥の歌》です。
この盤を聴く前にも後にも何人かのピアニストの演奏を聴きましたが、今でもハスキルの盤は
私にとって特別です。
モーツァルトが遺したピアノ協奏曲は全部で27曲ありますが、その中でも”短調”で書かれた
作品はこの第20番(ニ短調)と第24番(ハ短調)の2曲のみです。
特に第20番はベートーヴェンにも影響を与えており、後に第20番のカデンツァを書いていま
す。そのくらい他の作品と一線を画しています。
そういえば映画『アマデウス』でのエンディングタイトルが、この第20番の第2楽章でしたね。
とても印象に残っています~
モーツァルトのピアノ協奏曲第20番には数々の名盤がありますが、私が選ぶとっておきの1枚と
いえば、《Clara Haskil=クララ・ハスキル》(ルーマニア 1895-1960)が弾いた盤です。
これはハスキルが亡くなる1ケ月前に録音したもので、まさに《白鳥の歌》です。
この盤を聴く前にも後にも何人かのピアニストの演奏を聴きましたが、今でもハスキルの盤は
私にとって特別です。
モーツァルトが遺したピアノ協奏曲は全部で27曲ありますが、その中でも”短調”で書かれた
作品はこの第20番(ニ短調)と第24番(ハ短調)の2曲のみです。
特に第20番はベートーヴェンにも影響を与えており、後に第20番のカデンツァを書いていま
す。そのくらい他の作品と一線を画しています。
そういえば映画『アマデウス』でのエンディングタイトルが、この第20番の第2楽章でしたね。
とても印象に残っています~