最近、仕事が忙しかったこともあって、ブログを更新できず。。。
これからは出来るだけ毎日更新に努めようと決意も新たに!
さて、本題に入ろう。
チュニジアで起きた政権交代がエジプトやリビア等に飛び火し、隣国/中国でも同様の動きが拡がるのでは・・・との報道が日本で連日展開されている。
実際、日曜日には多くの都市で集会が開かれたとのことだが、実際のところ、どのような集会だったのか、どれくらいの規模だったのか、詳しいことは分かっていない(当局の報道規制も厳しい様子)。
そもそも革命や政変とは、どのようなことで起こるのか。
筆者は、誤解を恐れず端的に言うならば、国家の権力の源とも言える「軍」の行動次第だと考える。
今回のエジプトを例にとっても、最終的には軍が引導を渡した形となっている。リビアにしても、もはや正規軍は反政府側に寝返っていると言っても過言ではなく、そうした事態の発生を事前に見通していたかのような傭兵部隊が、何とか首都の治安を維持している有様である。
つまり、革命や政変は民衆の不満がきっかけとなって起こるわけだが、最終的な政権交代に至るのは、軍が新政権側に立つのか、新政権側が既存の軍を妥当するのか、このふたつしかないのではないか。
そう考えると、中国の状況はどうか。
現在報道されているように、たしかに貧富の差は拡大する一方である。わずか10%の富裕層が国家全体の富の40%強を保有すると言われるほど、富裕層の経済力は増している。その一方で、農村部・山岳地帯の農民は低所得に喘いでいる。
だが、今回の集会が軍を転覆するほどの力を有しているのか、又はそこまで勢力を拡大する可能性があるのか、と考えると、いささか心許ない。残念ながらその力はないと言わざるを得ない。
なぜなら、中国軍の軍部は経済的に不遇な立場にいるわけではなく、むしろその逆で、体制派として君臨しておくほうが自分たちにとってメリットが大きい。つまり、他国のように民衆蜂起を見過ごすことで得るものはほとんどないのである。
しかも、北アフリカの国々と中国とでは、経済成長の面で圧倒的な違いがある。中国人民に不満が溜まっていると言っても、北アフリカ人民の不満とは比べるまでもないのである。
中国人民は、基本的には現在の国家運営に不満を抱えつつも、その一方で安定を求めている。これは、中国が歴史上経験してきた文化大革命や天安門事件なども微妙に影響しているのだろう。
よって、少なくともこの2、3年で政権交代が成し遂げられる可能性は、限りなくゼロに近いと見ている(ただ、中期的には緩やかな変革の可能性は大いにあり得ると考えている。その点は、時期を改めて綴りたい)。
最後に日本はどうだろう。日本は第2次世界大戦以降、正規軍を有していないとの立場に立ってきたが、逆に言えば、政府が国家権力の源を保有していないとも言える。幸い周囲を海で囲まれており、朝鮮半島を除けば、目立った紛争もなかったため、米国の庇護の下、経済活動に専念することができたが、本格的な大競争時代を迎え、今後はそういうわけにはいかない。
筆者からみると、こうした国家観の欠如が近年の短命政権の続出や稚拙な外交の遠因になっているように思えてならない。
だからと言って、軍事政権を目指すべきという立場ではない。
「自衛隊をどう位置づけるのか」、「集団的自衛権のあり方とは何か」といった根本的な課題に結論を出さなければ、安定した経済の発展も見込めないのではないだろうか・・・?
これからは出来るだけ毎日更新に努めようと決意も新たに!
さて、本題に入ろう。
チュニジアで起きた政権交代がエジプトやリビア等に飛び火し、隣国/中国でも同様の動きが拡がるのでは・・・との報道が日本で連日展開されている。
実際、日曜日には多くの都市で集会が開かれたとのことだが、実際のところ、どのような集会だったのか、どれくらいの規模だったのか、詳しいことは分かっていない(当局の報道規制も厳しい様子)。
そもそも革命や政変とは、どのようなことで起こるのか。
筆者は、誤解を恐れず端的に言うならば、国家の権力の源とも言える「軍」の行動次第だと考える。
今回のエジプトを例にとっても、最終的には軍が引導を渡した形となっている。リビアにしても、もはや正規軍は反政府側に寝返っていると言っても過言ではなく、そうした事態の発生を事前に見通していたかのような傭兵部隊が、何とか首都の治安を維持している有様である。
つまり、革命や政変は民衆の不満がきっかけとなって起こるわけだが、最終的な政権交代に至るのは、軍が新政権側に立つのか、新政権側が既存の軍を妥当するのか、このふたつしかないのではないか。
そう考えると、中国の状況はどうか。
現在報道されているように、たしかに貧富の差は拡大する一方である。わずか10%の富裕層が国家全体の富の40%強を保有すると言われるほど、富裕層の経済力は増している。その一方で、農村部・山岳地帯の農民は低所得に喘いでいる。
だが、今回の集会が軍を転覆するほどの力を有しているのか、又はそこまで勢力を拡大する可能性があるのか、と考えると、いささか心許ない。残念ながらその力はないと言わざるを得ない。
なぜなら、中国軍の軍部は経済的に不遇な立場にいるわけではなく、むしろその逆で、体制派として君臨しておくほうが自分たちにとってメリットが大きい。つまり、他国のように民衆蜂起を見過ごすことで得るものはほとんどないのである。
しかも、北アフリカの国々と中国とでは、経済成長の面で圧倒的な違いがある。中国人民に不満が溜まっていると言っても、北アフリカ人民の不満とは比べるまでもないのである。
中国人民は、基本的には現在の国家運営に不満を抱えつつも、その一方で安定を求めている。これは、中国が歴史上経験してきた文化大革命や天安門事件なども微妙に影響しているのだろう。
よって、少なくともこの2、3年で政権交代が成し遂げられる可能性は、限りなくゼロに近いと見ている(ただ、中期的には緩やかな変革の可能性は大いにあり得ると考えている。その点は、時期を改めて綴りたい)。
最後に日本はどうだろう。日本は第2次世界大戦以降、正規軍を有していないとの立場に立ってきたが、逆に言えば、政府が国家権力の源を保有していないとも言える。幸い周囲を海で囲まれており、朝鮮半島を除けば、目立った紛争もなかったため、米国の庇護の下、経済活動に専念することができたが、本格的な大競争時代を迎え、今後はそういうわけにはいかない。
筆者からみると、こうした国家観の欠如が近年の短命政権の続出や稚拙な外交の遠因になっているように思えてならない。
だからと言って、軍事政権を目指すべきという立場ではない。
「自衛隊をどう位置づけるのか」、「集団的自衛権のあり方とは何か」といった根本的な課題に結論を出さなければ、安定した経済の発展も見込めないのではないだろうか・・・?












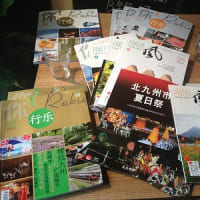


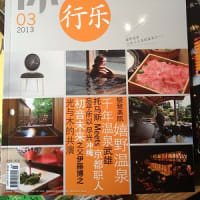




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます