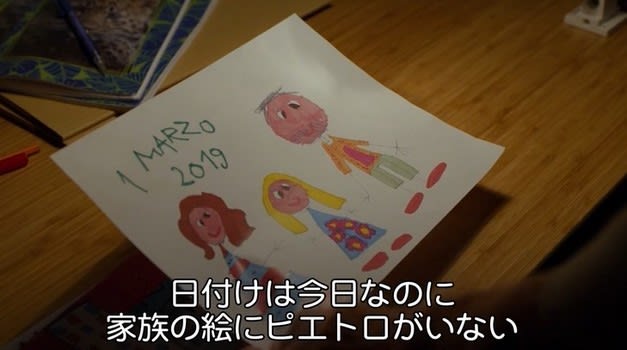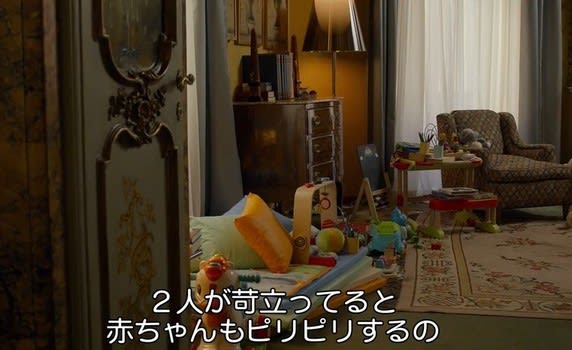あれは僕が大阪市立大学の1年の頃だったと記憶している。
僕の半血の姉、長崎京子が、僕を岡本の自宅に呼んでくれたのだ。阪急を岡本駅で降りて、六甲山へ向いた坂を歩いていった。 左に甲南大学の校舎を見ながら、結構急な坂を登った覚えがある。

<阪急・岡本駅>
この日の 京子との出会いは、僕のその後の人生において大きな出来事だったと、後になって分かってきた。
彼女のご主人が、日本郵船のハンブルグ支店長の任期を終えて、二人で日本に帰って来て、この地、岡本に住み始めた。その家へ、僕を呼んでくれたのだ。ご主人の映吉さんとは、見ず知らずだが、京子姉とは帰国したら会おうという約束はできていた。

<ハンブルグ港>
とても素敵な家だった。庭からは足元に芦屋の街、神戸の街、そして遠くには淡路島の影も見える南向き斜面の大きな家で、おそらく東灘区の桜坂近辺だったのだろうと思う。緑の芝生がまるで外国のように美しくて、僕は驚いていた。 生垣を挟んで隣にも人が住んでいるらしく、黒い大型の犬が生垣の間から 鼻を覗かせてクンクンといっていた。僕が近づくと、しっぽをユサユサ振っているように思えた。 しかしすぐに外国語(おそらくドイツ語)で何か命令されて、飼い主の方に戻って行ってしまって、その後は見ることはできなかった。ああ、ここでは犬も外国語が分かるのだと羨ましく思った。
半血と言ったのは 、僕の母、嘉與が僕の親父と結婚する前に一度結婚していて、子供を二人持っていたということから始まっている。最初に結婚したご主人は、若くして二人の子供を残して病気で亡くなってしまった。二人の子供はご主人の実家、土佐・安芸の大店に引き取られ育てられた。母、嘉與はその後、僕の親父と結婚して二人の姉と僕を産んだ。 だから一番上の兄姉は、異父兄姉だった。 つまり僕は5人兄妹姉妹の末っ子ということになる。 この関係を半血と呼んでいる。

<半血兄弟姉妹>
岡本での姉との話は、どんな内容だったかは、もう忘れているが、憧れのヨーロッパでの生活と、北海に面したドイツ最大の港、ハンブルグの様子、食べ物や文化の話などを聞いて、強い興味を引かれたことをはっきりと覚えている。 ハンブルグはヨーロッパの国際河川、エルベ川(ラベ川とも呼ばれている)の河口の港町だ。 この川を遡っていくと、どこまで行くのかと思うくらい、Google の地図は続いていていた。最後は、チェコとポーランドの国境に近い山が、その源流だった。

<エルベ河>
ハンブルグといえば、アメリカでハンバーグと呼ばれる、例のハンバーガーが思い出される。これは昔、ドイツのつましい人たちが馬の硬い肉をミンチして、やっと食べられるように作ったとの説明がある。
この岡本訪問が、僕にヨーロッパに行ってみたいという強い気持ちを抱かせた機会だった。 彼女にそういう意図があったかどうかはわからないが、僕が行きたいなという気持ちを持ったことは事実だ。
僕が大学を卒業して就職試験を受けるとき、候補の一つとしてアメリカのコンピューター会社があった。 日本の出版社とアメリカの会社の試験日がぶつかった時、頭のどこかにあった外国に行きたいという気持ちが大きく作用したのだろう、アメリカの会社を選び、入社することができた。
岡本を訪ねた頃から 数えると、6年ぐらい経っていたと思う。僕は大阪市立大を中退し、東京で改めて法政大学を卒業したから、大学生活は合計6年間になった。

<コンピューター Sモデル>
アメリカの会社に入ったので、英語は必須だった。大学受験の頃、FENを聞いてジャズにはまり、 友達のお姉さんの子供、アメリカ人とのミックス、ジャネットのかわいい姿と仲良くなるために、英語を一生懸命しゃべった。結果として、アメリカの会社に入る”クオリフィケーション”を身につけさせてくれたのだろうと思う。
27歳の時、海外での仕事のオッファーを受け、イタリアに2年ほど駐在することになった。 1969年の年末に羽田から、アンカレッジ経由の北周りの飛行機を降りたのが、あのハンブルグだった。岡本とのつながりを感じた時間でもあった。着陸するとき、日本のけばけばしい蛍光灯の光とはと違って、うす暗くて、ポツポツと街灯がついている放射状の町並みを見ながら飛行機は降りていった。僕が初めて外国の地を踏んだ場所が、奇しくもハンブルグだったのだ。興奮していたのは間違いない。
翌朝、飛行機を乗り換えてシュツットガルト経由で、イタリア・ミラノのリナーテ空港についた。長い旅だった。 そして、ミラノでとてもいい時間を過ごし、日本と違う文化と異世界を体験する時間を持つことができた。それは目に見えない大変な宝物だった。

<ミラノ リナーテ空港>
ミラノ駐在員の生活のことは、別の本「父さんは足の短いミラネーゼ」に書いているから、ここでは触れないことにする。(電子ブック http://forkn.jp/book/1912/)

日本に帰ってからの僕のキャリアに繋がることを、ひとつ話しておくと、ミラノで、「コンピューターシステムを使った業務設計」を勉強することができたことだ。それがその後、IBMで20年間、業務アプリケーション開発の仕事につながる大きいステップだったと思う。
僕が横浜に戻ってきてからも、 京子姉とは付き合いが続いていた。彼女も岡本から引っ越して、世田谷 の用賀 に住んでいたから、比較的近い距離にいたわけだ。
京子姉のお陰だと思う集まりができて、今も活動している。それは母方の土佐・奈半利の竹崎家の東京近郊の係累の人たちを集めた「いとこ会」だ。最初の二回は、用賀の姉の家で開かれた。 京子姉はもう他界しているが、今も「いとこ会」は続いている。

<いとこ会>
瀬田の斎場で行われた映吉さんの立派な告別式には、僕も親戚一同の一人として参列したことを覚えている。映吉さんとの間には子供がいなかったから、映吉さんが亡くなったあと、京子姉は一人ぼっちの生活だった。姉は、その後東京を離れ、神戸の裏座敷と呼ばれる有馬にある立派な老人ホームに入った。
そのころ毎年クリスマスになると、ドイツのクリスマスケーキ、シトーレンを神戸のフロインドリーブから僕が姉に送り、シトーレンの品評会を二人でやっていたことを思い出す。日本で一番美味しいシトーレンだと、ドイツに住んでいた京子姉が同意してくれたので、僕は今もフロインドリーブのシトーレンが、一番美味しいと信じている。

<フロインドリーブのシトーレン>
阪急・岡本の京子姉の家の訪問と、ドイツ語を理解する黒い犬に出会わなかったら、アメリカの会社に入っていなかったかもしれないし、ミラノ駐在も実現していなかったと思う。 京子姉は13年前の2008年7月に、84歳で他界した。天国にいる京子姉にありがとうといって、この話を終りにしよう。