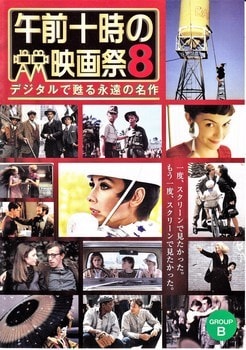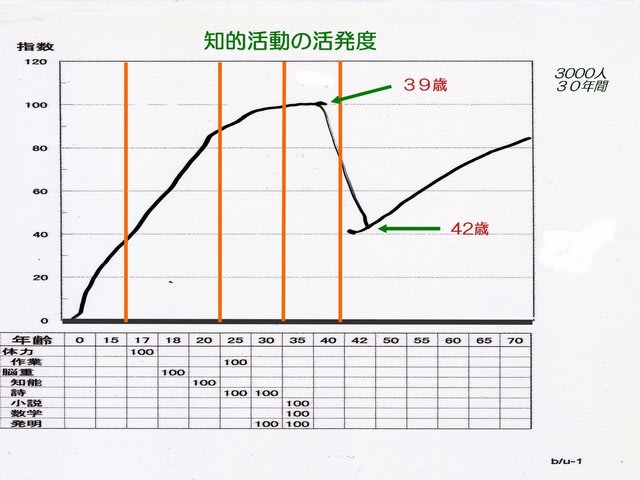台風一過の三浦半島の荒崎に、車を走らせてきた。

<荒崎>
10月の遅い台風の影響や、その前からの秋雨前線のお陰で、一週間以上も家に閉じ込められていたから、まあ、どこでもいいからで掛けてみようと思いついたのが、三浦半島の荒崎。
三浦半島の西海岸で知られた所といえば、城ケ島、三崎とか、油壷マリーナ、佐島マリーナ、葉山、逗子などの名前が挙がってくるのだろう。真っ先に荒崎と名前を上る人は、少ないだろうと思う。どちらかというと、地味な存在だ。
しかし僕にとっては、1963年に絵を描きに行ってから、50年以上の付き合いのあるやはり懐かしい場所なのだ。特に、荒崎の丘の上がいい。

<1963年のスケッチ>
荒崎は、風の強い丘、波しぶきに舞い上がる海の臭いを浴びる場所、岩と波の戦いを見る場所、そして茫然と立っていることのできる場所だ。どちらかというと、夕暮れがいい。

<岩とススキ>
丘の頂上に登り、相模湾の広がりを目にし、相模湾を吹き渡って来る西風に髪をザンバラにされながら、たたずんでみる。耳元をボウボウと風が吹き抜けていく。一人だけで、自分自身と語るときを持てる場所。風が聞いてくれるモノローグだ。

<荒崎からの富士>
1963年と明確に分かるのは、荒崎の下手なスケッチを残しているからだ。そこに1963年5月21日と書いている。この絵を描いた時、僕は一人だったのか、誰かが一緒だったのかは覚えていない。その時も、潮騒の音がして、風の強い日だっただろうと思う。
別の時には、子供たちと、磯遊びをした懐かしい場所でもある。波が削ったリアス式海岸の岩場の底に、潮が引くとたくさんの潮だまりができる。そこを、二人の子供の手を引いて、海の生き物を探して歩く。彼らにとっては大冒険。いろんな生物を発見する。小さなカニ、ハゼ、エビ、ヒトデ等を探して歩く。やはり一番面白いのは、ウミウシたちだ。棒で、突っつくと、真っ青な水を吐き出してチジコマって隠れる。あれは、明るい日の下の風景だ。こんな記憶が彼らに、なお残っているか聞いてみたいが、あれは楽しい穏やかな時間だった。僕んちは、湘南・江の島の西浜や東浜より、三浦の方が好みだったようだ
その後、荒崎の岩場でバーベキューなどを始める人があらわれて、入江の岩場は汚くなっていった。匂いが染みついている岩場になった。荒崎が汚された気がしたものだ。

<どんどん引き>
また別の日には、小さなグループで「どんどん引き」を過ぎて岩場に降り、岩場の道を注意しながら、歩いた記憶がある。小さな海岸洞窟から始まって、岩場の上にかけられた人口の橋を渡って岩場と浜を歩いていく。途中に浜小屋や、小さな売店があって、一休み。こんな時間を一時間くらい持てば、いつか、長井の浜に着く。ちょっとした、海岸の散歩だ。懐かしいが、この道が今もあるのかどうかはわからない。しかし、今や僕の心臓君の方が心配だ。
ある夏には、友達と犬を連れて、長井の浜で水遊びをした記憶もある。犬が、はしゃいで友達を追いかけまわし、シャワールームまで飛び込んで、キャーキャーと悲鳴が上がったのを覚えている。まさに真夏の記憶だ。この長井の浜は、三浦半島の西海岸では、珍しく静かでゆったりとした浜だ。幸い、国道134号線から外れていて距離があるから、逗子や葉山・森戸みたいな混雑はない。まあ地味な浜だ。会社の友人たちが、共同でヨットを揚げていた浜でもある。

<長井の浜>
モノローグから我に返って、昼飯を喰っていないのを思い出した。三崎のマグロずしも考えたが、もうせんの、高くてまずい記憶が残っていたので、最近うわさにきいた佐島マリーナの近くの寿司屋に寄って、地魚の握りを食ってみた。やはり、相模湾の鯵はうまかった。
佐島と言えば、会社の研修や、僕のセミナーをやったことがあって、懐かしい島。森繁久彌さんが作ったマリーナも、ホテルも、以前のような素敵な佇まいとは言えない古びた感じだった。マリーナとしては、活気があるようだ。昔、歩いた天神島の見える浜の公園は、休日で閉まっていた。残念。
三浦半島の最高峰の大楠山(242m)にも、僕は2回くらい登ったことがある。頂上からは相模湾が一望だった。そして、帰りのバス停は、佐島の近くの「大楠・芦名口」だったのを思い出した。こちらも懐かしい。安針塚からのハイキングには楽しいルートだ。
荒崎から帰りに、カメラで富士山を狙ってみた。ほとんど真西の直線距離で85㎞くらい先の富士山は、相模湾の遠くにシルエットを見せているだけだった。

<富士のシルエット>
三浦半島・西海岸へのアクセスは格段に良くなっていた。三浦縦貫道から横浜横須賀道路に直結していて、強い横風に少しあおられながら、車を横浜に向けてブッとばしながら考えた。
やはり、今の遺言書の通り、僕の散骨は相模湾の沖にしてもらおうと思った。何故って、やはり懐かしい海だからだ。