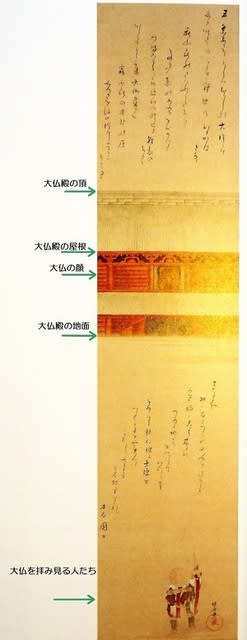伊豆高原への旅が、15年ぶりにやっと実現した。カスケットリスト(棺桶リスト)にある、くたばるまでに達成しておきたい項目の一つだった。

<大室山>
実は、今回が3度目の正直。2017年の春に計画し、ホテルも、スーパービュー踊り子も、レンタカーも予約していたのだが、大雨の天気予報でキャンセル。2018年秋にも、同じ準備をしたのだが、天候が悪く中止となってしまっていた。今回(2019・5)の旅も、3泊3日の旅のうち、1.5日は雨の予報だったが決行、やっと達成できた。
旅の目的は、大きく言って、4つ。
・姉の句碑を、もう一度、城ケ崎の蓮着寺で見ておくこと
・7年間暮らした、伊豆高原の我が家のその後を見ておくこと
・僕のボランティアの原点、伊東・イタリアの国際交流モニュメントの確認
・IBM時代、10回以上も訪れたお客様研修の天城ホームステッドの訪問
天城ホームステッドは、天城山の中腹、812mの高さにあるから、雨だと霧が巻いてとても近づけたものではないから、天候は大切な条件だったのだ。
さて、1つ目
亡き姉、徳山暁美は、俳句に生涯傾倒し、晩年、女流作家としてちょっと有名になった俳人だった。作品は、牧羊社の「現代俳句女流シリーズ」、「紀の山」で発刊され、有名な、河野多希女が序文を書いている。そんな彼女の句碑が、伊東市・城ヶ崎海岸にある蓮着寺の庭の、つつじに囲まれた句碑群の中心にある。

<徳山暁美の句碑>
句は、「かの世にて 花の曼荼羅 描きたまえ」という、洋画家だった父への献歌だ。
親父にかわいがられた暁美の、天国にいるおやじへの、やさしい句だった。とてもいい句だと僕は思っている。全部で10個ほどある句碑たちは、蓮着寺の一角、つつじの群れの中に立っている。少し字がぼけているか、苔むしていないかと心配だったが、どっこい、暁美さんの字はやさしく美しく彫られていて、しかも彫が少し柔らかくなって、小雨の中に立っていた。久しぶりと、声をかけた。
この暁美には、僕はよく面倒を見てもらったと思っている。彼女が長津田のマンションで、心筋梗塞によると思われる孤独死の身元確認を僕がやって、葬式を仕切った。だから、僕がくたばるまでに、この句碑の安否は確認しておきたかったのだ。宿題がやっと終わった。
2つ目
横浜脱出の地として選んで、7年間住んだ伊豆高原の家の状況を知っておきたかった。本当は、オーストラリア・メルボルンへの移住を予定して、準備を進めていたのだが、最後になって、僕の心臓君の問題が発覚してヴィザ申請ができなくなった。

<城ケ崎海岸 大室山の溶岩が作り出した風景>
そこで、日本国内の移住先として決めたのが伊豆高原だった。後で述べる天城ホームステッドへの出張の際、伊東や城ケ崎を知っていたから、ここになったとも言える。仕事の関係で、東京へのアクセスが大切だったことが決め手だった。他には、仙台、四万十川、高知市、八ヶ岳東麓などが候補だったが、実際に行ってみての判断から、伊豆高原に決めた。

<15年ぶりの我が家>
ここでは、ミニチュア・シュナウザーのチェルト君を中心とした、楽しい日々があった。犬友達もたくさんできて、多くの脱都会派との交流ができていた。家は、僕が「Casa Verde」と名付けて、色も塗り替え、素敵な住処になった。海抜300mのベランダからは、伊豆の島々が見え、特に神津島が美しく見えた。ここは伊豆高原でも最も高い位置ある小さな住居だった。大室山の麓からちょっと下ったところにあった。思い出のあるカロライナ・ジャスミン、ブラジル原産のフィージョア、ここで知ったオガタマの木などを、横浜のサカタに探してもらって、家の庭と側の遊歩道に植えた。この植物たちはどうだろうかと気になっていた。
元気でいるのを確認できたのは、2階のベランダ迄育て、伸ばしたカロライナ・ジャスミンだけだった。年に2回咲く、素晴らしい香りの存在に救われてか、新しい家の持ち主にも、大切にされているらしく、ベランダに健在だった。オガタマは庭の中だから、貝塚いぶきの生け垣に阻まれて見えなかった。遊歩道に植えたフィージョワは、この15年の間に大きくなった、空木の林の中に埋没していた。残念。
伊豆高原近辺には、他にいろいろあったけれど、本当に見るに値する美術館は、二つ。その一つは、「伊豆ガラスと工芸美術館」だったが、今年の4月に閉館してしまった。あのたくさんの、アールヌーヴォーのガラスたちはどこに行ってしまったのか。見ることができなくて、とても残念。単品で散らからないで、まとまっていることを祈るだけだ。

<アールヌーボーのガラススタンド>
後の一つは、健在だった。確かに絵を見たと実感できる、一碧湖近くの「池田20世紀美術館」https://www.nichireki.co.jp/ikeda/?lang=en だ。ニチレキ(日瀝化学工業)の創始者、池田氏が個人的に集めた1400点もの絵と彫刻と、それを展示するためのデザインされた建物が、ヒューマニティをテーマとして存在している。ゆっくり見れば、半日はかかるだろう。ルノワール、マティス、ピカソ、シャガール、A.ウオーホール、ミロ、ダリなどの作品が物理的に近くで見られるようにデザインされた美術館だ。

<池田20世紀美術館>
久し振りだったから、美術館のインフォーメーションの女性と話してみた。ガラスの美術館も一碧湖美術館も閉館し寂しくなったから、頑張ってくれなくては…と声を掛けたら、頑張りますと戻ってきた。ここは今や、伊豆高原、いや伊東市が誇れる唯一の世界に通用する美術館だと思う。

<シャガール>
皆さんの旅行プランには、ぜひ加えてあげてください。その価値はあると確信します。
(あと2つの目的については、伊豆高原へ #2に続きます)