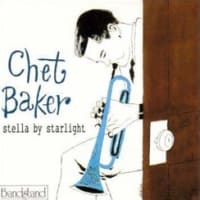スコット・ラファロが出てきたので彼の話をもうちょっと続けよう。
彼が一般から認められるようになったのは、この「The arrival of Victor Feldman」(58年)に参加した頃からだ。
彼は当時22才。もちろんビル・エヴァンスと組むようになる前の話だ。
ここでのラファロもすごい迫力で私たちを驚かせる。単にベースの音がでかいだけではない。常に大黒柱のような安定感・存在感でいっぱいなのだ。これくらい土台の音ががっしりしていると、主役のフェルドマンもさぞかし安心してヴァイヴにピアノに専念できただろう。
ビル・エヴァンスと組んだ時との違いは、脇役に徹していたことで彼自身がリラックスできていたことにあり、ベース奏者としての本領が発揮されていたような気がする。逆にエヴァンスと組んでいたときは、主役の一人として緊張感の中で演奏をしなければいけない状況にあって、その実験的な試みが人間としてのキャパを越えてしまっているような感じがするのだ。エヴァンスとは4作しか作品を残していないのでそれで良かったが、彼がその後も長生きしていたなら必ずその弊害が出ていたに違いない。
ともあれ6曲目の「BEBOP」を聴いてほしい。これくらい早いテンポを刻んでも彼のベースは全くひるまない。ひるまないどころか「こんなのお茶の子さいさい」といった感じがして、まるでデビュー当時のジャコ・パストリアスをも連想してしまう。まるで機械のようなその腕は、短時間で燃え尽きた人間だからこそ与えられたものなのかもしれない。