 ご訪問してくださり、ありがとうございます
ご訪問してくださり、ありがとうございます 

1985年に、結成された、ニュージーランド出身の、 Crowded House というバンドの、
’93年にリリースされた、アルバム 『 together alone 』 ( 『 お互いに 孤独 』 対訳より ) に、
収録されている、シングル 『 Distant Sun 』 という曲が、好きです

Crowded House は、 vocals / guitars の Neil Finn ( ニール ・ フィン ) 、
drums の Paul Hester ( ポール ・ へスター ) 、 bass の Nick Seymour ( ニック ・ シーモアー )
の3人によって、結成されました。
80年代の終わりに、 『 Don ' t Dream It ' s Over 』 という曲が、ヒットしたのを、思い出します。
とっても、懐かしいです ~

4作目になる、このアルバムでは、プロデューサーが、これまでの、ミッチェル ・ フルームから、
元キリング ・ ジョークのべーシスト、ユースに、変わり、 Keyboards に、 Mark Hart ( マーク ・ ハート ) 、
が、加入することになって、バンドにとって、変化が、生まれたようです。
ニール自身も、 「 すべてを変えよう 」 という気持ちになったそうで、
「 自分がどこから来たのか? 」 という、自身のルーツについて、関心を、抱いていたようです。
彼の出身地である、ニュージーランドの、東海岸にある、タスマニア海に、面した、
KARE ・ KARE ( カレ ・ カレ ) という、マオリの人々の住む地域で、マオリのアーティストと、共演したそうです

このアルバムは、そうした、自らのルーツ的な、音楽からの影響が、反映された、
大きな自然を、感じさせる、アルバムになっています

話は、戻りますが、わたしの好きな 『 Distant Sun 』 ( 『 遠く離れた太陽 』 対訳より )
という曲は、そのメロディの美しさ、とともに、
歌詞の素晴らしさが、とても、心に、響いてくるのです

『 Distant Sun 』
written by Neil Finn 対訳 : 松沢 みき さん
キミが変えたいと思うことを全て 僕に話してみてごらん
キミの望みを わかっているようなフリはしやしないさ
キミは僕のところにやって来ては
キリキリ舞いさせるのさ
休んでは また来て
休んでは また来て
僕を元気づけたのは 苦しみなんかじゃない
キミのキツい一言が 心を奪うような暗闇も恐くない
僕をもっと不幸にしてくれていいよ
僕をもっと不幸にしてくれていいよ
* だって 僕がキミの側にいる時はいつも
キミの7つの世界は 食い違ったままだから
そして 遠く離れた太陽から運ばれてくる宇宙のちりが
まんべんなく みんなに降り注ぐんだ
今までは 旅をするには余りにも若すぎた
自分が何者であるか 分かっていても
心の痛みを背負っていくだけの
十分な分別があったとしても
非難なくしては 誰も責められない
キミの学んだことなどは あっという間に忘れて当然
戻るためのスリルを待つこととか
炎に溺れてしまう時
自分の願望が輝くこととか
* くりかえし
僕はテーブルの上に横たわって
キリスト教徒が天からの復讐に怯えるように
洪水の中で疲れ切っているキミの望みを
わかっているようなフリはしやしないさ
でも 愛の告白だけはさせてもらうよ
* くりかえし
Crowded House - Distant Sun
Crowded House の ’93年のアルバム 『 together alone 』 からの、1st シングル 『 Distant Sun 』 の PV です。
crowded house distant sun live
1996年に、シドニーのオペラハウスで、行われた、 彼らの解散コンサート、 “ Farewell to the World ” コンサートより。
Sydney Children ' s Hospital のための、チャリティー ・ ライヴでもありました。
Crowded House - Glastonbury 2008 - Distant Sun
2007年に、再結成した Crowded House が、’08年に、グラストンベリー ・ フェスに、出演したときのライヴです。
聴いていて、とりはだが、立ちました
 ! Welcome coming back! Crowded House!!
! Welcome coming back! Crowded House!!( 動画が、消えていましたら、ごめんなさい
 )
)言うまでもなく、とても、素晴らしい歌ですね
 !
!これから先、時を経ても、きっと、人々の心に、残っていく歌だと思います

Neil Finn という人が、自身のルーツを、探しはじめたときに、そこで、出会った人々から、影響を受けて、
この歌が、生まれたのではないかと、歌詞の意味を知って、わたしなりに、思いました。
この歌に、出てくる “ seven worlds collide ” ( 「 7つの世界は 食い違ったまま 」 ) というフレーズが、
のちに、ある “ 動き ” となって、再び、私たちの前に、現われてくることになります

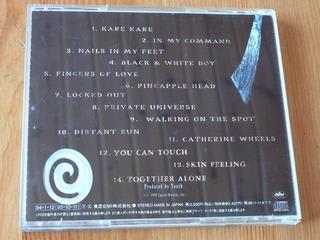
アルバム 『 together alone 』 の裏ジャケです。

 読んでくれて、ありがとうです
読んでくれて、ありがとうです 
ほいじゃ、また。。。
























 !!
!!








 動画が、消されてしまっていたら、ごめんなさい
動画が、消されてしまっていたら、ごめんなさい 
































 !!
!!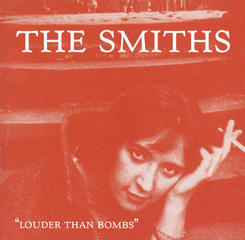




 意外と似合ってる
意外と似合ってる



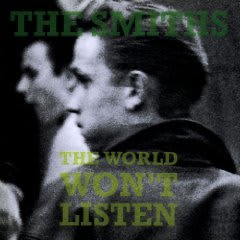

 !!
!!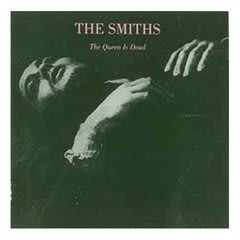
 !!
!!
