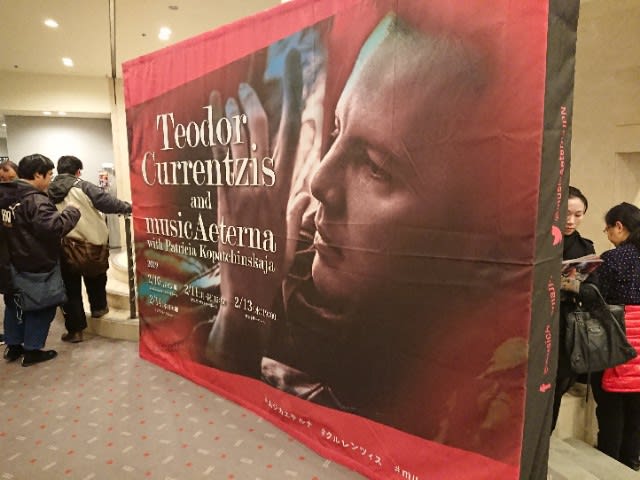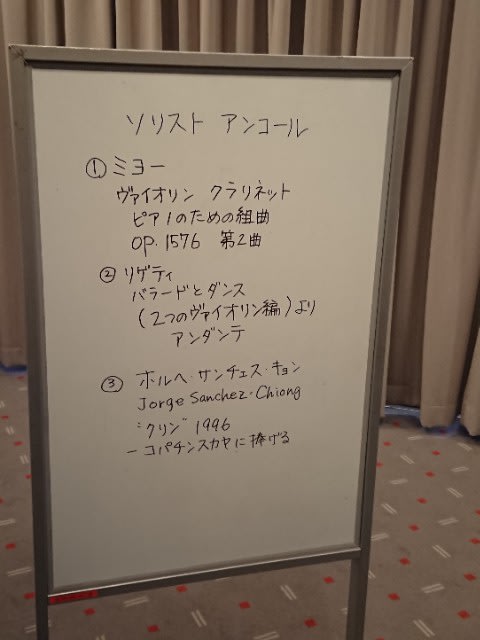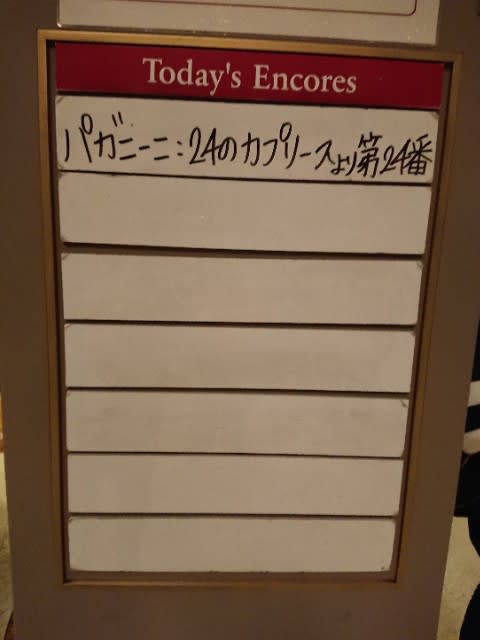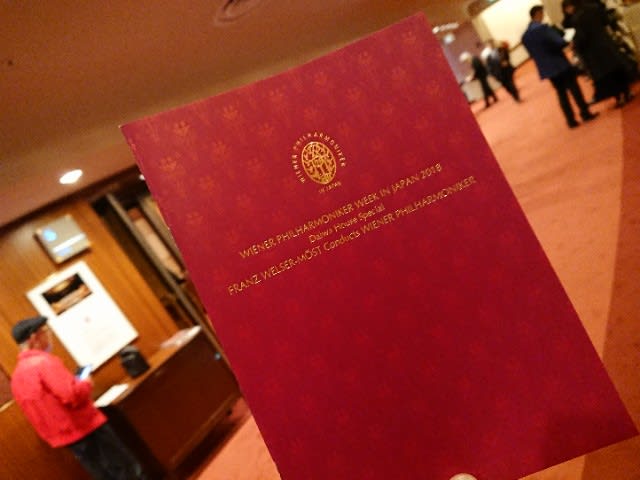拙ブログとおなじgooblogに執筆されているアントンK氏のアントンK「趣味の履歴簿」に嬉しい記事がありました。
「ああ、アントンKさんは、我々の演奏を深いところで理解されておられるのだな」というとが伝わってきて深い感慨に浸っている。関係者にはもちろん、当日、会場にいらっしゃれなかった方にも知って頂きたく、ここに紹介致します。
「今回の演奏では、指揮者福島章恭氏の懐の大きさを見たようで、さらにまた別の楽曲で聴いてみたいという気持ちになっている。あれほどまでに独自性が強く、自分の想いを具現化できる指揮者は、そうそういないと思われるからだ。前回鑑賞したモーツァルトの大ト短にしろ、今回のジークフリートにしろ、ある意味音楽がそそり立っており、これが孤灯の芸術美ということを示した演奏だったのだと思える。だからこそ聴衆は、彼のベートーヴェン、そしてブルックナーを心待ちにしているのだ。想像しただけでワクワクするではないか・・」
また、素敵なソプラノ独唱を披露してくださった平井香織さんは、Facebookにこのようなご感想を寄せてくださいました。
「ブラームス「ドイツ・レクイエム」終了しました。
私自身はいつもの事ながら反省しかありませんが💦極度の緊張に襲われた事に自分自身が驚いてしまいました😭
ゆったりと柔らかながら濃密な音楽を作り上げるマエストロの的確な指揮ぶり。
崔さん率いる✨奇跡のオーケストラ✨
何がどう素晴らしかったか語るのも無粋なくらい⁉️…素晴らしいメンバー(しかいない!)
全国からこの曲を演奏する為に集まった合唱団。
徹底した発声と音楽作りでこの大曲に果敢に立ち向かい、フォルテでも決して叫ばず丁寧に丁寧に歌われていました👏
バリトンソロの与那城君、オペラ「金閣寺」が終わったばかりなのに疲れも見せず安定の歌唱。流石です。
お世話になった皆さま、ご来場の皆さま、ありがとうございました。」
また、池田卓夫さんのブログ:iketakuhonpoにも、”福島章恭の静謐な祈り、「独逸鎮魂曲」”という有り難い記事があるのですが、わたしのやり方が拙いのか、うまくリンクが貼れません。
興味のある方は、池田卓夫さんのお名前で検索してみてください。
どうぞ、宜しくお願いします。