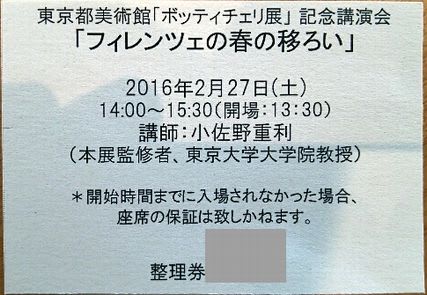前日の雨&激寒がウソのような、
晴天&小春日和の昨日の土曜日(2016/11/12)。
上野の東京都美術館で行われる、
ゴッホとゴーギャン展講演会に行ってきました。
13:00に聴講券配布ですが、
12:40頃に到着した所、既に結構な行列が形成。
最近、ここ東京都美術館も、近くの国立西洋美術館も、
こう言う展覧会記念講演会は盛況なんですよね。
以前は聴講券の入手がもう少し簡単だった気がするんですが、
近頃は、あんまり配布時間ギリギリに行くと、
聴講券を入手し損ねる懸念が。
今日も、開場時刻の13:30までには、聴講券が全て捌けていました。
14:00になって、開演。
今日の講師は、一橋大学大学院准教授の小泉順也さん。
タイトルは、『ゴッホとゴーギャン―イメージの反復と転用』
内容ですが、
こんな感じですかね。
中々面白かったです。
わかり易く解説してもらえましたしね。
ゆっくり話していたので、どうなるのかと思いましたが、
キッチリと時間通りに終了しました。
素晴らしい!
晴天&小春日和の昨日の土曜日(2016/11/12)。
上野の東京都美術館で行われる、
ゴッホとゴーギャン展講演会に行ってきました。
13:00に聴講券配布ですが、
12:40頃に到着した所、既に結構な行列が形成。
最近、ここ東京都美術館も、近くの国立西洋美術館も、
こう言う展覧会記念講演会は盛況なんですよね。
以前は聴講券の入手がもう少し簡単だった気がするんですが、
近頃は、あんまり配布時間ギリギリに行くと、
聴講券を入手し損ねる懸念が。
今日も、開場時刻の13:30までには、聴講券が全て捌けていました。
14:00になって、開演。
今日の講師は、一橋大学大学院准教授の小泉順也さん。
タイトルは、『ゴッホとゴーギャン―イメージの反復と転用』
内容ですが、
- ゴッホは書簡が多く残されていて、書簡に述べられている作品はかなり時期を同定することができる
- 《自画像》(1886年9~11月/ファン・ゴッホ美術館)と《自画像》(1887年9~10月/ファン・ゴッホ美術館)は、ゴッホがオランダからパリに出てきたあたりの作品であって、フランスの影響を見て取ることができる。
- グービル商会と言う所に勤務したときにイギリスに行っている。(ゴッホがイギリスに赴いたことがあるのは知りませんでした。今回勉強になった)
- ゴーギャンの《自画像》(1885年/キンベル美術館)はコペンハーゲンで描かれているが、絵の雰囲気は必ずしも明るくない。陰鬱な雰囲気を感じる。丁度ゴーギャンが、妻の実家で過ごしていた頃に描かれたものであって、その影響と思われる。
- ゴッホがオランダ・イギリス・フランスと比較的狭い範囲にしか行ったことが無いのと異なり、ゴーギャンは世界中に足を伸ばしている。ゴーギャンは、幼い頃にはペルーで過ごした事もある。1888年10月にゴッホとゴーギャンが共同生活を始めるが、この様に、そこまで二人が見ていた世界はかなり違う。そう言う背景から、二人の共同生活地のアルルは、ゴッホに取って理想郷に近かったかもしれないが、ゴーギャンに取っては通過点に過ぎなかったのではないか。
- ゴーギャンの《自画像》(1893年頃/デトロイト美術館)。これは、《ドラクロワのエスキスのある静物画》(1887年頃/ストラスブール美術館)の構図に似ている。さらにこれの元ネタとしてドラクロワの《アダムとイブ》(1838~47年/国民議会図書館)がある。
- また、《偶像のある自画像》(1893年頃/マクネイ美術館)は、《自画像》(1893年頃/デトロイト美術館)の構図を反復している。
- こう言う反復は他にもあり、トレマロ礼拝堂にキリスト像の磔像があるが、ゴーギャンの《黄色いキリスト》(1889年/オルブライト=ノックス美術館)には、その磔像が描きこまれている。さらに、《黄色いキリストのある自画像》(1890~91年/オルセー美術館)では、その《黄色いキリスト》を描き込んでいる。加えて、《黄色いキリストのある自画像》では、ゴーギャン自ら作った焼き物も描き込まれている
- こう言うように、絵画のみならず彫刻、焼き物、様々なバラエティに富む作品を作っているゴーギャンは、はたして画家か?と言う事を考えることが有る。こう言うバラエティに富んでいることが、ゴーギャンの本質。
- ゴッホに取っての反復は、ゴーギャンと違う。
- フランス語の反復を示す言葉には、模写・写し、反復・繰り返し・模写、解釈、複製など色々ある
- ゴッホの《種をまく人》(ミレーによる)(1890年1月/クレラー=ミュラー美術館)は、ミレーの《種をまく人》(1850年/ボストン美術館)の模写であるが、これは実は、ポール=エドメ・ルラの複製版画《種をまく人》(ミレーによる)(1873年、エッチング/ファン・ゴッホ美術館)を見て描いている。ミレー自身の《種をまく人》は、描かれて直ぐにボストン美術館に収蔵されていて、ゴッホは実物を見ていない。
- ゴッホは、数多くのミレーの模写をしている。彼の中に何かテーマがあり、繰り返し描いていたのではないか。ゴッホが繰り返し描いたテーマは、25ほどある。ゴーギャンの場合は、そういう感じではなく、モチーフをどこかから取り出してくる感じ。
- しかし、繰り返し繰り返し描くと言っても、色々展開することもある。《種をまく人》(1888年6月/クレラー=ミュラー美術館)と《夕陽と種をまく人》(1888年11月/ビュールレ・コレクション財団)がその例。ゴーギャンの《説教の中の幻影(天使と闘うヤコブ)》(1888年9月頃/スコットランド国立美術館)が、《夕陽と種をまく人》へ刺激になった?
- ゴーギャンの作画は、必ずしも見て描いているわけではない。《ブドウの収穫、人間の悲惨》(1888年/オードルップゴー美術館)についてゴッホはテオへの書簡で「描かれている女性は、ゴーギャンの頭の中で作られたものである」と指摘している。
- ゴッホも同じ頃《赤いブドウ畑》(1888年11月頃/プーシキン美術館)や《エッテンの思い出》 (1888年11月/プーシキン美術館)を、当時の事を思い出しながら描いている。これはゴーギャンの影響を受けたゴッホが、これまでに無い描き方をしている作品
- ゴーギャンが描いた《腰掛け椅子のひまわり》(1901年/ビュールレ・コレクション財団)は、当時タヒチに居たゴーギャンが、アルルの頃を思い出して描いている作品だが、似たモチーフの《花束にするために》(1880年/個人蔵)と言う作品も同時期に描いているので、《腰掛け椅子のひまわり》はゴッホとの思い出だけを描いている訳でも無い
- ゴッホの《夜のカフェ》(1888年/イェール大学美術館)。これと似た作品にゴーギャンの《アルルの夜のカフェにて(ジヌー夫人)》(1888年11月/プーシキン美術館)がある。このゴーギャンの《アルルの夜のカフェにて(ジヌー夫人)》に描かれた女性を、ゴッホが《アルルの女(ジヌー夫人)》とし抜き出して何点もゴッホが描いている。ゴッホは、この《アルルの女(ジヌー夫人)》4作品描いていて、うちひとつを、ゴッホはゴーギャンに贈っている。
- 最後にシニャックについて。シニャックは、アルルのゴッホを訪ねている。その後シニャック最晩年に再びアルルを訪れ、《アルル、ファン・ゴッホの家》(1935年、水彩/個人蔵)を描いている。この作品に描かれたファン・ゴッホの家の実物は、後の戦争で失われた。
こんな感じですかね。
中々面白かったです。
わかり易く解説してもらえましたしね。
ゆっくり話していたので、どうなるのかと思いましたが、
キッチリと時間通りに終了しました。
素晴らしい!