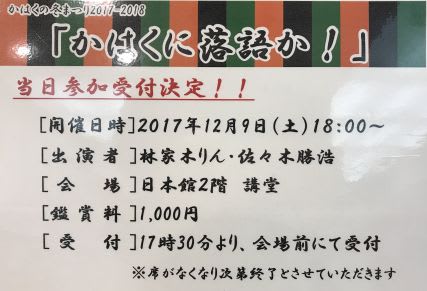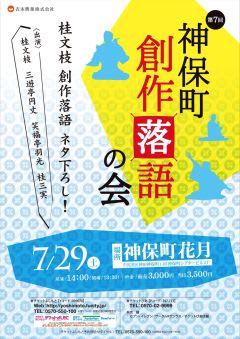いつの頃からか、落語に興味を持ち始めました。
コロナ禍になってから、
落語会とかに行けなくなっていたんですが、
コロナ禍3年目の新春に、
まだコロナ禍は治まっていないのですが、
桂文枝の新春特撰落語会に行ってきました。
今日、落語を披露したのは、桂貴文、桂三度、
桂三四郎、そして、桂文枝の4人。
前半は、桂貴文、桂三度、桂文枝の三席。
桂貴文はさておき、桂三度は、嘗て、
“世界のナベアツ”で一世を風靡した芸人。
数字ネタだったので、その頃のネタも、
落語に入れてくるかともいましたが、
入ってきませんでしたね。
入れてきても良かったのではないかと思いましたが、
敢えての封印なんですかね。
前半最後に、桂文枝が登場して「文句の叫び」。
まぁ、何というか、夫婦が(というか、主に
妻の方ですけど)文句を言う事の落語です。
シャレにならんですwww
ここで15分休憩のあとに後半に入ります。
後半は、桂三四郎と桂文枝の二席。
桂三四郎は、時々テレビでも見かける人なので、
知っていましたが、流石に後半に出てくるだけあって、
面白かったですね。
もしかしたら、今日いちばん客席を沸かせていたかも。
若いのでテンポもいいし、話のネタも面白かったです。
今日いちばんの収穫ですね。
そして最後のトリに、再び桂文枝。
二席目は「芸者ちどり・24才」。
芸者の話なんですが、結構面白かったです。
でもね、桂文枝も今年で80歳なのだそうですが、
ちょっと活舌が悪くなり始めていますね。残念。
もう少し活舌が良ければ、もっと面白かったかな。
実は、コロナ禍直前にも桂文枝の新春特撰落語会に
行ったことがあるんですが、その時は、
もっと活舌が良かった気がするんですけどねぇ。
コロナ禍になってから、
落語会とかに行けなくなっていたんですが、
コロナ禍3年目の新春に、
まだコロナ禍は治まっていないのですが、
桂文枝の新春特撰落語会に行ってきました。
今日、落語を披露したのは、桂貴文、桂三度、
桂三四郎、そして、桂文枝の4人。
前半は、桂貴文、桂三度、桂文枝の三席。
桂貴文はさておき、桂三度は、嘗て、
“世界のナベアツ”で一世を風靡した芸人。
数字ネタだったので、その頃のネタも、
落語に入れてくるかともいましたが、
入ってきませんでしたね。
入れてきても良かったのではないかと思いましたが、
敢えての封印なんですかね。
前半最後に、桂文枝が登場して「文句の叫び」。
まぁ、何というか、夫婦が(というか、主に
妻の方ですけど)文句を言う事の落語です。
シャレにならんですwww
ここで15分休憩のあとに後半に入ります。
後半は、桂三四郎と桂文枝の二席。
桂三四郎は、時々テレビでも見かける人なので、
知っていましたが、流石に後半に出てくるだけあって、
面白かったですね。
もしかしたら、今日いちばん客席を沸かせていたかも。
若いのでテンポもいいし、話のネタも面白かったです。
今日いちばんの収穫ですね。
そして最後のトリに、再び桂文枝。
二席目は「芸者ちどり・24才」。
芸者の話なんですが、結構面白かったです。
でもね、桂文枝も今年で80歳なのだそうですが、
ちょっと活舌が悪くなり始めていますね。残念。
もう少し活舌が良ければ、もっと面白かったかな。
実は、コロナ禍直前にも桂文枝の新春特撰落語会に
行ったことがあるんですが、その時は、
もっと活舌が良かった気がするんですけどねぇ。