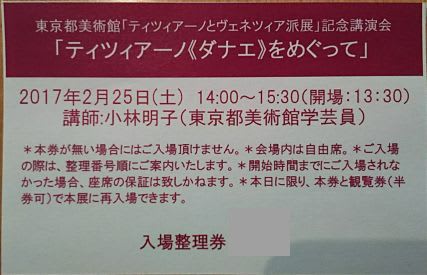スッキリしない空模様の日曜日。
めっちゃ蒸し暑いですが、
東京都美術館で「ボストン美術館の至宝展記念講演会」
があったので、行って来ました。
1300時に講演会整理券の配布開始ですが、
1230時頃に、配布場所に到着。
最終的にはまぁまぁの行列になっていましたが、
満席までにはならなかった様です。
今日の講師は、神戸市立博物館学芸員の石沢俊さんで、
講演タイトルは、
「コレクターとコレクション―ボストン美術館の日本・中国美術」
この『ボストン美術館の至宝展』は、
東京都美術館・神戸市立博物館・名古屋ボストン美術館と
巡回する展覧会なのですが、各美術館・博物館で分担して、
展覧会のテーマの中身を企画したそうです。
今回講師の石沢さんが所属する神戸市立博物館が、
日本・中国美術を担当したので、今回の講演となったそうです。
ちなみに、東京都美術館は、西洋美術を担当。
それぞれ、得意の分野と言うのがあるんですね。
さて、講演の中身は以下の感じ。
こんな感じでしょうか。
うまくテーマを区切って講演されていたので、非常にわかりやすかったです。
めっちゃ蒸し暑いですが、
東京都美術館で「ボストン美術館の至宝展記念講演会」
があったので、行って来ました。
1300時に講演会整理券の配布開始ですが、
1230時頃に、配布場所に到着。
最終的にはまぁまぁの行列になっていましたが、
満席までにはならなかった様です。
今日の講師は、神戸市立博物館学芸員の石沢俊さんで、
講演タイトルは、
「コレクターとコレクション―ボストン美術館の日本・中国美術」
この『ボストン美術館の至宝展』は、
東京都美術館・神戸市立博物館・名古屋ボストン美術館と
巡回する展覧会なのですが、各美術館・博物館で分担して、
展覧会のテーマの中身を企画したそうです。
今回講師の石沢さんが所属する神戸市立博物館が、
日本・中国美術を担当したので、今回の講演となったそうです。
ちなみに、東京都美術館は、西洋美術を担当。
それぞれ、得意の分野と言うのがあるんですね。
さて、講演の中身は以下の感じ。
- 今回の『ボストン美術館の至宝展』は、コレクション、コレクターと言う観点で展覧会を構成
- ボストンに関連する美術コレクターなどのボストニアン、ボストン市民に支えられていると言うところに、ボストン美術館の特徴がある
- 今回の展覧会に際しては、三年ほど前にボストン美術館を現地調査。今やっと展覧会の開始となった。
モースについて
- いわゆるお雇い外国人で、元々は貝の専門家。大森貝塚の発見者としても有名。
- モースは、帰国後、日本文化についての講演を行うが、その講演が、フェノロサやビゲローなどボストニアン来日のきっかけとなる
- ボストン美術館のコレクションには、必ず誰のコレクションかわかる様にキャプションを入れるのが特徴。それだけボストニアンを大事にしていると言う事
フェノロサとウェルドについて
- モースの推薦でフェノロサは来日
- ビゲローの保証と斡旋で、フェノロサは自身のコレクション売却契約をウェルドと締結。フェノロサ=ウェルド・コレクションとしてボストン美術館の寄託となる。その際、フェノロサはボストンから出さない様にとの条件を付けた。しばらくは、寄託と言う扱いだったが、1911年にボストン美術館に所有権が移り、今に至る
- 曾我蕭白の《風仙図屏風》。描かれているのは"陳楠"と呼ばれる仙人。蕭白37才くらいの作品。蕭白の作品は40数点あるが、欧米ではアクセッションナンバーで作品を管理する。右隻左隻それぞれに付けるので、アクセッションナンバーとしては2つになるので、アクセッションナンバー的には50幾つになっている
- 喜多川歌麿の《三味線を弾く美人図》。歌麿の肉筆画は53点が確認されているが、そのうちの一つ。美人の視線の先に5人の狂歌が書かれている。
- 英一蝶の《月次風俗図屏風》。
ビゲローについて
- 元々は外科医。実家は裕福で、それを元手に日本の古美術を収集
- 曾我蕭白の《飲中八仙図》。画中画としてお釈迦様が描かれている。飲酒と言う世俗的な行いと、お釈迦様の姿を対比させようとしたのか?実は、今回の出展に際して修理が行われた
中国美術コレクションの補完、拡充について
- フェノロサと五百羅漢図。1894年『大徳寺五百羅漢図展』が行われ、100幅のうち44幅を展示していて、そのうち10幅がボストン美術館に収蔵される。これは、廃仏棄釈によって荒廃した大徳寺の修理費用捻出のためとされている。ボストン美術館収蔵の10幅のうち5幅は通常の購入予算で購入されているが、残り5幅は寄付金で購入されていて門外不出になっている。肉眼では判らないが、金泥で中国からの由来が書かれている。
- 岡倉覚三(天心)と中国日本特別基金。欧米の美術館なので欧米のキュレーターであるべきと言う岡倉の考えで、ボストン美術館では嘱託の職にしか就かなかった。岡倉は、理事会にコレクション充実のための基金設立を訴え、理事会は寄附金で1905年基金設立。その後、その資金で中国日本の美術品の充実が図られた
- カーティスと九龍図巻。カーティス没後、基金が設立され、その基金で九龍図巻が購入される。金額に換算することはできないが、近年購入された六龍図巻は60億とも言われていて、九龍の本作品は・・・(笑)
幻の巨大涅槃図について
- 英一蝶の《涅槃図》は、構図などから、命尊の《仏涅槃図》の系列と見られている
- 英一蝶の《涅槃図》には、51種類の動物が書かれている。描かれた当時は、ヒョウはトラのメスと言う認識だったので、トラとヒョウでつがいとして書かれている
- この涅槃図の墨書には、嘉永3年に納められたと書かれているが、納められた先の吟窓院の所蔵目録には、嘉永2年の所蔵と書かれている。このずれは謎であるが、嘉永2年に大火があり吟窓院では色々燃えてしまった様である。檀家の古筆家が、吟窓院の復興を祈念してこの作品を納めているが、一先ず、嘉永2年の段階で吟窓院に納めることとし、実際に所蔵されたのは嘉永3年だったのか?
コレクターとコレクション
- 松村景文・岡本豊彦・東東洋の《松に鹿蝙蝠図屏風》と岸駒・呉春・東東洋の《梅に鹿鶴図屏風》は左隻右隻のペアの作品だが、《松に鹿蝙蝠図屏風》はフェノロサ=ウェルド・コレクション、《梅に鹿鶴図屏風》はウィリアム・スタージェス・ビゲロー・コレクションとコレクターが違っている。最終的にはボストン美術館に納められると言う事が念頭に、コレクターはコレクションしていたと言う事を示しているのか?
こんな感じでしょうか。
うまくテーマを区切って講演されていたので、非常にわかりやすかったです。