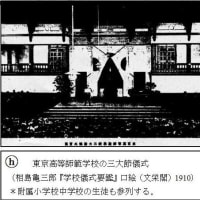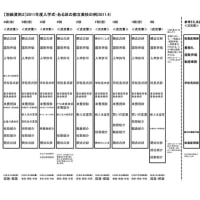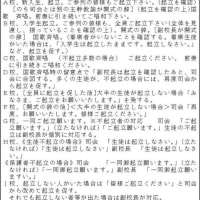◎「柳田國男とわたくし」(本山桂川)
最近になって、インターネット上で、小泉みち子氏の「研究ノート 本山桂川―その生涯と書誌」という論文に接した。これは、非常な労作であって、今後、本山桂川について何か語ろうとするものは、必ず、この小泉氏の研究を踏まえなければなるまい。
私はかつて、本山桂川編集の雑誌『土の鈴』(長崎市・土の鈴会)を何冊か入手したことがある。このブログで、その内容の一部を紹介したこともあった。しかし私は、今回、小泉氏の論文を読むまで、この雑誌が第一九輯まで(一九二〇年六月「第一輯」~一九二三年六月「第一九輯」)、計十九冊が発行されていたという基本的な事実すら知らなかった。また、本山の死後、数年たった一九七九年(昭和五四)一二月に、村田書店から、『土の鈴』の全冊が復刻されていた事実も知らなかった
先日、図書館で、『土の鈴』復刻版を閲覧してみた。すると、この復刻版には、全十九冊のほかに、復刻に際して編集された「別冊」というものが付いていた。別冊には、本山桂川の文章が三つ収録されている。「『土の鈴』について」、「柳田國男とわたくし」、そして「コレクト・メニア」〔collect mania〕である。いずれも、初出に関するデータは、記載されていなかった。あるいは、未発表だった文章を、ここに収録したものか。
この三つの文章のうち、今日読んで、最も興味深いのは、「柳田國男とわたくし」である。本日は、これを紹介してみよう。
柳田國男氏とわたくし
人との挨拶の中で、民俗学を研究している旨を告げると、「それでは、あの柳田さんの……」と誰もいう。そしてわれわれまでが皆、その門下生であるかのような認定を示すのである。民俗の研究に指を染めるようになったのは、初期の民俗学徒が誰も皆そうであったように、民間の勝手な学問として勝手な方向に進んで行ったに過ぎない。もとより柳田氏に直接相接し〈アイセッシ〉、また、その数々の著書を読んでいれば多少となくその言動に左右され、或は自著に引用するようなことは有り勝〈アリガチ〉だが、門下生と目される程の影響は受けていない。表面師事するが如きくちぶりを筆にする折口信夫氏や中山太郎君にしても、口では門下生扱いに世間から見られることを露骨にきらっていた。
柳田氏と文通をするようになったのは、誰の紹介によるものでもなく、はっきりは記憶にないが、多分長崎で「土の鈴」を発行して、それを寄贈して以来のことと思う。この「土の鈴」は、地方における郷土民俗の刊行誌として甚だ古いスタートを持ったもので、当時中央には柳田氏の主宰する「郷土研究」〔郷土研究社、一九一三~一九三三〕があり、地方には京都の「郷土趣味」〔郷土趣味社、一九一八~一九二五〕とこの長崎の「土の鈴」があったのみだ。故南方熊楠〈ミナカタ・クマグス〉翁と文通するようになったのも「土の鈴」がとりもつ縁であった。佐々木喜善〈キゼン〉君との交友もまたそうであった。(後年、神田の坂本〔書店〕から閑話叢書の一つとして南方熊楠翁の「南方閑話」〔一九二六〕、佐々木喜善君の「東奥異聞〈トウオウイブン〉」〔一九二六〕を出したのもそうした関係からである。)
その頃大正十年か十一年の頃〔正しくは、大正一〇年=一九二一年二月〕、柳田氏が琉球に行った帰途長崎に来られた時、これを迎えて商工会議所や県庁で講演をしてもらった事が二人の文通を一層密にした。
その時の会議所での講演が「家船〈エブネ〉の話」で、速記をとったが速記の翻訳が甚だ不完全であったため、それを柳田氏に送って訂正して貰うことを依頼した。その後、柳田氏はジュネーヴに行かれその原稿も持って行かれたと聞いたが、今日に至るまで返戻〈ヘンレイ〉されず、家船に関する限り今以って柳田氏の発表がない。
わたくしが琉球の旅をした頃、柳田氏は外国から帰られ、長崎を飛び出して以来の自分の行動の突飛さに驚いたという意味の手紙を那覇の旅宿で受取った。
琉球の旅から帰り、市川〔千葉県東葛飾郡市川町〕に居住してからは折にふれて牛込〔東京市牛込区加賀町〕の柳田氏邸を訪れた。早川孝太郎君、宮本勢助〈セイスケ〉君、今和次郎〈コン・ワジロウ〉君等と相知ったのもその頃のことだと思う。閑話叢書の一冊に「家船説話」の一冊を予定していたのもその頃のことだった。それもついに物にはならなかったが、「南島情趣」〔聚英閣、一九二五〕や「与那国島図誌」〔郷土研究社、一九二五〕を刊行したのは柳田氏の紹介と推薦によるものであった。市川で職を失った時〔一九二五年=大正一四年三月、私立市川学館を退職〕、相談に行ったら「決してポジションハンターにはならないように」といわれた一言は今もよく肝に銘じている。
佐々木喜善君が遠野在の土渕〈ツチブチ〉村長に失脚して仙台に移住する前、遠野町の鈴木重男氏宅を訪れ、佐々木君や、土地の伊能〔嘉矩〈カノリ〉〕氏、釜石の山本銘次郎氏〔ママ。正しくは、「山本茗次郎」〕等と一夕〈イッセキ〉の会談をし、席上たまたま佐々木君のところに寄寓していた竹隈というアイヌ人〔ママ。正しくは「武隈徳三郎」〕に会ったのは何時の年であったろうか。【以下、次回】
文中、「商工会議所や県庁で講演をしてもらった」とあるが、柳田は、一九二一年(大正一〇)二月二三日、長崎市商工会議所で「家船やシャアの話」をし、翌二四日に、長崎県議事堂で、「国語研究の要、沖縄語のこと」を講演している(柳田國男「年譜」による。『定本柳田國男集』別巻第五、筑摩書房、一九七一)。
「竹隈というアイヌ人」とあるのは誤記で、正しくは武隈徳三郎〈タケクマ・トクサブロウ〉である。武隈には、『アイヌ物語』(富貴堂書店、一九一八)という著書がある。なお、本山桂川が、遠野町の鈴木重男宅で、佐々木喜善・伊能嘉矩・山本茗次郎・武隈徳三郎らと、あい会したのは、一九二四年(大正一三)四月のことであった(典拠は後述)。