◎内田百間と「漱石全集校正文法」
たまたま、『送り仮名法資料集』〔国立国語研究所資料集3〕(秀英出版、一九五二)という本を見ていたところ、そこに、内田百間の「送り仮名論」が載っていることに気づいた。
タイトルは、「動詞の不変化語尾について」で、雑誌『東炎』の一九三五年(昭和一〇)に掲載されたものだという。
論旨は、送り仮名は、動詞の不変化語尾も含めるべきだ(「尽す」でなく「尽くす」)というものであるが、その部分の紹介は省き、「漱石全集校正文法」や「ゲーテ全集文典」に言及している末尾の部分を紹介してみよう。
大正六年〔一九一七〕、漱石全集第一版が岩波書店から刊行せられた時、私は同門の二三君と共にその校正にあたつた。
これより先数年、先生〔夏目漱石〕のまだ在世せられた当時、既に、先生の新著及びその頃盛に翻刻された縮刷版の校正にあたつて、私の手にかけた数は、恐らく十冊に近かつたらうと思ふ。
校正をする際、一ばん苦しんだのは、語尾の取扱ひ方であつた。校正は原作者の原稿通りにするのが本当である。
しかし、新著の場合でも、その時原稿として与へられるのは、新聞の切抜である。新聞のルビ附活字で都合よく植ゑられた語尾は、全然信用する事は出来ない。ルビ附活字は初めから附いてゐるルビを語幹として、その余りを勝手に語尾に出すのである。原作者の原文の語尾とは何の関係もない。
翻刻の縮刷版の校正の時は、なほ更である。
さうして、先生はさう云ふ問題には、割合に無頓著〈ムトンチャク〉であつた。勢ひこちらで、何かの機会に、得られた材料によつて、例へば、新聞の切抜に書き入れをしてゐられる先生の文章とか、書きつぶしの原稿の文章とかによつて、先生の文章癖を観察する外はなかつた。
さう云ふ観察によつて知り得た先生の癖は、大体
聞える
恐ろしい
と云ふ風な書き方であつた。
この「と」や「ろ」を見つめてゐる内に、又度度〈タビタビ〉手にかけて、語尾として校正する間に不変化語尾と云ふ事を考へ始めた。
先生の死後刊行せられた漱石全集の校正の際には、先生の原稿を見る事が出来たのも二三篇あつた。それは新聞社の内部の人が、毎日連載された小読の原稿を、丹念に保存しておいたのが手に入つたのである。
しかし、それは勿論全集全体の一部分に過ぎないいので、大部分は単行本又は切抜を原稿として校正しなければならなかつた。
その通りにやりさへすればいいと云ふ本人の原稿がなくて、漱石全集の様な大部分物の校正をするには、何等かの拠りどころなり、方針なりが確立してゐなければ、出来るものではない。
その方針が国定教科書に採用せられてゐる文部省制定の送仮名法ですめば、一ばん簡単であるけれども、その文法は先生の文章を律するに全然不適当である事は、一緒に仕事をするみんなの意見であつた。
それで、これから実際の仕事にあたる者が、相談協議の結果、行文上の先生の用字癖、慣用の送り仮名等を基礎にして、一つの「校正文法」を作らうと云ふ事になつた。
みんなの協力によつて、半紙四五十枚の原案が出来上がつた。それを私が纏めて謄写版に書き上げた。「漱石全集校正文法」と云ふ表紙を著けて〈ツケテ〉、本の様な形にした。その中で、不変化語尾を初めて明確に取り扱つた。
その「校正文法」は、私の手許に近年まで、まだ幾冊も残つてゐたのだけれど、転転と居を移す内に、何時の間にか無くなつてしまった。それが今手許にあれば、本稿を草するにも、もつと用例を豊富にする事が出来たのに残念である。
大正十三年、大村書店からゲーテ全集が刊行せられる際、私はその発案者の一人として編纂にたづさはり、再び校正 文法の起草にあたった。その本は幸ひ見つかつたので、本稿の用例は主として、その中から摘用した。
凡例十項のうち、初めの三項に次の如く記してゐる。「一、ゲーテ全集文典は全集翻訳者の備忘に資する為、主として語尾の取扱ひ方を規定す。二、規定は文学上の作品に慣用せらるる一般の用例に従ひ、これに起草者の私見を加へて統一せり。三、不変化語尾の取扱ひ方に関しては文部省編纂国定教科書の文法と拠る所を異にす」
ゲーテ全集文典の起草によつて、私は不変化語尾に関する所見を、一応明らかにした様である。
爾後十年私は大体自分の建てた方針を、自分の文典として文を行つてゐる。特に最近の一両年、筆研に親しむ事か多くなつてからは、実際その場合にあたつて、不変化語尾は全部必す送り仮名として、扱はなければならぬと痛感する事が多いので、この稿を草して大方の叱正を仰ぎたいと思ふのである。
附言。活用と変化との両語を同意義に混用せり。
引用せるは、大正十五年〔一九二六〕二月、国定教科書共同販売所発行文部省内国語調査委員会編纂、第二十版翻刻版「送仮名法」なり。


















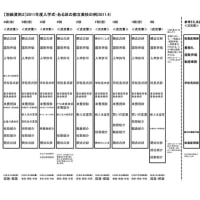
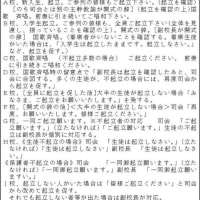








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます