◎岩波茂雄、野尻湖上の弁天島にこもる
昨日の続きである。昨日は、山崎安雄著『岩波茂雄』(時事通信社、一九六一)の第二章「東都への遊学」から、「藤村操の投瀑」という節を紹介した。本日は、それに続く「涙の野尻湖」の節を紹介する。ただし、本日は、その前半のみ。
涙 の 野 尻 湖
岩波〔茂雄〕のこもったのは弁天島という野尻湖上の一孤島で、横が一町〔約一〇九メートル〕、縦が二町ほどもあって、琵琶の形をしているところから琵琶島ともいわれていた。湖はあくまで清澄の水をたたえて美しく、見渡せば飯綱〈イイヅナ〉、黒姫、妙高の山々が湖のほとりから裾野をひいて聳え立っている。わけても妙高は最も高く、その雄姿はいうべき言葉を知らなかった。
島は老杉をもって蔽われ、その奥深いところに作物の神を祀る神社があった。土地の先覚者(池田万作)の語るところによると、明治十四、五年〔一八八一、一八八二〕ごろこの神社はなかなか栄えたもので、野尻からこの島まで二間幅の橋が架り、人力車なども通って参詣人の絶え間がなかった。
その橋も明治二十二年〔一八八九〕にこわれたまま修復するものもなく、さびれる一方になってしまった。
もと天台の僧(雲井某)が住んでいたという拝殿の右側の荒れはてた板の間に、岩波は蓆〈ムシロ〉を敷いて仮りの宿りとした。ここから毎日、湖に下りて米をとぎ、自炊生活をしたのである。野菜などは、かれが「牧童【ヒルテンクナーベ】と呼んだ少年(石田才吉)が対岸のから運んでくれた。それ以外に村との連絡はまれに参詣人が舟を雇ってきた時だけである。
社殿から舟のつく鳥居のところまで二町ほどある。一日の生活といえばこの短い道を二往復するだけ。終日、本を読むでもなく、何をするでもなく、鳥の声をきいたり(鶯や時鳥〈ホトトギス〉や郭公〈カッコウ〉などがよく鳴いた)、雲の峰を眺めたりしていた。特に印象に残っているのは月の夜、霧の中から横笛の音のもれてきたことで、あの時はまるで夢の国にでも遊んでいるような思いにかられた。また静かなもの音一つしない夜、鯉が突如として湖面をたたくのなども忘れられない、と岩波は回想している。
「黒姫は誰を待つらん薄化粧」とは土地の女学生がよんだ黒姫の初雪の姿であるが、紺碧〈コンペキ〉の空を流れる白雲の千変万化といい、山肌の色のきのうにかわる姿など、見ていれば飽きることがない。とはいえ「空洞の生活ではなく充実した生活であった」と岩波はいう。かれの筆によれば、
《……赤子が母の腕にねむるが如き、自然の懐に抱かれた安らけき生活であった。自然を友とするとか、自然に同化するとかいう言葉があるが、最も自然に接近し、天地の心にふれた生活であった。自然は何時でも何処でも限りなく慰みを与えてくれ、決して愛する者の心に背くことはない。古人は「天地の悠々を思い愴然として涙下る」といったが、私は左千夫の「寂しさの極みにたえて天地〈アメツチ〉に寄する命をつくづくと思う」の歌を口ずさんで涙ぐむ心を、うれしくも有難くも思う。(「思い出の野尻湖」)》
そうはいうものの、この島に初めて来た当座は、さびしくて身のおき場もなかった。そして親しいたれかれの名を呼んだ。いくら呼んだとて、なんの反応もあればこそ、迫るは漆黒の闇ばかり。それはさながら死を暗示するもののごとくであった。さびしさを求めてこの島に来ながら、友の名を呼び、生を厭うて死場所をここに求めながら、死の恐怖に身がふるえた。なんという矛盾だ、なんという弱さだ。岩波は自分で自分がわからなかった。
人恋しさに堪えられなくなると、岩波は、親しい友へ手紙を書いた。伊藤長七、上野直昭、樋口長衛、吉崎淳成、林久男、阿部次郎などである。かれらからも返事があった。その多くは東京にもどって学業をつづけるよう勧告する文面であった。そのうち、最も親しかった林久男ははるばる島までやって来た。突然の友の来訪に喜んだ岩波は、夜中、湖を泳いで対岸のにふとんを借りに行き、村人を驚かしたこともある。【以下、次回】


















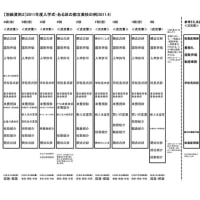
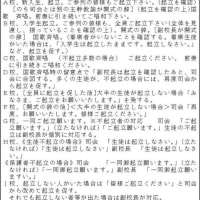








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます