ヨーテボリのハーフマラソン大会「Göteborgsvarvet」が開催された同じ週末、ヨーテボリの港に見慣れない軍艦があちこちに集結していた。NATO加盟国の海軍が寄港していたのだ。なぜかというと、NATOの共同軍事演習がバルト海で企画されていたためだ。


デンマークとスウェーデンの海峡での小規模な演習をしたあと、バルト海で大規模な軍事演習「Noble Mariner 2007」を行う。バルト海における有事を想定した演習で、民間の商船の保護も含んだものだという。そのために大小43のNATO艦艇とスウェーデン海軍の駆逐艦が、演習を控えてヨーテボリに立ち寄っていたのだった。
そのため、ハーフマラソン大会と同じ日に、ヨーテボリ市内では大きな抗議デモが繰り広げられた。その上、ハーフマラソンのコース上のあちこちには何者かが「NATO kommer. Spring för livet!(NATOがやって来るぞ。命が惜しければ走って逃げろ!)」と書いていた。(マラソンと掛けた機転の利いたジョーク&抗議に思わず笑ってしまった)
スウェーデン人の一部がNATO軍の寄港に大きく反発したのも無理はない。公式には非同盟・中立を維持しているスウェーデンの領海に、軍事同盟であるNATOの艦艇を入れてもいいのか、疑わしいからである。また、集団防衛行動のための共同演習を目的としたものであり、これまで行われてきた国連ミッションにおけるNATOとの協力とは、わけが違う。特に、抗議に加わった多くの人が「こうして共同訓練を重ねることで、NATO加盟のための既成事実が作られてしまうのではないか?」という恐れているようである。
さらに挙げられた問題は、今回寄港するNATO艦艇の中には核兵器を搭載している疑いがあるものが混じっていたことであった。スウェーデン政府としては、「スウェーデンの国内法が核搭載艦、および原子力推進艦をスウェーデンの領海に持ち込むことを禁じている」ということを演習参加国に通達するだけで、それ以上の手は打ったなかった。各国がこの法律を遵守してくれることを信じる、に留めたのだ。
ただ、今回のヨーテボリ寄港で注目されることになったNATOとの共同演習は、どうやら氷山の一角に過ぎないようだ。国連のマンデートの下での平和維持軍の活動(コソボ、アフガニスタン、レバノン沖の地中海など)は90年以降、NATOとの協力が欠かせなくなってきていることは、前回書いたとおりだが、それ以外にも協力関係は強まっている。例えば、スウェーデン空軍はアメリカでも訓練の一部を行っているし、その他にもスウェーデン海軍の潜水艦を乗組員付きでアメリカ軍に長期的に貸与し、浅海における索敵演習の標的として使わせたりもしている。(アメリカを始めとするNATOとのこれらの連携は、スウェーデン国防省がどんどん推し進め、政府が追認する、という形で進んできたようだ。)
そのため、NATOとの密なる連携が既成事実として出来上がっているのなら、パートナーシップ協定に留めず、正式な加盟国になるべきではないか?という声も強い。現在の中道右派政権を構成する保守党と自由党は、まさにこの立場である。彼らが言うには「今のような協力関係だけでは中途半端。加盟国との情報共有が保証されているわけではないし、NATOの政策決定における影響力もない。今後さまざまな国連ミッションでNATOの協力がますます強まるのなら、それならいっそのこと正式加盟国になって、影響力を持とうではないか」ということである。さらに「近年の国防軍縮小でスウェーデン軍には自国防衛の能力はなくなった。可能性が小さいとはいえ、起こりうる外的脅威に対抗するためには、スウェーデンだけで国防軍を組織するよりも、NATOの集団安全保障の枠組みの中で国防を行うべき」という論拠もある。
ただ、去年の選挙戦では、この事項は大きなテーマにはならなかった。今でもこの点に関する世論の関心は低い。そのため、風もないのに余計な波を立てたくない国防大臣は、NATOとの協力関係は今後も強めていくが、NATO加盟は今の時点で議論すべき問題ではない、との立場を取っている。
スウェーデンにおける様々な意見を整理すると以下のようになる。
① 従来のような大規模徴兵制によって、非同盟中立を裏付けられる 規模の国防軍を維持すべき・・・ 左派の論客(作家)であるJan Gillouなど
② 国防軍を縮小し、なおかつ非同盟中立を今後も維持すべき・・・左党、環境党、社会民主党(?)
③ 国防軍を縮小する一方で、NATOへの加盟を実現していくべき・・・保守党、自由党、それに加え、社会民主党(?)
----------
統一通貨ユーロへの参加の是非を巡る論争と同じように、非同盟中立の理念とNATOへの加盟をめぐる論争でも、「wait & see」の立場で傍観するか、積極的に加わっていくべきか、が問われている。
私が思うに、本当にその必要がないならば、これまでの方針(つまり、非同盟中立)を変えず(つまり、NATOには加わらず)、刻々と変化する日々の情勢(つまり、国連ミッションにおけるNATOとの連携増大)には、解釈の変更などで対応していく道もいいのではないか、と思う。


デンマークとスウェーデンの海峡での小規模な演習をしたあと、バルト海で大規模な軍事演習「Noble Mariner 2007」を行う。バルト海における有事を想定した演習で、民間の商船の保護も含んだものだという。そのために大小43のNATO艦艇とスウェーデン海軍の駆逐艦が、演習を控えてヨーテボリに立ち寄っていたのだった。
そのため、ハーフマラソン大会と同じ日に、ヨーテボリ市内では大きな抗議デモが繰り広げられた。その上、ハーフマラソンのコース上のあちこちには何者かが「NATO kommer. Spring för livet!(NATOがやって来るぞ。命が惜しければ走って逃げろ!)」と書いていた。(マラソンと掛けた機転の利いたジョーク&抗議に思わず笑ってしまった)
スウェーデン人の一部がNATO軍の寄港に大きく反発したのも無理はない。公式には非同盟・中立を維持しているスウェーデンの領海に、軍事同盟であるNATOの艦艇を入れてもいいのか、疑わしいからである。また、集団防衛行動のための共同演習を目的としたものであり、これまで行われてきた国連ミッションにおけるNATOとの協力とは、わけが違う。特に、抗議に加わった多くの人が「こうして共同訓練を重ねることで、NATO加盟のための既成事実が作られてしまうのではないか?」という恐れているようである。
さらに挙げられた問題は、今回寄港するNATO艦艇の中には核兵器を搭載している疑いがあるものが混じっていたことであった。スウェーデン政府としては、「スウェーデンの国内法が核搭載艦、および原子力推進艦をスウェーデンの領海に持ち込むことを禁じている」ということを演習参加国に通達するだけで、それ以上の手は打ったなかった。各国がこの法律を遵守してくれることを信じる、に留めたのだ。
ただ、今回のヨーテボリ寄港で注目されることになったNATOとの共同演習は、どうやら氷山の一角に過ぎないようだ。国連のマンデートの下での平和維持軍の活動(コソボ、アフガニスタン、レバノン沖の地中海など)は90年以降、NATOとの協力が欠かせなくなってきていることは、前回書いたとおりだが、それ以外にも協力関係は強まっている。例えば、スウェーデン空軍はアメリカでも訓練の一部を行っているし、その他にもスウェーデン海軍の潜水艦を乗組員付きでアメリカ軍に長期的に貸与し、浅海における索敵演習の標的として使わせたりもしている。(アメリカを始めとするNATOとのこれらの連携は、スウェーデン国防省がどんどん推し進め、政府が追認する、という形で進んできたようだ。)
そのため、NATOとの密なる連携が既成事実として出来上がっているのなら、パートナーシップ協定に留めず、正式な加盟国になるべきではないか?という声も強い。現在の中道右派政権を構成する保守党と自由党は、まさにこの立場である。彼らが言うには「今のような協力関係だけでは中途半端。加盟国との情報共有が保証されているわけではないし、NATOの政策決定における影響力もない。今後さまざまな国連ミッションでNATOの協力がますます強まるのなら、それならいっそのこと正式加盟国になって、影響力を持とうではないか」ということである。さらに「近年の国防軍縮小でスウェーデン軍には自国防衛の能力はなくなった。可能性が小さいとはいえ、起こりうる外的脅威に対抗するためには、スウェーデンだけで国防軍を組織するよりも、NATOの集団安全保障の枠組みの中で国防を行うべき」という論拠もある。
ただ、去年の選挙戦では、この事項は大きなテーマにはならなかった。今でもこの点に関する世論の関心は低い。そのため、風もないのに余計な波を立てたくない国防大臣は、NATOとの協力関係は今後も強めていくが、NATO加盟は今の時点で議論すべき問題ではない、との立場を取っている。
スウェーデンにおける様々な意見を整理すると以下のようになる。
① 従来のような大規模徴兵制によって、非同盟中立を裏付けられる 規模の国防軍を維持すべき・・・ 左派の論客(作家)であるJan Gillouなど
② 国防軍を縮小し、なおかつ非同盟中立を今後も維持すべき・・・左党、環境党、社会民主党(?)
③ 国防軍を縮小する一方で、NATOへの加盟を実現していくべき・・・保守党、自由党、それに加え、社会民主党(?)
統一通貨ユーロへの参加の是非を巡る論争と同じように、非同盟中立の理念とNATOへの加盟をめぐる論争でも、「wait & see」の立場で傍観するか、積極的に加わっていくべきか、が問われている。
私が思うに、本当にその必要がないならば、これまでの方針(つまり、非同盟中立)を変えず(つまり、NATOには加わらず)、刻々と変化する日々の情勢(つまり、国連ミッションにおけるNATOとの連携増大)には、解釈の変更などで対応していく道もいいのではないか、と思う。










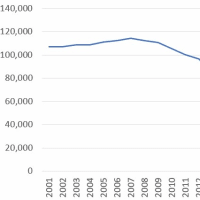
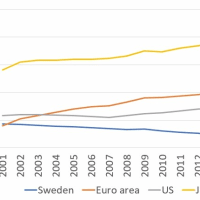
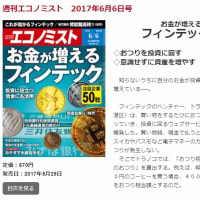
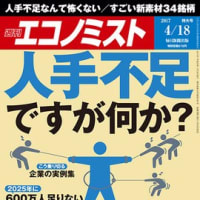






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます