
この童謡は何となく怖いイメージがある。歌を忘れたカナリヤは、捨てましょうか、埋めましょうか、ぶちましょうか、と言っている。いえいえ、それはかわいそう、という否定はついているが、およそ童謡の詩らしくない。時代背景(大正時代)からかと思っていたが、本当は辛い話がこの裏にあった。作詞家西條八十(やそ)の苦しみから生まれていた。詩を作る仕事に就きたいと願いながら、日々の生活に追われ、株の取引に明け暮れる自分を責めて作った歌であった。いえいえ、それはかわいそう、というのは妻の口癖だったとか。西條はカナリヤに自分を映して詩を作っていた。
そんな裏話を聞くと、過激とも思える言葉も少し納得できる。西條は大正7年(1918年)に作詞。これを成田為三が作曲、レコード化されたのは大正9年(1920年)。タイトルは「かなりや」であった。昭和27年(1952年)になって小学唱歌としてとりあげられ、その時「歌を忘れたカナリヤ」となった。
子供のころに何となく怖いと思ったイメージのせいか、大人になってもあまりなじめなかった。カナリヤと自分を重ねるほど自意識過剰であったとは思えないが、心に引っかかるように残っていた歌でもある。
童謡は子供の情緒的感性を育むための愛唱歌、おおいなる教育的目的を持っている。美しい日本語を残す意味もある。だから、子供に童謡の生まれた背景や真実を教える必要はない。そのままに歌ってもらえばいい。だが、大人になったなら、その真実を知ると言うことも時に必要だ。子供の時のイメージと大人になってからのイメージが変わったとしても。また、童謡を知った時の純粋な気持ちを再認識するためにも良いことだと思う。
調べてみると、結構怖い裏話を秘めた童謡がたくさんあった。「花いちもんめ」は人身売買の歌だったとか。花は女のこ、いちもんめは一匁。つまり重さから値段を決めたという説もある。「指切りげんまん」は遊女の話が原点。好きな人への誓いのために小指を切った事から伝わった。げんまんは拳骨一万発の意味。はりせんぼんは針を千本飲ますという意味。「てるてる坊主」は雨乞い師の話で、失敗すれば首を切られると言う話。「ちょうちょう」は浮気男の話というのがあるが、これはちょっとウソ臭い。昔この歌には二番があって、「栄ゆる御代」という歌詞があった。これは天皇を崇拝する意味があるからと言ってGHQが禁止したという話である。「あんたがたどこさ」は生活苦から売られた子供たちが集まって出身地を聞いた時の歌とか、「かごめかごめ」は流産の歌とか、「とおりゃんせ」は関所の歌とか、お産の歌とか。まあよくも、怖い話が次々と続く。真実はどうもよく分からないが、まだ他にもあるみたいだ。
人間は本当に哀しい時、それと真逆な世界に浸りたくなる。のどかな美しい童謡と現実のギャップに反発して、こうした風聞を生んだのかもしれない。それだけ童謡の世界と現実はかけ離れていたということなのか。現実が苦しいから美しい童謡の世界に浸るという証かもしれない。
童謡の作詞家でもあった野口雨情にもそれが覗える。彼が作詞した「しゃぼんだま」には、哀しい話が隠れている。彼の長女が生後わずか8日で亡くなった。やりきれない悲しみの中で作った歌がしゃぼん玉であった。「しゃぼん玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで、壊れて消えた」。美しくも儚いしゃぼん玉に託した雨情の悲痛な叫びが聞こえる。
彼の作詞した「赤い靴」にも哀しい事実が隠れている。異人さんに連れられて行った、というから人買いの話かと思っていたが、事実は違う。きみちゃんという幸薄い少女の話。生活苦から母親はきみちゃんを帰国間近のアメリカ人宣教師に養女として出す。母はその後、再婚するが養女に出した娘のことが忘れられず、雨情にその話をした。それをモチーフに生まれた詩がこれであった。母はずっとアメリカで暮らす娘を思ってこの歌をうたっていた。ところが事実は違っていた。きみちゃんはアメリカにわたる直前、結核に冒される。長い船旅に耐えられないという判断をした宣教師は孤児院に預けて旅立っていた。残されたきみちゃんはその孤児院で9歳の命を終える。雨情もきみちゃんの母もその事実を最後まで知らなかった。東京の麻布十番の商店街に行くときみちゃんの銅像がたっている。孤児院は麻布にあったからで、後年になって童謡の赤い靴を記念して建てられたのであった。
だが、最近となってこの話も嘘ではないかと言う説が出ている。きみちゃんは最初から孤児院に預けられていて、アメリカ人宣教師は関係ないとか、野口雨情は社会主義詩人で赤い靴は赤い国の共産主義を象徴した歌だとか、と主張する人もいる(永六輔)。そこまで話を膨らませると、ちょっといき過ぎだろうと感じる。とにもかくにも、裏話とは果てしなく広がるものだ、と感じる。
裏話を深く探るのは、真実から離れる結果になりかねない。やはり童謡は感じるままに歌うのが一番良い。余計な裏話は必要ない、という当たり前の結論にたどり着いていた。

歌を忘れたカナリヤは うしろの山に捨てましょうか
いえいえ、それはかわいそう
歌を忘れたカナリヤは 背戸の小藪に埋けましょうか
いえいえ、それはなりませぬ
歌を忘れたカナリヤは 柳の鞭でぶちましょうか
いえいえ、それはかわいそう
歌を忘れたカナリヤは 象牙の船に銀のかい
月夜の海に浮かべれば、忘れた歌を思い出す
なんとも言えない、怖さと甘さがあるな、やっぱり。今日4日は選挙の公示日。総選挙の口火が切られた。本来の目的を忘れて私利私欲で立候補する政治家が多くなった。彼らにあらためて言いたい。歌を忘れたカナリヤには、ならないでほしいと。
*カナリヤはカナリアとも表記するが、原詩がカナリヤであったのでそれに準じた。
















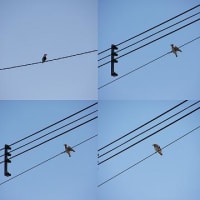


シャボン玉も歌を忘れたカナリヤもトおりゃんせも…。
昔の歌は、心情や時代や管理体制によってストレートに表現できない、体制への批判、皮肉をいろいろ潜ませた表現ですよね。
踊りにもそういう一面があって、フラダンスには「裏フラ」というのがある。もっともコチラはもっぱら性的な表現となるのですが…。
童話や寓話にも、イソップはじめグリムなど、オオカミが平気で人を食うなど、怖い話がいっぱいです。
これらは、もっぱら子供の躾に利用したんでしょうが、
子供らは怖いとは思わなかった。それに比べ、現代はイジメなど、虐殺など、芯から怖いことが増えましたね。
ところで、カナリヤの鳴き声をじっくり聞いたことがありますか。考えてみれば、ほとんど聞いたことがありません。でも歌声のように鳴くとか、きれいな声の代表として、ウグイスとともに並んでいます。本当かと思って鳴き声を検索してみました。やはりなかなかに良い声。さわやかな鳴き声でした。自然の中でこれを聞きわけるのはとても難しいように思いました。
親父がカナリアを多数飼ってた一時期があって、二年ほど多数のカナリアと暮らしてました。
当時は黄色カナリアより、オレンジのほうが人気があって、高く売れたようです。カナリアの声はいいですね。歌になるだけのことはあります。
私は生で聞いたことがありません。残念です。自然の中ではまったく聞きわける耳を持ってませんしね。もっとも、北海道の山にカナリヤはいるのかな?今度調べておきます。
しかし、動画(youtube)で何度も聞きましたが、心に残る声ですね。歌声に揶揄する気持ちがよくわかります。心が洗われます。それだけ汚れてしまったということなのかもしれませんが。
足の具合はいかがですか?調子を見ながら、一献の調節をお願いします。