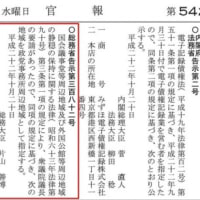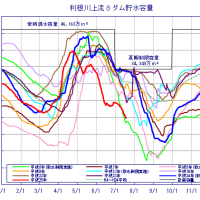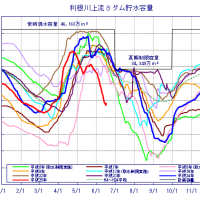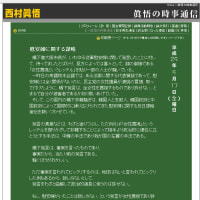国を憂い、われとわが身を甘やかすの記:意味不明な旧皇族「排除の論理」について
田原氏の男女同権論には、(心の中で)椅子がひっくり返る思いがした。言葉の力(猪瀬)は、ここでも大事なんだと。

たとえば、1日付の読売新聞は旧皇族復帰についてこう書いています。《政府は「(現在の旧皇族は)一般人として生まれており、多くの国民の理解が得られない」として否定的だ。》(中略)政府(官僚)は、新設する女性宮家の配偶者も皇族とする案を胸にあたためているわけです。純然たる民間人は皇族になれるが、旧皇族は世間が許さないという理屈にならない理屈は、どこから出てくるのか。私も百地氏と同様、この主張の異常さについて、1月6日付の産経紙面でこう書きました。《また、政府は、戦後皇籍離脱した旧皇族の復帰については「現天皇陛下との共通の祖先は約600年前までさかのぼる」とする17年の報告書を踏まえ、検討対象から外した。女性宮家の配偶者となる民間男性が皇族となるのに旧皇族は無理とするのは不合理ではないか。しかも旧皇族のうち竹田、北白川、朝香、東久邇の4宮家には明治天皇の皇女が嫁ぎ、東久邇宮家には昭和天皇の皇女も嫁いでいる。母方の系統とはいえ血縁は近い。》旧皇族の復帰を排除しつつ、一般民間人の皇族化を推進するのは、異常としか言いようがない。「女性宮家」の条件は、旧皇族の男系男子との婚姻に限るのが最低ラインであり、言い換えると、「女性宮家」創設は旧皇族男系の皇統復帰とイコール、同じ意味になる。しかしそうなると、「女性宮家」というより、旧皇族男系の皇統復帰が主であり、出来るのは「男性宮家」に他ならない。もちろん(どうせ法改正を前提とはするが)旧皇族男系男子(既婚未婚を問わず)を現在の宮家の養子にする手もある。いずれにせよ、こうした事は全て、ありていに申せば、皇籍復帰の方便に他ならない。形式は整える。「女性宮家創設」が「旧皇族男系男子」の皇籍復帰の排除なのか、皇籍復帰の方便になるのか。確かに予断は許さない。
田原氏の男女同権論には、(心の中で)椅子がひっくり返る思いがした。言葉の力(猪瀬)は、ここでも大事なんだと。