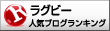ネットを通じて様々な音楽が大量に流れ込んでくる現代社会。それは果たして音楽ファンにとって幸福なことなのだろうか?と未だにレコードプレーヤーやカセットデッキから出てくる音を愛しているアナクロ、ではなくてアナログ音楽愛好家は想う。
大量に音がダウンロードできるということは、言い換えれば、大量に音が捨てられているということも意味する。ミュージシャン達が心を込めて創り上げた作品が、DELキーで一瞬のうちに「削除」されてしまうのだ。1ヶ月に1枚しか買えないレコードを、気に入ろうが気に入るまいが、それこそ盤が擦り切れるまで聴いた(聴くしかなかった)少年時代の体験を未だに引きずっている人間にとって、それは耐えがたい行為なのだ。
最初はさっぱりだった曲が、ある日突然悟りを開いたかのように心の扉を開いたりすることがあるから音楽は面白い。さわりだけ聴いて気に入らなければ捨てるという行為からは、けして生まれ得ない素晴らしい体験もある。もちろん、何度聴いても「こらアカンわぁ」というのもあるのだけれど、1枚のレコード(CDでもよい)ととことん付き合ってみることが、かけがえのない楽しみであり続けている。
そのような音楽とつきあい方の原点を振り返ってみると、結局はこの作品に辿り着く。サンタナが1972年にリリースした『キャラヴァンサライ』。この盤には何度針を下ろしたことか。(ちなみにアナログレコードを聴く行為を「針を下ろす」と表現する。)レコード盤が擦り切れてしまうのを心配してカセットテープにダビングしたり、おそらく生涯で聴いた回数はナンバー1になるはず。最初に飛び出してくるのは楽器の音ではなく「コオロギ」の鳴き声なのだが、そのパターンも完全にマスターしているくらいだ。
サンタナと言えば、グラミー賞に輝いた『スーパーナチュラル』で大ブレークしたベテランギタリストという印象が強い。でも、私の少年時代の頃は『ウッドストック』で大暴れし、『ブラックマジックウーマン』でホームランをかっ飛ばし、『哀愁のヨーロッパ』で多くの音楽ファンを泣かせた官能的なギタリストとして多くのファンを獲得していた人だった。
そんなサンタナにとって、『キャラヴァンサライ』は異色の作品と言える。2作目の『天の守護神』でファンになった人を突き放すようなところがあった半面、私のように新たな音楽ファンを獲得した記念すべき作品でもあるのだ。コオロギ、サックスソロにウッドベースが登場と凡そロックらしくないオープニングから切れ目なしに6曲が続くA面の展開が素晴らしい。アルバムのクレジットを見ながら、いろんな楽器の音を覚えたのだった。
もちろん、この作品がサンタナがマイルス・デイヴィスの不朽の名作『ビッチズ・ブルー』に強く感化されて作ったものであるとか、肉を食べてしまったためワイルドが作品になってしまった(サンタナは当時宗教上の理由で肉食を絶っていた)とか、サンフランシスコのベイエリアにはニューヨークとは違ったチカーノ(メキシコ系アメリカ人)によるラテン音楽ファミリーが形成されていた、なんてことは知る由もなく、純粋に音を愉しんでいた。
しかし、この作品の醍醐味はB面にある。当時の多くのレコードはA面で大衆受けを狙い、B面でホンネを語るという手法がよくとられていた。テープの逆回転とラテンパーカッションを競演させた「フューチャー・プリミティブ」、アントニオ・カルロス・ジョビンの名曲「ストーンフラワー」を世界に知らしめた絶妙のカヴァー、NYのラテンジャズやサルサに通じるところもある「リズムの架け橋」、そして圧倒的な盛り上がりを見せてフィナーレを飾る「果てしなき道」。ブラジルとアフロキューバンを共存させ、しかもブラジルもサンバやボサノヴァではなくて北東部のリズム。何でも吸収してエネルギーに変えてしまうサンタナ・マジックが堪能できる作品になっている。
さて、この作品の魅力(魔力)は何処にあるのだろうか? それは、クロスオーヴァー/フュージョンの先駆けとも言える先進的なジャズに通じるコンセプトの音楽を、サンタナが殆ど自前のミュージシャンだけで成し遂げていることではないかと思う。ジャズ畑の巧いミュージシャンを使ったら、こんなに熱のこもった音楽ができあがっただろうか? スポーツに例えれば、雑草軍団がエリートで固めたチームを倒すジャイアントキリングのような爽快感に満ちていることこそが、この作品の尽きぬ魅力になっているように思う。
この『キャラヴァンサライ』をそれこそレコード盤が擦り切れるくらいに聴き込んだことが、その後出逢うことになる様々な音楽に親しむ上での最高のトレーニングになったことは間違いない。