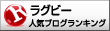エリック・ドルフィーが死の直前の1964 年にオランダで録音した『ラスト・デイト』もジャズのレコードをまだ全部で一桁の枚数しか保有していなかった頃に買った貴重なもの。
もちろん、この作品もジャズ史に残る名盤であることは間違いない。サイドメンはすべてオランダ人(ミッシャ・メンゲルベルグとハン・ベニンクは世界的にも有名)で録音場所もアメリカから遠く離れた欧州。さらに、ドルフィーが操る楽器もバス・クラリネットやフルートといったジャズでは主役ではない管楽器。
だから、内容はよくてもジャズを聴き始めた人が10枚目までに選ぶような作品とは思えない。では、なぜ私がこのアルバムを手にしたか?だが、高校時代のジャズ通の友人の影響以外には考えられない。「エリック・ドルフィーも聴くべし。」と勧められたことで、レコード屋に向かったのだった。でも、じゃぁ何を買えばいいのだろうか。
ここでも決定打になったのは「お値段」。クリフォードブラウンと同じで1,300円で売られていたのが、たまたま『ラスト・デイト』だったわけだ。「死を直前にした最後の演奏」という部分が気になったし、ジャケット裏面の油井正一さんの手になるライナーノーツを読んでいたら、聴きたくなってきたということもアシストになってはいるが。
家に帰ってきて早速レコードに針を下ろした時、飛び出してきた聞き慣れないサウンドにまず度肝を抜かれた。それがバスクラリネットのそろ演奏に初めて接した瞬間でもあった。曲はセロニアス・モンクの「エピストロフィー」だが、当時は駆け出しだからまだモンクのことは知らない訳で、何だか面白い音楽を作る人だなぁという印象を持つに至る。もっとも、当時は、クラシック音楽でもありきたりのロマン派の音楽とは決別していて、20世紀から現代音楽へと耳が向いていた時期だったから、面白く聴けた。
A面の2曲目は一転して爽やかなフルートの演奏。秋に聴いたらさらに深く印象に残りそうだなと安心感を持つ。ラストのアルト・サックスの演奏を経て、レコード盤をひっくり返してB面を聴く。ここでもトップバッターはバスクラリネットだ。曲想もA面と似た感じで、残りは再びフルートとアルト・サックス。ここでふと思った。エリック・ドルフィーはなんて律儀は人なんだろうと。楽器の選択に関して平等で偏りがないのだから。
さて、B面の2曲目はこのアルバム中の白眉であるだけでなく、ドルフィはもとよりジャズ・フルートでももっとも美しい演奏と評される「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラブ・イズ」。そんな予備知識は全く持ち合わせない人間にも深い感銘を与える演奏だ。このレコードにしてとってもよかった!と思ったものだ。
でも、実は一番気に入ったのはラストのアルト・サックスで奏でられる「ミス・アン」。頭の中をそれこそグチャグチャにこねくり回してくれそうなフレーズが続くが、それがとても快感だったりするから不思議。そして、曲が終わった後にジャズ史でもミュージシャン自身が語った言葉(録音)では、もっとも有名な言葉が飛び出す。
“When music is over, it’s gone in the air. You can never capture it again.” 高校生でもしっかり聞き取れるくらいの明瞭な言葉により発現で、思わず納得もしたのだった。「確かに音楽は終わったら消えてなくなってしまう。二度と取り戻すことはできない。」と。
「ミス・アン」は今でも私的ベスト10に入っているくらいに愛している曲なので、このレコードもよく聴いた。ドルフィーはもとより、実はヨーロッパ・ジャズとの初めての邂逅であったりするのだが、件の名言も含めて「先入観なし」で楽しめたことがよかったのだと思う。やっぱり、ジャズは人がなんと言おうと自分の耳で感じて納得して聴くものなんだなぁと思ったのも、遡ってみればこのときが最初だったかもしれない。
件の名言に話を戻す。ドルフィーが言うように確かに音は空中に消えてしまう。でも、その後も数え切れないくらいのたくさんの人たちが「録音」のお陰で彼が残した素晴らしい演奏を楽しむことができるわけだ。
だから、ドルフィーの意図したところ(遺志)には反することにはなるが、「けして、そんなことはないんだよ。少なくとも聴く人の心に深く刻まれた感動は永遠に不滅だよ。」と天国に居るドルフィーに言い返すためにこの言葉は存在するのだと勝手に思っている。
今日は本当に久しぶりにレコードを針を下ろしてみた訳だが、上で書いたような思いを新たにすることができた。放送局でのスタジオライブ録音であり、音の録り方も欧州らしい楽器の響きを大切にしたライブな感覚ということもあってか、1974年発売のレコードなのにCDで聴き直してみたいという気持ちには全くならなかった。
理由を明確に述べることはできないのだが、どうもアナログ録音をデジタル化してしまうと、ノイズは除去され音は確かに綺麗になるかもしれないが、楽器の定位感というかリアリティが失われてしまうような気がしてならない。少なくともアナログ録音の前には、音はリスナーの耳に届くまで製作工程を通じて直接的に繋がっていたはず。何でもかんでもリマスターでいいのだろうかと思ったりもするこの頃だ。
◆Eric Dolphy Quatet “The Last Date”
1) Epistrophy (Thelonius Monk)
2) South Street Exit (Eric Dolphy)
3) The Madrig Speaks, The Panther Walks (Eric Dolphy)
4) Hypochiristmutreefuzz (Misha Mengelberg)
5) You Don’t Know What Love Is (Ray/De Paul)
6) Miss Ann (Eric Dolphy)
Eric Dolphy : Flute, Alto Saxophone & Bass Clarinet
Micha Mengelberg : Piano
Jacques Schols : Bass
Han Bennink : Drums
Recorded at Hilversum, Holland, on June 2, 1964