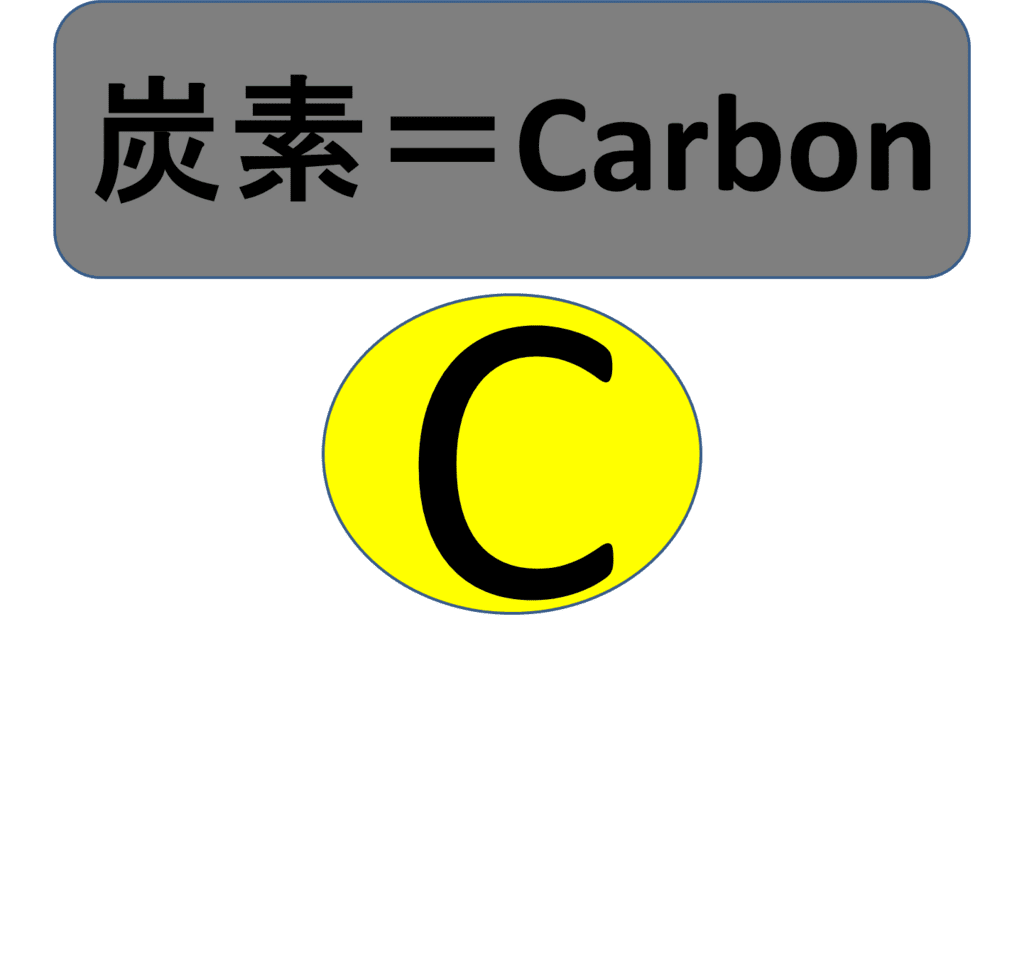
今の状態を放置していたらどうなるのか?
〇食糧危機
当ブログで毎月「世界の自然災害」を掲載してますが、いつも暑い国で雪が降ったり、乾燥地帯に大雨が降ったり、世界の多くの地域で洪水が起きたり、そんな状況を確認しています。
その地域に合った作物が作られているのに、そこで全く違う気象の変化が起きると当然作物がダメになります。
乾燥地域の大雨でバッタが異常発生しアフリカから中国までのバッタの移動で作物が大きなダメージを受けていることも掲載しました。
このように、例えばある種の大量の穀物を生産している地域が気象変化等で収穫できなくなる可能性は十分あります。
すでに、世界中ではたくさんの人が飢餓に苦しんでいる人々が多くいます。地球温暖化で気候が変化すれば、このような人たちはさらに追いつめられます。
一方、日本では、食べ残しや売れ残りの食べものが毎日大量に捨てられています。しかし、日本は食料を自国で調達しているわけではない。世界でも有数の食糧輸入国なのに。
他の先進国と比べても日本の食料自給率は特に低く、カロリーベースでわずか約37%しかない。
パンや麺の原料である小麦の自給率は約12%。日本食には欠かせない味噌・しょうゆ・豆腐等の原料である大豆でもアメリカやカナダなどからの輸入に頼っている。
最近、オーストラリアでは気候変動が目立ちますが、2006年の大干ばつで小麦の生産量が前年と比較して約60%減少し、輸出量が約3分の2に減少したことがありました。日本に大きな影響を及ぼしました。
〇食糧危機
当ブログで毎月「世界の自然災害」を掲載してますが、いつも暑い国で雪が降ったり、乾燥地帯に大雨が降ったり、世界の多くの地域で洪水が起きたり、そんな状況を確認しています。
その地域に合った作物が作られているのに、そこで全く違う気象の変化が起きると当然作物がダメになります。
乾燥地域の大雨でバッタが異常発生しアフリカから中国までのバッタの移動で作物が大きなダメージを受けていることも掲載しました。
このように、例えばある種の大量の穀物を生産している地域が気象変化等で収穫できなくなる可能性は十分あります。
すでに、世界中ではたくさんの人が飢餓に苦しんでいる人々が多くいます。地球温暖化で気候が変化すれば、このような人たちはさらに追いつめられます。
一方、日本では、食べ残しや売れ残りの食べものが毎日大量に捨てられています。しかし、日本は食料を自国で調達しているわけではない。世界でも有数の食糧輸入国なのに。
他の先進国と比べても日本の食料自給率は特に低く、カロリーベースでわずか約37%しかない。
パンや麺の原料である小麦の自給率は約12%。日本食には欠かせない味噌・しょうゆ・豆腐等の原料である大豆でもアメリカやカナダなどからの輸入に頼っている。
最近、オーストラリアでは気候変動が目立ちますが、2006年の大干ばつで小麦の生産量が前年と比較して約60%減少し、輸出量が約3分の2に減少したことがありました。日本に大きな影響を及ぼしました。
日本の米は大丈夫か?
お米の自給率は何とか約59%となっている。いや、約6割しかない。唯一のお米も輸入に頼るありさまです。
温暖化が進むとどうなるのか?
北日本では収穫量が増え、西日本では高温による生育障害が起こることが予測されています。病害虫・ウイルスにも新種が現れたりする可能性もある。
温暖化が進むとどうなるのか?
北日本では収穫量が増え、西日本では高温による生育障害が起こることが予測されています。病害虫・ウイルスにも新種が現れたりする可能性もある。

〇干ばつと大雨
温暖化が進むと、現在の乾燥地域での干ばつの頻度が増加し、乾燥地域が広がり乾燥亜熱帯地域では、地表水と地下水の水資源の減少が予測されている。
逆に、高緯度地域では大雨によるリスクが高まると予測されている。
大雨・洪水により地表の化学物質の堆積物や汚染物質が生活圏の地面を汚染する。洪水による上下水処理施設への障害などは、水資源の質を著しく低下させ、飲料水にリスクをもたらすと考えられている。
〇経済活動の不安定化
食料需給のアンバランスの増大、燃料の需給のアンバランス、投機資金の流入など、さまざまな理由によって様々な商品の価格が国際的に高騰する傾向にある。
温暖化が進むと、現在の乾燥地域での干ばつの頻度が増加し、乾燥地域が広がり乾燥亜熱帯地域では、地表水と地下水の水資源の減少が予測されている。
逆に、高緯度地域では大雨によるリスクが高まると予測されている。
大雨・洪水により地表の化学物質の堆積物や汚染物質が生活圏の地面を汚染する。洪水による上下水処理施設への障害などは、水資源の質を著しく低下させ、飲料水にリスクをもたらすと考えられている。
〇経済活動の不安定化
食料需給のアンバランスの増大、燃料の需給のアンバランス、投機資金の流入など、さまざまな理由によって様々な商品の価格が国際的に高騰する傾向にある。
参考資料:全国地球温暖化防止活動推進センター




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます