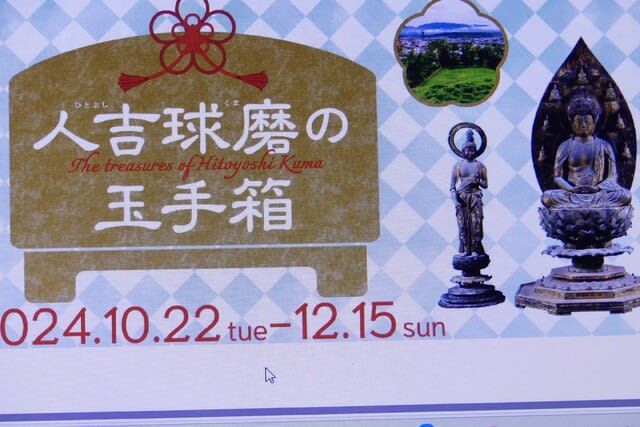2017年春にスタートした九州国立博物館でのボランティア活動。2020年春、新型コロナウイルス蔓延のため全体の終了式は開催されず研修室での感謝状受領。それから2年コロナで活動休止、23年に6期生を迎えて活動スタートして3年、足掛け8年にわたる活動が終了、5~6期で214名の終了者。6期生はこれから後半の3年間のボラ活動を7期生を迎えて始まる。
午前中、新方式のレンタル農園にでかけ、1時間あまり作業。合同でのジャガイモの植え付けやレタス株の植生、人参の種まきなどの作業。年会費は払わず、成果物を市価の半額程度で買い取る仕組みにかわった。あたらしい取り組みだがうまく行くかどうか。後の作業はベテランにまかせて11時過ぎ帰宅。そそくさと昼食をすませて徒歩で九博に向かう。終了式は13時スタート。終了後、別会場でわが部会のお別れ親睦会がある。ということで徒歩。

10分前会場のホール着。ボランティアの運営担当をしていただいたYさんやUさんの懐かしい人たちと再会。13時、現在の担当のTさんの司会で式典スタート。感謝状の各部代表への授与。館内案内や英語案内、中国語案内など12部門、214名が終了する。
その後、T館長より感謝の辞、荘子哲学から「道は瓦璧に在り」というはなむけの言葉。人の歩んでいくべき道は決して高尚な高みにあるのではなく身のまわりのどこにでも落ちているところにある。子供たちはなにも大谷並みの1000億プレーヤーなど目指すべきものではないないということか。いまさら人生下山中の我々にはどう受け止めるべきか。ひとさまのために小さな奉仕を黙々と続けよということだろう。

予定より1時間余り早く終了。我々の首にかかっていたId カードを返却、エントランスで部会メンバーとのお別れ交流やボラ担当スタッフとの記念写真。部門メンバーの集合写真。IS部会のSさんが私にどうしても感謝の挨拶をしたいと探しておられたとか。まあ私が趣味の写真をかしてボラ向け活動レポート誌づくりに奮闘したのをあり難く思ってくれていたらしい。私はなんとも思っていなかったがこうして思ってくれている人がおられたのは意外だったがうれしいことでした。

新しい九博の魅力になっている雲海桜はまだつぼみは硬い。満開の枝垂れ桜のもとで5期生の同窓会でもできたらいいなと思う。

動くエスカレーターをおりて天満宮へ。懇親会まで1時間弱ある。園内散策。ヒヨドリが梅の花の蜜をもとめて飛び回っている

3時半、懇親会場のVにつく。5~6期あわせて19名の参加。会費3000円。初の女性代表のMさんの開宴挨拶。挨拶も堂に行ってきた感じ。いろいろな企画提案で奮闘してきた5期のTさんの乾杯挨拶。大方のメンバーは赤や白のワインだったがTさんはレモン水。酒はだめらしい。いろいろあって面白い。前菜が終わったあたりで幹事のHさんが5期生メンバーに思い出のスピーチ依頼。各人がそれぞれ印象に残った話を紹介。思ってもみなかったことがスピーチにでてくる。人それぞれ対人関係ではそれぞれなりの印象をかかえてやってきたのだなと思う。
こんな懇親の場がないとほんとに人の気持ちはわからないものだ。6期のメンバーに7期生を迎えたら3か月くらいのタイミングで懇親会の場を設けることを提案。18時、博多一本締めでお開き、大変有意義で楽しいお別れ親睦会でした。8年、ともにやってきた5期生、グループラインをつくって連絡網を確保することに。
ワイングラス2杯と缶ビール1本だけだったが結構酔いがまわり、食べ物もそう多くはなかったが胃の膨満感がはげしく気分悪し。6時半のバスで帰路に就く。

スマホを開くと写真愛好会の大ベテランYさん、85歳、身体の具合が思わしくなく退会したいとグループラインへメッセージ投稿。新年会でも退会意思表示したらしいがメンバーに遺留されていたようだが体調だけはどうしようもなさそうだ。
写真にうつる私の顔をみても目の不調が顔の表情にあらわれてどうしても気持ちの良い顔つきでなくなってきている。意識して口角をあげて笑みが感じる表情をつくる努力をしていないと駄目なようですね・・・・・・・・