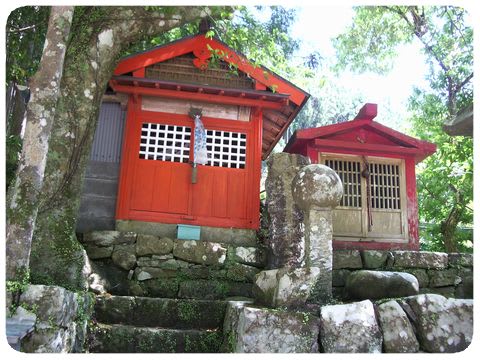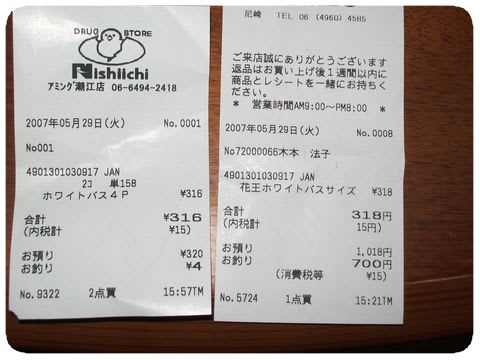雲ひとつ無い晴天に恵まれた日、中ノ島の国立国際美術館を訪れました。
ベルギー王立美術館展を鑑賞するためです。

土佐堀川の流れる筑前橋から西方向を眺めたら、次の橋は常安橋、私が痛い目にあった橋です。
右隅にチョコッと見える薄茶色の建物はロイヤルホテルです。
開場まで時間があったので、流れる水を動画に収めてみました。
10時の開館と同時に入場、あまり混雑も無く楽に観ることが出来ました。
展示の最初の頃は公爵だの伯爵だの人物画か宗教画が多く、暗いものが多いのですが、最後の方はかなり近代的なものもあり、絵として面白いものもありました。
先日見たギメ展の日本の浮世絵などと比べると、浮世絵が何かを訴えようとしているのではなく、構図とか配色に重きを置いているのに比べ、洋画は暮らしぶりや何かを訴えようと試みているのがよく判ります。

展示場ではカメラを向けることは出来ませんが、ここは休憩所、TVではここに絵画を運ばれてくる様子を映していました。修復している映像も見せていました。

これが国立国際美術館の入口、私はこの近くで28年間働き、以後10年程度経っていますが、ここで働いている当時はこの建物はありませんでした。
この敷地は昔の阪大の後地、隣の科学館は以前からありましたけどね。

帰りに私の骨折した地を訪れてみました。
この坂道の何処かで滑ってしまったのでした。
ベルギー王立美術館展を鑑賞するためです。

土佐堀川の流れる筑前橋から西方向を眺めたら、次の橋は常安橋、私が痛い目にあった橋です。
右隅にチョコッと見える薄茶色の建物はロイヤルホテルです。
開場まで時間があったので、流れる水を動画に収めてみました。
10時の開館と同時に入場、あまり混雑も無く楽に観ることが出来ました。
展示の最初の頃は公爵だの伯爵だの人物画か宗教画が多く、暗いものが多いのですが、最後の方はかなり近代的なものもあり、絵として面白いものもありました。
先日見たギメ展の日本の浮世絵などと比べると、浮世絵が何かを訴えようとしているのではなく、構図とか配色に重きを置いているのに比べ、洋画は暮らしぶりや何かを訴えようと試みているのがよく判ります。

展示場ではカメラを向けることは出来ませんが、ここは休憩所、TVではここに絵画を運ばれてくる様子を映していました。修復している映像も見せていました。

これが国立国際美術館の入口、私はこの近くで28年間働き、以後10年程度経っていますが、ここで働いている当時はこの建物はありませんでした。
この敷地は昔の阪大の後地、隣の科学館は以前からありましたけどね。

帰りに私の骨折した地を訪れてみました。
この坂道の何処かで滑ってしまったのでした。