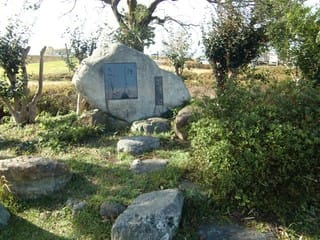島田市南にある「蓬莱(ほうらい)橋」。世界一長い歩行者や自転車専用の木造の有料橋。 通行料金は一回あたり、自転車と中学生以上が100円、子供は10円でそれ以外は通行禁止。

大井川右岸、蓬莱橋の正面に見える緑の一画は、全国でも有数の茶園として知られる牧之原台地。 橋ができる前、大井川は小舟で渡るしかなく、行き来する為には、時に非常な危険を伴うこともありました。

そこで、島田宿の開墾人総代達は、時の静岡県令(現在の知事)に橋をかける願いを出しました。 これが許可され、明治12年(1879)1月13日に農業用の橋として「蓬莱橋」が完成。

しかし木製の蓬萊橋は増水のたびに被害を受けた為、昭和40年に橋脚部分をコンクリートに変更。 現在も茶農家が対岸の茶園を管理するために利用しており、農道としての重要な役割を担っています。

さて、冒頭で世界一長いと書きましたが、ではその長さは・・・何と「897.4m」もあり、1997年12月「世界一長い木造歩道橋」として、英国ギネス社から認定を受けました。

またその長さの語呂から「8(や)9(く)7(な)4(し)」=「厄無し」として厄払いのスポットに。 更に「長(なが)い木(き)の橋」=「長生きの橋」として、長寿のご利益スポットとしても知られるようになりました。そういった事もあってかどうか、橋の対岸には七福神像など、様々なご利益スポットが点在しています。

2011年に訪ねた折は、災害の影響で橋の中央までしか渡れず断念。そんなわけで無事に再訪を果たすことが出来た今回は、もうワクワクが止まりません。お天気は良いし、12月なのにそれほど寒くも無く、しかも空は青く澄んで気分は上々。

橋の中ほどまで来たところで、左手に富士山を発見!!そうか、ここから富士山が見えるんだ! 富士山の下に見えている長い橋は「島田大橋」、942.5mで、蓬莱橋より50mほど長いのです。

と、そんなことはどうでも良くて(笑)橋の端が怖いはずの私が、今回ばかりはと端っこににじり寄り・・。富士山大好きで、静岡・山梨方面への旅の第一目的は「富士山」と言い切る私には最高の展望。 たとえ一瞬でも苦手な橋の上という怖さを忘れさせてしまうなんて、富士山の威力ってホント、侮れない(笑)

橋の中ほどから振り返って見ると島田の市街が遠くに見え、改めて橋の長さに思いをはせて感嘆の吐息。 左右に見えるのは、川越当時が想像できないほど水量の少ない、広大な砂地を見せる大井川。

先を行くご亭主殿がしきりに足元を指差し手招きするので近づいてみたら、なんとここが橋の「ど真ん中」だって! 気がつかなかったら絶対にそのまま行き過ぎていたかも、細かい目配りのご亭主殿に感謝(笑)

ワイワイと賑やかに橋を渡り終え、早速ご利益スポットと呼ばれる場所の散策に繰り出します。

足元には赤い実を付けた万年青と、万両の白実・・何かとっても縁起がよさそうで思わず顔がほころぶ(*^^*)。


御利益スポットの最初は「蓬莱吉祥天女像」。「蓬莱山」は不老不死の仙人が住むと云われた幻の山。

麗しい天女像に旅の無事と安全を願い・・少し足場は悪いけど、更に上に登ります。

「蓬莱の島台」と呼ばれる高台から見る蓬莱橋、こうしてみると結構沢山の人が行きかっています。

ご利益スポットの最初のご利益は、ここから見える富士山。ホント!何処から見ても富士山(笑)

橋を渡った先には、色々と話題になりそうな場所もありまだまだ紹介は終わりそうにありません。という事で、恒例の「続きはまた明日」・・・要するに何処も彼処も素敵すぎて、どれも端折れないのです(笑)

訪問日:2011年11月14日&2016年12月12日