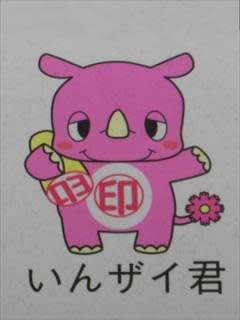山武郡横芝光町(よこしばひかりまち)は千葉県北東部に位置する町です。2006年3月27日、山武郡横芝町と匝瑳郡光町が合併して発足しました。東は匝瑳市、西は山武市、北は香取郡多古町、山武郡芝山町に隣接。成田空港の南側、太平洋に面し、九十九里浜および九十九里平野のほぼ中央に位置しており、中央部を九十九里平野最大の河川である栗山川が流れています。町内には国史跡の「芝山古墳群」や「小川台古墳群」があり、千葉県最古の形象埴輪が出土されています。またそれ以前の貝塚の出土から縄文中期にはすでに人の居住の形跡を見る事が出来ます。「町の木:梅」「町の花:桜」「町の鳥:コアジサシ」を制定。
キャッチフレーズは「栗山川の流れがはぐくむ 人・自然・文化が共生するまち ~協働のまちづくり~」

2006年3月27日制定の町章は「横芝光町の「よ(横芝)」「ひ(光)」をモチーフに、九十九里浜と太平洋、緑溢れる新町を組み合わせ、全体で新町建設に躍動する町民を描き「栗山川の流れがはぐくむ人・自然・文化が共生するまち」をデザインしました。」公式HPより
役場近くで唯一見つけた、「八匝(はっそう)水道企業団章」の規格消火栓。
横芝光町マスコットキャラクター『よこぴー』は、九十九里の海からやってきた謎の妖精。帽子には町の木「梅」と町の特産品の「ねぎ」。体は町の特産品「トマト」で、九十九里浜をイメージしたチョッキを着ています。

------------------------00----------------------
旧山武郡横芝町(よこしばまち)は、九十九里平野のほぼ中央に位置した町です。山武郡松尾町、蓮沼村、香取郡多古町、匝瑳郡野栄町、光町と隣接。九十九里浜沿岸地域のほぼ中央にあり、東は栗山川、南は九十九里浜に接し、南北に細長い地形をしています。 町の北部は起伏のある丘陵地帯で、畑地や森林からなる台地を形成、中央部から海岸部にいたる南東部は平地が続き、宅地や水田、畑作地帯になっています。「町の木:梅」を制定。
旧キャッチフレーズは「人、環境にやさしい横芝町」
明治22年(1889)、町村制の施行により、武射郡(むさぐん)旭村・大総村・上堺村が成発足。
1892年、旭村が改称、武射郡横芝村となる。
1897年、横芝村が町制を施行、武射郡横芝町(初代)が発足。
1955年、武射郡大総村、上堺村と合併、改めて横芝町となる。
2006年、匝瑳郡光町と合併、山武郡横芝光町となりました。
集排マンホールには、町章を中心に「町の木:梅」と「栗山川の鮭」が描かれています。栗山川は千葉県で唯一、鮭が遡上する川で、サケ回帰の南限とされています。(町立大総小学校付近の歩道ブロックの横に一枚)





昭和34年(1959)3月16日制定の町章は「「ヨコ芝」の文字を図案化したもので、三つの分線は、旧3町村を意味しています。また全体を円で構成し、その周辺に4枚の翼を配してありますが、円は合併により 新しく誕生した町が円満に融和することを、翼は未来への躍進を象徴しています」旧公式HPより

上水道関連の蓋は「山武郡市広域水道企業団章」の「消火栓」と「制水弁」


------------------------00----------------------
旧匝瑳郡光町(ひかりまち)は千葉県の東部、県立九十九里自然公園の中央に位置した町です。東は八日市場市・野栄町、西は栗山川を隔てて山武郡横芝町、北は香取郡多古町に隣接。町域の約70%は農地と山林で、町の北部一帯はゆるやかな丘陵地帯が断続し、台地は畑、低地には水田が広がっています。また中央部以南は、土地改良事業によって整然とした田畑がならんでおり、それが白砂青松の九十九里浜へ続いています。町名は、将来の栄光と一致団結、また輝かしい発展を願って「光町」と命名。「町の木:黒松」「町の花:桜」を制定。

旧光町の指定史跡「尾垂(おだれ)ヶ浜」にある、町指定史跡「成田山上陸地」。今回の旅で改めて成田山の歴史に触れる事が出来ました。

明治22年(1889)、町村制の施行により、匝瑳郡の南条村・東陽村・白浜村・日吉村が発足。
1954年、南条村、東陽村、白浜村、日吉村が合併、匝瑳郡光町が発足。
2006年、武射郡横芝町と合併して山武郡横芝光町となりました。
昭和30年3月制定の町章は「「光」の文字を図案化したもので、四つの空間は合併の関係4村を意味し、それを円によって「団結」と「輪」をシンボライズさせています。」旧公式HPより

旧光町域、二度の訪問でしつこく探しましたがマンホールらしいものは皆無。なんとも寂しい結果になりました。
撮影日:2014年5月19日&2019年3月10日