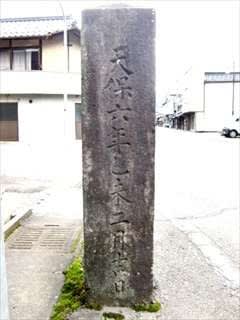豊岡市祥雲寺字二ヶ谷の一画、広大な敷地内に、人とコウノトリが共生できる環境と、学習の場を提供することを目的として設立された「県立コウノトリの郷公園」。


国の天然記念物であり、兵庫県の県鳥、豊岡市の市の鳥「コウノトリ」。羽は白と光沢のある黒、口ばしは濃い褐色で脚は赤く、目の周囲に赤いアイリングを持つ、コウノトリ目コウノトリ科に属する鳥類・別名、ニホンコウノトリ。

兵庫県北部の但馬地域には、コウノトリの野生繁殖個体群が日本で最後まで残っていましたが1971年に絶滅。それ以降、長い間、飼育下で保護増殖の努力が続けられてきました。そのかいあって、コウノトリの再導入が2005年9月24日の5個体のリリース(放鳥)により開始、2020年までに計74個体が野外に放たれました。


ケージの中ではなく、自由に動き回るコウノトリが見たい。豊岡にはそんな希望を叶えてくれる場所がある・・今回の但馬方面の車泊旅:楽しみの一つが今回のコウノトリ郷公園への訪問。

園内には「自然観察・学習ゾーン」があり、実際に餌をついばみ羽を休めるコウノトリを間近に見る事が出来ます。こんなにも美しい鳥が翼を広げ、かって但馬の空を自由に飛び交っていた時代があったのです。



まったくもって月並みな表現ですが、水辺を行き交うコウノトリの姿は本当に美しくて優雅。時折、羽を広げる姿などが見えると、もうそれだけで感動で満たされます😊


PM3時過ぎは餌やりタイム。タイミングが合えば、野生のコウノトリが見られる事もあるそうです。この時間にココに来れば美味しい食事がある事を知ってるのはサギも同じらしく、かなりの数のサギがせっせと美味しい餌にありついていました😅




併設された「豊岡市立コウノトリ文化館」ではコウノトリの飼育の様子や、放鳥に使われたゲージの展示等々、どれも非常に興味深いものばかり。

館内に入ると真っ先に目に映るのは、天井高く舞うコウノトリ・・の模型・・模型ですが綺麗です。

この剥製のコウノトリは、ここで飼育していたコウノトリでしょうか?大空高く自由に飛びまわっていた頃のままの美しい姿で、私たちを出迎えてくれます。その美しさが伝えてくれるものは、いかに大切に守られているかという事実・・・剥製の賛否は別にして素直に感動しました。

これは人工飼育の際に使われる時の「模擬くちばし」

かつて日本列島には、コウノトリが普通に棲息していました。けれども様々な要因が重なり、いつしか日本の大空を翔るコウノトリは完全に絶滅してしまいます。この空に再びコウノトリを・・・そんな願いを籠めて1985年、ロシアより幼鳥6羽を受贈し、飼育場での飼育が開始。試行錯誤の繰り返しの中、人工飼育開始から25年目の1989年、ついにコウノトリのヒナが誕生。

2005年には野生復帰の第一歩となる試験放鳥がスタート.。秋篠宮皇継殿下:紀子妃殿下ご臨席のもと、放鳥式典が行われました。

2007年には国内の野外では46年ぶりとなるヒナが巣立ちました。以後毎年野外繁殖が成功し、2020年には、野外コウノトリが200羽を超え、国内の各地でコウノトリを見かける機会が増えています。

2006年の歌会始、秋篠宮両殿下はこの放鳥の瞬間を待ちわびた人々の感動と喜びを御歌に詠まれました。
【 人々が 笑みを湛へて見送りし こふのとり今 空に羽ばたく 】皇継殿下
【 飛びたちて 大空にまふこふのとり 仰ぎてをれば 笑み栄えくる 】妃殿下

そしてこの年の九月六日、皇室の未来を担う日嗣の皇子がお生まれになられました。日本に神の存在を感じた・・鳥肌の立つようなあの感動が今も忘れられません。お健やかに、ただお健やかにと願いあげます。🙏

子宝を運ぶと言われるコウノトリ。コウノトリ郷公園では、大切な人に思いを伝える手紙もこんな風に大切に守ってくれてます😊

【ほろびゆくものは みな美しい しかし 滅びさせまいとする願いは もっと美しい】元兵庫県知事:阪本勝氏 心に響く言葉です。

訪問日:2011年3月30日