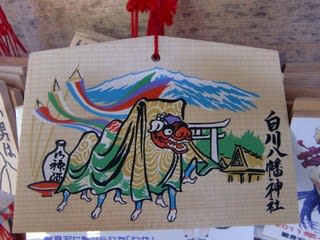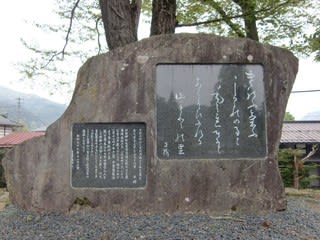白川郷の絶景スポットと言われる「荻町城址展望台」。ここからの景色を見ずして「白川郷に行ってきました」なんて、口が裂けても言えません。彼方に見える白山の力を借り、ついでに御亭主殿の手を借りて、山道の遊歩道をひたすら歩く事20分・・・

荻町を見下ろす山上展望台からの白川郷は、まさしくポスターで見た世界そのまま。

田植え前の水田、深い緑の山懐に抱かれた合掌造りの集落、手前に見えるあの大きな家屋が「和田家」、こうしてみるとその規模の大きさが一際目立つ・・はぁ~~~~byため息💗💛

「荻町城址展望台」と「天守閣展望台」は、どの観光案内でも「白川郷随一の撮影ポイント」として紹介されています。それが決して誇大表現でない事は、この場所に立てば納得の一目瞭然。

天守閣展望台では有料の記念撮影もあり、それとは別に自前のカメラで記念撮影もしてくれます。シャッター時の合言葉は「しらかわごぉ~」😄

遠くに雪を抱いた白山を望むロケーションは、内外問わず観光客に絶大な人気のスポット。カメラマンを担当してくれたご亭主殿のおかげで、忘れ難い記念の一枚となりました。

折角此処まで来たのだからと、城址らしき遺構を探索。とは言え本当に「らしいもの」は何もありません。唯一見つけた「荻町城址の空濠跡」をカメラに収めて、さて、再び下界を目指しますか。

登りに比べれば多少はましな筈!!と我が身を慰めつつ・・もと来た道を引き返します。やっとこさ平地について振り向けば、展望台が遠くに。そして目の前には、何度見ても見飽きない茅葺合掌集落の佇まい~💗

何といっても、今日は丸ごと一日、白川郷を楽しんでもいいと言われているので、名残惜しさに足が動かないなんて言い訳も必要なし!。目に入るもの全てが特別で、素晴らしくて!ああ、形容詞のボキャの少なさが恨めしい・・・・

足の向くままに歩いていると不思議なほど人気のない場所に出たりします。そこにはごく普通の日常があるだけなのに、やっぱり私には特別な一場面。そうして目の前に広がる、緑に包まれた穏やかな風景に見とれ、いつの間にか時の流れを忘れてしまうのです。

水田に映る合掌造りは「逆さ合掌造り」と呼ばれ、それはもう何も知らなくてもカメラを向けたくなる情景。

水が張られた田では「代掻き」をしている場面があちこちで見られました。世界遺産に登録され、世界に知られた「白川郷」ですが、そこには普通に人の営みが行われている日常があるのです。

目に入る風景の一つ一つがどれほど素晴らしくとも、そこに暮らす人たちの存在を忘れてはいけません。時折見かけてしまう心無い行為は、通り過ぎてしまう旅人の私さえも、眉をしかめ、胸を痛めるものです。

誰もが心惹かれる景色は、そこに暮らす人たちによって守られている事を、ここに訪れる誰もが心して欲しい・・・そう願わずにはいられません。

「「合掌造り」とは、木の梁を山形に組み合わせて建てられた日本独自の建築様式です。外から見たその形が、まるで掌を合わせたように見えることから「合掌」造りと呼ぶようになった等、諸説あるようです。白川郷の合掌造りは「切妻合掌造り」といわれ、屋根の両端が本を開いて立てたように三角形になっているのが特徴です。積雪が多く雪質が重いという白川郷の自然条件に適合した構造になっています。」白川郷観光協会公式ページ

訪問日:2012年5月19日