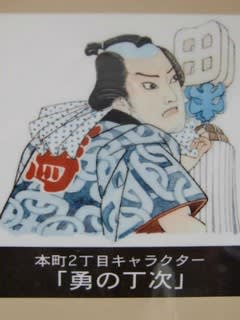見て面白いと思うものは人それぞれですが、我が家のご亭主殿、感性が似ているのか、それとも長い年月の間に私のツボに慣らされてしまったのか、街歩きの折々に、唐突に面白い発見をして楽しませてくれます😊

鍛冶橋の上にある手長足長の銅像、手長足長は出雲神話で簸川(ひのきかわ)の川上に住んだ足名椎(あしなづち)とその妻手名椎(てなづち)をモデルにしたとされています。なぜ「八岐大蛇」神話のヒロインである櫛名田比売(くしなだひめ)の両親の名がここに出てくるのか・・・しかもこんな「変わり果てた姿」で(大爆笑😆)

観光客が多く訪れる場所には、その土地ならではのお土産ショップが並び、見て歩くだけでも楽しいのですが、油断すると直ぐにお財布が緩むのが難点 😓 こちらはうさぎの雑貨:高山うさぎ舎の「うぼぼ」。キャラクターはこのお店だけのオリジナルで、「サルぼぼ」ならぬ「うぼぼ」・・・・まぁ、可愛いから何でもOK😆

「兎ぼぼ」があるなら「牛ぼぼ」だって有りですよね?、何といっても飛騨は「飛騨牛発祥の地」なのですから😊


布キャップ専門店の店先、入り口で頑張るマネキンさんのインパクトががあまりにも強くて、ご亭主殿、すっかりメロメロ 😍

こちらもご亭主殿の心を鷲づかみにしたマネキンの「獅子」。売り物よりもインパクトが強いってどうなの?・・・と言うか、何のお店だったっけ??

町歩きの途中で見かけた、祭礼の様子を描いたと思われる絵。もしかして上の獅子は、この獅子舞がモデルなのかな?

祭礼と言えば、町中で見かけた「屋台蔵」。高山祭りの屋台はこの中で解体されること無く保存されています。説明に掲載された美しい屋台を見ていると、人の多さが嫌いで祭りを敬遠してしまうご亭主殿も、心が動くようです。(屋台蔵と説明は別々)

豪華絢爛な屋台を彩る彫刻の数々、さて、この獅子の飾りは何処で見たものだったのか・・流石に8年も前の事なので記憶が・・・😓

観光地と言えばお約束の「顔出しパネル」、もちろん商店街のあちこちでミーハーな観光客(私たち)の足を引き止めてくれます。

高山の町歩き、フォルダを見返しながら「何と言ってもダントツはこれだよね」と、珍しく意見が一致した「とある理髪店」。ウインドウ越しの中の様子に釘付けの私たちを「どうぞ、中に入って見ていって」と、声をかけてくださったご主人に誘われて・・・いや~~~!!外で見るよりも更にパワーアップの店内に、テンションがあがりました😲

そもそも足を止めたきっかけは、壁から飛び出す龍の鏝絵。何とご主人の手作りだそうで、他にも紹介しきれないほど沢山の画像があるのですが、見るもの聞くもの、ただただ驚き。

美女の等身大看板収集が趣味との事で、実は彼女たちの為の住まいも別にあるとか。それに関してのテレビ取材も受けたそうで、当時の録画映像や、趣味と本職を兼ねた養蜂の話しなど、ついつい長居をしてしまいました。あれから八年ですが、今も沢山の美女に囲まれ、更にパワーアップされている事でしょう。その節は本当に楽しい時間を有難うございました。(顔出しOKの許可は頂きました)

しつこくもまだまだ続く「高山町歩き」続きは高山:ふらりそぞろ歩き~其の三で。
訪問日:2012年5月17日