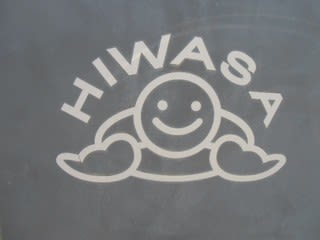旧海部郡日和佐町(ひわさちょう)は徳島県の南東部に位置した町です。海部郡由岐町・赤河内村(あかがわちそん)に隣接。町域の北から西は海部山脈を背にし、東から南は太平洋に面して大きく開けています。耕地は日和佐川・赤松川・北河内谷川・奥潟川などの流域に沿って帯状に点在し、日和佐川河口には臨海平地が開け、市街地を構成。地方港の指定を受けた「日和佐港」が町の中心部をなしています。海岸線は、風光明媚なリアス式海岸で千羽海崖やアカウミガメの産卵地:大浜海岸などを有し、室戸阿南海岸国定公園の中心に位置し、1967年に「大浜海岸のウミガメ及びその産卵地」として国の天然記念物に指定されました。「町の木:クスノキ」「町の花:桜」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、海部郡赤河内村 ・日和佐村が発足。
1907年、日和佐村が町制を施行、海部郡日和佐町(第1次)が発足。
1956年、赤河内村が日和佐町を編入・町制を施行し、海部郡赤河内町が発足。即日改称、海部郡日和佐町(第2次)が発足。
2006年、海部郡由岐町と合併、海部郡美波町となりました。
マンホールには、海に向かって泳ぎ出す「ウミガメ」と町章がデザインされています。(展示マンホールは美波町庁舎内。)




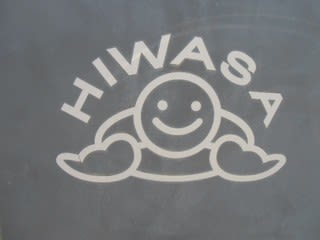
昭和10年7月23日制定の町章は「上半分は「日」・下半分は「三(佐)」を表し、薬王寺に因み、旭日昇天海辺の街の発展性を表したものです」合併協議会資料より


撮影日:2013年3月17日
------------------------00----------------------
旧海部郡由岐町(ゆきちょう)は徳島県の南東部に位置した町です。阿南市、日和佐町に、また紀伊水道を隔てて和歌山と隣接。町域は海岸線に細長いリアス式海岸でその入り江に八集落が点在。平坦地は少なく、ほとんどが山地で、太平洋に面した漁業の盛んな町で、特産品としてアワビ、サザエ、イセエビなどの魚介類、その加工品であるかまぼこなどが知られています。明治期、アメリカ船が志和岐沖で座礁した時には、村民総出で救出。それを聞いたアメリカ大統領から、銀メダルや賞状、250ドルを送られたという逸話も残されています。「町の木:うばめがし」「町の花:ツバキ」「町の鳥:メジロ」を制定。
明治22年(1889)、町村制の施行により、海部郡三岐田村・阿部村が発足。
1922年、三岐田村が町制を施行、海部郡三岐田町が発足。
1955年、海部郡三岐田町、阿部村が合併、海部郡由岐町が発足。
2006年、海部郡日和佐町と合併、海部郡美波町となりました。
昭和40年5月28日制定の町章は「ひらがなの「ゆき」を図案化したもので、全体的には平 和の象徴「はと」と、本町の飛躍的発展を表現し、部分的には 「船」「いかり」「波」をかたどり、港内に浮かぶ泊船を表し、港町 を強調しています。」合併協議会資料より

(※)旧海部郡由岐町は未訪問のため、マンホール画像はありません。